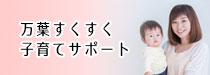本文
平成26年第2回大衡村議会定例会会議録 第1号
平成26年6月4日(水曜日)午前10時開会
出席議員(14名)
- 1番 小川ひろみ
- 2番 早坂 豊弘
- 3番 佐藤 貢
- 4番 齋藤 一郎
- 5番 佐々木春樹
- 6番 赤間しづ江
- 7番 高橋 浩之
- 8番 細川 幸郎
- 9番 佐藤 正志
- 10番 遠藤 昌一
- 11番 山路 澄雄
- 12番 佐々木金彌
- 13番 細川 運一
- 14番 萩原 達雄
欠席議員(なし)
説明のため出席した者の職氏名
- 村長 跡部 昌洋
- 教育長 庄子 明宏
- 総務課長 早坂 勝伸
- 住民税務課長 和泉 文雄
- 農林建設課長 齋藤 浩
- 都市整備課長 松木 浩一
- 会計管理者 木村 祐喜
- 副村長 伊藤 俊幸
- 監査委員 渡邉 保夫
- 財務調整監 織田 四郎
- 保健福祉課長 高嶋 由美
- 企画商工課長 文屋 寛
- 教育学習課長 佐々木 修
事務局出席職員氏名
- 事務局長 齋藤 善弘
- 書記 西村清二
- 書記 佐々木 敬
議事日程(第1号)
平成26年6月4日(水曜日)午前10時開会
諸般の報告
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 一般質問
本日の会議に付した事件
議事日程(第1号)に同じ
午前10時00分 開会
議長(萩原達雄君) おはようございます。
ただいまの出席議員は14名であります。
定足数に達しますので、ただいまから平成26年大衡村議会第2回定例会を開会いたします。
ここで、皆さんに議長より申し上げます。ただいま本村ではクールビズ施行中であります。上着を着用されている方は、着用を外されても結構であります。執行部におかれましても、そのようにお願いをいたしたいと思います。
これより諸般の報告を行います。議長としての報告事項並びに監査委員から報告のあった例月出納検査結果についての報告書は、お手元に配付している写しのとおりであります。
事務組合等に関する報告書については、議員控室に備えておりますので縦覧願います。
陳情書については、陳情書文書表のとおりであります。
次に、常任委員会の閉会中の所管事務調査に係る報告を行います。各委員長に報告を求めます。まず、佐藤正志総務民生常任委員長、登壇願います。
〔総務民生常任委員長 佐藤正志君 登壇〕
総務民生常任委員長(佐藤正志君) 皆さんおはようございます。
それでは、総務民生常任委員会の調査報告をします。
本委員会の閉会中の継続調査を行った所管事務調査について、次のとおりとなっております。会議規則第75条の規定により報告します。
調査事件、所管事務調査。
1番目に、環境管理センターの施設調査について(現地視察)。あと、ごみの収集運搬業務並びに分別収集状況について。3として、各課の所管事務について。
調査年月日は、平成26年5月22日に行っております。
調査内容、現地視察の件です。
黒川地域行政事務組合環境管理センターの施設調査について。これは、現地調査を5月22日に行ったものですが、ごみの焼却状況について、皆さんに配付のとおりになっておりますが、かなり施設も老朽化して、処理能力は80トンということで、1日16時間という、これが40トンのもの2基で処理してはいるというような状況でございましたけれども、かなり故障が多くて、下のほうにいきますと、この状況が写真で載っていますが、平成25年度ごみの収集運搬実績は、大衡村の黒の太枠で囲んでおります状況でございます。下の段が資源ごみということで、先ほどもちょっと控え室で話がありましたけれども、焼却炉の整備スケジュール、実質平成26年度から各設計ということで、平成26、27、28、29年ということで工事、工事が終わるのが平成29年ということで、実質稼働が始まるのが平成30年の4月1日からということでございます。
次に、5番目として、ごみの減量化強化推進についてということで、これもこの表に基づいて、平成26、27、28、29年として減量に努めていきたいということでありました。
今さっき申し上げたとおり、下のこの写真のとおりです。故障してピットに入り切らず、施設内に山積みになっていたということで、かなり量が多かったということです。これが、現状に3月の焼却炉故障、4月にクレーンが故障して、ちょうど私たちが調査に行った前日5月21日の午後から焼却が始まったということで、かなりの量が散乱していたというよりも、散乱ということではちょっと失礼ですけれども、ごみの山になっていたということでありました。
次に2ページ目、ごみ収集運搬業務並びに分別収集の状況についてということで、生活ごみ搬入量の推移ということで、この表のとおりにだんだんとふえていっているということで、平成25年度の搬入は過去最大だということで、かなりの量になっております。
次、2番目に、年度別ごみの総量と1人当たりの排出量ということで分けております。この表を見ていただければわかると思います。事業所からのごみがふえ続けて、約半分となっているというふうな説明でございます。
3番目は、ごみの量と種類別内訳、ごみの資源化率ということで、この表に載せております。ごらんになっていただきたいと思います。
次の3ページ、各課所管事務についてということで、放射性物質検査状況、平成25年度の検査実績でございます。この表のとおりでございます。平成26年度は、まだ4月現在ということで3件のみということでございました。
次に、財政課、平成25年度大衡村一般会計繰越明許費繰越計算書ということで、この表のごらんのとおりでございます。
次に、下のほう、平成25年度3月専決予算編成状況ということで、表のとおりでございます。
次に、住民税務課、条例改正(専決処分)についてということで、大衡村の税条例の一部改正条例ということで、法人税割税率の改正(第34条の4)ということで、10月1日施行ということで、市町村税が12.3%から9.7%ということでございます。また、軽自動車税率が引き上げということで、平成27年4月1日から施行されます。値段的に単価がこの表のとおりになっています。ごらんになっていただきたいと思います。
次に、大衡村国民健康保険条例の一部を、これも条例改正ということで、3番目も、大衡村企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例ということで、基本計画の同意期限を平成28年まで延長されるものとなっております。
次に、平成25年度の村税等の徴収実績です。平成26年3月末現在です。次の表のとおりでございます。
次に、保健福祉課からは、次のとおり平成25年度万葉クリーンエネルギーカー導入促進事業補助申請及び交付決定状況についてということで、ほかごらんのとおり、いろいろとこの報告書のとおり載っておりますので、ごらんになっていただきたいと思います。
以上、報告を終わります。
議長(萩原達雄君) 次に、佐々木春樹産業教育常任委員長、登壇願います。
〔産業教育常任委員長 佐々木春樹君 登壇〕
産業教育常任委員長(佐々木春樹君) おはようございます。
産業教育常任委員会が閉会中に継続調査として行った所管事務調査については、次のとおりであったので、会議規則第75条の規定により報告します。
調査事件、所管事務調査。
1)請負工事の現場調査について。
2)その他所管事務について。
2、調査年月日、平成26年5月21日。
調査結果は、別紙のとおりであります。
まず、現地調査ですが、尾無堰、西沢用排水路、西沢溜池、楽天イーグルス大衡球場、宮沢用排水路と、おのおの視察をしています。内容については、報告書に記載のとおりであります。特に、西沢の用排水路に関しては、現地地権者の方々が、便利になったというふうなお話が出ているというふうに報告を受けています。
請負工事について。
農林建設課、都市整備課、ともに記載のとおりの状況であります。震災後と若干変わりまして、ほぼ予定どおり進捗しているということですので、内容については資料をごらんください。
教育委員会について。
平成26年度の生涯教育の計画(主なもの)が載っております。これもご確認願います。
社会教育委員設置条例の全部改正について。
今回議案にもございますけれども、改正理由等々記載しておりますが、上位法、自治体で条例の設置ということで、内容的には変わらないというふうなご説明でしたけれども、大衡村で条例化するに当たり、委員の構成についてさらに検討していただきたいというふうなお話があり、教育委員会としても検討するというふうにお返事いただいております。
次のページに、農林建設課の行政区ごとの生産調整の表が記載されております。例年どおり行政区ごとに載っておりますが、現状超過達成しております。今村全体で105%ほどになっております。行政区ごとから見て、若干未達成になっているところもありますけれども、6月に転作確認を実施し、その際各行政区ごとに、目標を達成するよう若干調整をするとのことでありました。
4ページです。被災農業者向け経営体育成支援事業、経営体育成支援補助事業内容の内訳ということで説明がありました。冬の大雪に対するハウスの倒壊等に補助をするというふうなお話でしたが、さまざまな補助がございますので、その農家さんに合った支援を課では考えているというふうなお話がありました。
平成26年度道路調査(国道4号線拡幅)の見通しについてということで説明がありました。記載のとおりでありますし、同僚議員から質問もありますので、この辺で5ページに移ります。
都市整備課。
万葉の里・おおひら定住促進事業補助金交付状況についてということで説明があります。ときわ台がほぼ完売して、次々と宅地に建たれておりまして、今後も沓掛の万葉ヒルズ等からも可能性があるというふうなことで、当然予算を超せば補正を組んで対応するというふうなお話でした。
万葉パークゴルフ場の利用状況は、ごらんのとおりであります。
企画商工課から、大衡村のスマートコミュニティ化計画について概要を説明受けております。今後、今年度からスマートコミュニティ化に向けた施策・先導プロジェクトの実施検討並びに事業準備・実施を進める。また、中長期の取り組みになりますが、第5次の大衡村総合計画の最終年度の平成31年度を中期目標年次として進め、なお本計画については村のホームページで公開するとの説明がありました。
産業教育常任委員会の報告を終わります。
議長(萩原達雄君) 以上で諸般の報告を終わります。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
日程第1 会議録署名議員の指名
議長(萩原達雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を議題といたします。
会議録署名議員は、会議規則第115条の規定により、1番小川ひろみ君、2番早坂豊弘君の2名を指名いたします。
日程第2 会期の決定
議長(萩原達雄君) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
本件について議会運営委員長に委員会の報告を求めます。佐々木金彌議会運営委員長、登壇願います。
〔議会運営委員長 佐々木金彌君 登壇〕
議会運営委員長(佐々木金彌君) おはようございます。
本日招集されました平成26年第2回大衡村議会定例会の運営に関しまして、5月26日に議会運営委員会を開催しておりますので、その結果について報告いたします。
本定例会に付議されました案件は、村長提案の案件が10件であります。内訳は、専決処分承認が6件、条例制定1件、平成26年度各種会計の補正が2件、報告が1件であります。陳情に係る議案が2件、意見書に係る議案が2件となっております。
議案審議に先立ちまして一般質問を行うこととします。そして、一般質問は5名の議員から5件について通告されております。
以上の議案審議でありますので、本定例会の会期は、本日4日とあす5日の2日間としたいというふうに報告いたします。なお、先ほど議長から冒頭にクールビズについて話がありましたが、これは議会運営委員会で執行部を交えて、開会のときにはバッジをつけて一応やって、それから議長の宣告によってクールビズを実施すべきではないかというふうな点についても話し合われましたので、その点よろしくご協力をお願いしたいというふうに思います。
以上で報告を終わります。
議長(萩原達雄君) お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から6月5日までの2日間とすることにご異議ございませんか。
〔異議なし多数〕
議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、会期は本日より6月5日までの2日間と決定いたしました。
議長(萩原達雄君) ここで、村長に招集の挨拶並びに提案理由の説明を求めます。村長、登壇願います。
〔村長 跡部昌洋君 登壇〕
村長(跡部昌洋君) 皆さん、おはようございます。
平成26年第2回大衡村議会定例会を招集しましたところ、議員皆様方におかれましてはご多用のところご出席をいただきまして、まことにありがとうございました。
ここに、招集の挨拶並びに提案理由の説明をさせていただきます。
初めに、稲作の状況でありますが、田植えもすっかり終わりまして、この時期には比較的好天にも恵まれたのではないかなと思います。長期予報では、ことしの夏は冷夏だというふうな予報も出されておりますが、この予報が外れて、このままのいい天気で実りの秋を迎えてほしいなと、そんな願いでございます。
なお、TPP交渉の行方や農業再生のための農業改革案が、安倍総理みずから示されました。農業をとりまく環境は依然として厳しいものでありますが、よりよい改革を望むものでありまして、一層の情報の収集に努めるとともに、農家の皆様方へは随時いろいろな情報が入りましたら提供してまいりたいと、このように思っております。
交通安全関係につきましては、5月5日に死亡事故ゼロ1,231日を達成したことを受けて、宮城県知事から褒状をいただいております。今回の受賞は、平成22年12月に死亡事故が発生して以来2年と500日が経過したことによるものでございます。今後、この記録が長く続くよう、さらに大和警察署を初め関係機関と連携を図りながら、交通事故防止に向け、交通安全活動をさらに推進してまいる所存でございます。
5月18日には、王城寺原演習場を会場に宮城県林野火災防御訓練が実施されました。今回の訓練は、初めて実火を用いた訓練で、黒川4町村の消防団、宮城県内の消防本部、さらには陸上自衛隊、森林組合等々の関係機関の参加のもとに開催されたものでございます。また、放水に当たっては、1.5キロ離れた水源地から遠隔・遠距離送水訓練、宮城・福島・仙台市の防災ヘリや陸上自衛隊のヘリコプター合計6機による空中消火活動も行われ、より実践に近い訓練となりました。4月27日には、岩手県盛岡市において80ヘクタールに及ぶ林野火災が発生するなど、山火事は広範囲に及ぶものでありますので、今回の訓練は林野火災による被害を最小限に防ぐ手だてになるものと、大変期待をしているところでございます。
なお、今月15日には、大衡村消防団の消防演習が実施されますので、議員の皆さん方にはぜひご参加をいただき、消防団員の方々に激励をいただければ幸いと、このように思っております。
米軍移転訓練の関係でありますが、実はきのう、今回の米軍の司令官、オーエンズ中佐という方が来庁していただきまして、私たちに安心して安全な訓練をしてまいりたいと、このような言葉を述べていかれましたが、この実弾訓練が、あしたの5日から13日までの9日間射撃訓練が行われる予定になっております。昨年度に引き続き実施されるものでありますが、今月下旬に全ての資機材が撤収されるまでの期間中は、防犯協会、消防団を初めとする各種関係機関と連携を図りながらパトロールを行うとともに、東北防衛局とも連携を密にしながら、滞在中における事故などの未然防止に努めてまいる、そのような考えでございます。
本定例会に提案いたしました案件は10件であります。
議案第23号から議案第28号までは、専決処分の承認を求めるものでございます。
議案第23号と議案第24号は、地方税法の改正に伴い、大衡村税条例と国民健康保険税の条例の一部を改正するものでございます。
議案第25号は、省令の改正により大衡村企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正するものでございます。
議案第26号から議案第28号までは、平成25年度一般会計並びに国民健康保険事業勘定特別会計、介護保険事業勘定特別会計予算の専決処分をするものでございます。
議案第29号は、第3次地方分権一括法により、社会教育委員設置条例の全部を改正するものでございます。
議案第30号、一般会計予算の補正につきましては、9,831万1,000円を追加するもので、主なものは大雪による被災ビニールハウスの撤去及び設置補助金、定住促進住宅外壁のクラックの補修、そしてスクールバスの更新、中学校のコンピューター教育の学習用のパソコンの更新などでございます。
議案第31号、介護保険事業勘定特別会計予算の補正につきましては、介護保険事業計画策定業務に係る委託料を計上するもので、歳出のみ補正であります。
報告第1号は、一般会計の繰越明許費繰越計算書で、4事業を繰り越ししております。
以上9議案、報告1件をご提案いたしますので、原案どおりご可決賜りますようにお願い申し上げまして、招集の挨拶並びに提案理由の説明にかえさせていただきます。
日程第3 一般質問
議長(萩原達雄君) 次に、日程第3、一般質問を行います。
一般質問は、通告順に発言を許します。
まず、通告順1番、山路澄雄君、登壇願います。
〔11番 山路澄雄君 登壇〕
11番(山路澄雄君) 私は、通告したとおり、一般質問件名が、「日本創成会議」が公表した消滅自治体として大衡村もその一つに数えられている。今後の村の方針を問う、という件名でございます。
その中身は、まず一つに、2040年の若年女性、20歳から39歳までの人口、出産可能な若い女性の人口が、2010年と比較して57.2%の減少という予測が発表されました。村長は、この数字をどのように認識され、感想はどうであるか、まずもってお聞きするものであります。
第2点は、人口の急激な減少をどのように食いとめるか、今後の対策を早急に講じる必要があると思うが、考え方の基本を伺うものであります。
さて、全国の各自治体に非常な衝撃が走ったわけであります。それは、去る5月9日の新聞報道に、各自治体の首長初め議会関係者、職員もでしょうが、かなりの衝撃を受けたと、そのように推察されるわけでございます。狭い国内で、県内におきましても、県内23市町村が、創成会議の人口試算では消滅のおそれということで、これは朝日新聞の県内版でございますが、子供を産む世代の若年女性、20歳から39歳の2040年の人口推計と、2010年と比べて50%以上減る自治体は将来的に消滅する可能性があるとしています。大都市への人口移動が今後も続く前提で、震災の影響も反映しているそうでございます。50%以上減るとされているのは、南三陸町など23市町村ですが、南三陸町は約70%の減少と、県内で一番若年女性人口が減少するのが南三陸町であると。当大衡村は57.2%の減少、これも50%を超えていますので、近い将来消滅するという自治体に数えられているわけでございます。県内で唯一人口が増加するのは富谷町というふうに発表されました。富谷の若年女性人口の増加は8.3%でございます。隣の大和町も31.5%の減ということですが、50%よりはるかに低い状況であります。
我が大衡村、これまではトヨタ等の自動車関連企業の進出で、バラ色の将来が約束されたかのように、大変将来の見通しが明るいものと、そう信じてきた多くの村民の方々に、大きなショックと冷や水を浴びせかけられると、そういうような状況でございます。
この日本創成会議という組織でございますが、元岩手県知事増田寛也さん、岩手県知事を3期12年務められたようであります。その後、総務大臣として約2年、大臣を経験なさっています。現職は東京大学大学院客員教授という肩書であります。また、日本創成会議の座長であります。日本創成会議、座長談話が出ておりますが、中央公論の2014年6月号では、増田寛也さんはこのように述べています。「ストップ人口急減社会」というテーマでコメントを載せています。その内容は、「足元の定かではない目標を幾らいっても、本当の未来は展望できない。真に有効な対策を行うためには、人口減少社会の実像を私たちがきちんと認識する必要がある。今回、私はあえて消滅可能性都市を公表することにした。この現実を立脚点として、政治、行政、住民が一体となり議論し、知恵を絞る必要がある」そのように増田座長は述べています。そして、消滅可能性都市として全国に896、そのうち523、約60%は人口1万人以下の市町村、大衡も当然人口1万人ですから、その523の中に含まれるわけであります。
若年女性の定義でございますが、人口の再生産を担う20歳から39歳までの女性を若年女性と定義づけております。当然出産可能な女性年齢ということです。それから、大事な指標がありまして、人口の再生産力をあらわす指標というのがございまして、それを参考にして日本創成会議等はこの提言をしているはずですが、1、総再生産率、生産可能年齢の女性が次の世代の女子をどの程度再生産するかを示すと。それから、準再生産率、出生した女の子の死亡率を考慮したもの。こういう基礎的な数字を勘案しながら、今回の発表に至っているわけでございます。簡単な指標として、人口の再生産を担う20歳から39歳の女性人口そのものを取り上げたということであります。
私は、この新聞発表、それから増田寛也さんは人口問題について、日本創成会議の人口減少問題検討分科会の中で、さまざま人口の減少問題に取り組んできていまして、2013年の12月に日本の将来の人口について、滅亡する拠点都市と、そういうような提言もなさっています。日本創成会議のメンバーは何だと、そのような問いかけがあるかもしれませんので申し上げておきます。きちんとした民間の会議でございまして、日本創成会議人口減少問題検討分科会、そういう名称でございますが、増田寛也さんが座長でございます。その構成員は、野村資本市場研究所顧問の岡本 保さん、明治大学教授加藤久和さん、国立成育医療研究センター周産期・母性診療副センター長齊藤英和さん、東京大学大学院教授白波瀬佐和子さん、国際医療福祉大学大学院教授高橋 泰さん、G&S Global Advisors Inc.社長橘・フクシマ・咲江さん、前内閣官房参与丹呉泰健さん、慶応義塾大学教授樋口美雄さん、内閣官房参与平田竹男さん、政策研究大学院大学政策研究センター所長森地 茂さん、以上のきちんとしたそうそうたるメンバーが、この人口減少問題検討分科会のメンバーであります。そのようなきちんとしたこの日本創成会議人口減少問題検討分科会が提言している内容でございますので、将来の見通しに対してきちんとした分析を行い、きちんとした責任ある提言、公表を行ったと、そのように私は感じております。
その中で、「ストップ少子化・地方元気戦略」というのもございますが、これを挙げていますので述べてみたいと思います。人口急減の流れをストップさせるのは、さまざまな戦略がございますが、国のとるべき戦略と、村が、地方自治体が行うべきこと、さまざまございますが、国の問題として、やはり基本出生率、現在は合計特殊出生率、大体子供さん何人望むと、大体1.8人だそうですけれども、これを必ず実現させなければならない。他方、人口の低下に歯どめをかけようとしているところは、後から述べますけれども、長野県下條村、2.04という特殊出生率を誇って実現させていっている村もあるわけでございます。増田寛也さんがおっしゃっています若年人口の減少に注目した理由、それを最大のポイントにした理由は、人口の再生産を中心に担う20歳から39歳、平成24年特殊合計出生率、先ほど1.8と同じTFR、横文字出ますけれども、1.41のうち、95%の出産は20歳から39歳の女性によると、大方は20歳から39歳の女性が出産していると。それで、1組の夫婦がつくる子供が1.41、そのようになっています。若年女性が50%減少すると、出生率が上昇しても人口維持は困難というふうに定義づけております。また、人口の都市部への移動が収束しない場合、とまらない場合は、2010年から2040年の間に20歳から39歳の女性が50%に減少と、先ほど述べた896の自治体ですね。大変な問題なんです。50%以下に減少するというのは、非常に大変な問題なんですけれどね。
まず、これらの対策もさまざま講じていく必要がございますが、国の施策、各自治体の施策、さまざまございますが、国のやるべきことは、参考まで述べますが、国民の希望出生率の実現、1.81からもっと上げてやらなければならないんですけれども、東京一極集中の歯どめをかけるという。東京一極集中、人口集中がこれからまたますます進むというふうにこの会議では見ております。なぜかといいますと、いわゆる東京オリンピック、その他の問題、それから都市部の高齢化社会を支える介護の需要、介護労働力としての若い人たちの需要が都市部で非常に増大すると。そして、農村地帯、地方はどうかというと、介護する高齢者もだんだん人口が減って、若い人たちが働く場所が、介護関係でもなくなると。現在の大衡を見ても、介護の従事者というのはやっぱり女性の方々が主な方々でございまして、その方々が働く場所が地方ではだんだん減ると。東京等の都市部では超高齢化社会が来る、団塊の世代が75歳以上を迎えますあと10年後になると、物すごい超高齢化社会で、反面介護難民、介護のサービスを受けられない人たちが多く出てくると、そのように言われていますので、ますます地方から都市への人口流出は避けられないだろうと、そのように述べております。国のやるべきこと、東京一極集中の歯どめをかける、出生率1.8の実現、それから、これは第1次の2015年から2024年まではどうするかと、第2次として2025年から2034年、出生率2.1を実現し、将来人口の安定を図ると。かなり難しいことではないかと思うわけです。それで、増田さんのグループは、人口減少に対応する総合戦略本部を国で設けなさいと。それから、地域戦略協議会の設置、これは当然各地方自治体も入るべきと、そのように述べていらっしゃいます。
それでは、この人口減少に今まで取り組んできた先進的な自治体もあるわけでございます。私たち議会は、5年前長野県下條村を視察しました。その当時から、長野県下條村の伊藤村長のリーダーシップによって、少子化をとめて若者の定住がふえていると。それで、出生率も非常に上がったと、そのように大変全国から視察が相次いだ村でございます。
さまざまな施策をやっているわけですが、行政改革の推進は、まず当然行っております。無駄な金は一切使わないと。それで、次に特徴的なのが、いわゆる少子化対策の問題ですけれども、若者の定住促進住宅を建設しました。下條村では、平成9年から平成18年まで若者定住促進住宅を10棟124戸、1戸建て住宅54戸、合計178戸住宅を建てました。1戸建て2LDK、2台駐車場つきだそうです。家賃が月3万6,000円です。入居者数が590人、保育園児以下児童全体に占める居住の児童数が41.6%の子供さんたちが住んでいるそうです。家賃収入ですが、年間6,800万円のうち、約3カ月分の家賃で新たに2棟建築可能な額と、この家賃をまた再度住宅建設のために使っている。それから、中学生までの医療化を平成16年度から実施と、大衡村は18歳までは既に達成しているわけでございますが、保育料の10%引き下げを平成19年度から20年度連続実施、その他支援策として延長保育、学童保育等を積極的に実施しているということであります。
それで、平成15年から18年度特殊出生率、下條村では2.04人と。すごいですね、2.04人。これは長野県下第1位だそうです。全国では大体1.97人ぐらいになっているんですかね。そういうことで、非常に出生率が高い、2.04人、2人を超えているわけですからね。若年人口比率が17.1%、県下第1位だそうです。
それで、新しい施策をことしから進めているそうです。ことしから、第3子に出産祝い金10万円、第2子に5万円、第3子以上に20万円です。入学祝い金として、小学校入学時2万円相当の商品券、中学校入学時5万円相当の商品券。学校給食は、これまで40%の補助を行っていたが、50%にことしから引き上げたそうです。それで、現在の下條村の人口は4,024人、1,288世帯だそうです。このたびの日本創成会議発表のデータでは、2010年から2040年までの若年女子の人口ですが、2010年が438人、2040年が393人で、マイナス8.6%の減少と予測されています。これは、長野県で最下位だそうです。総人口も4,200人から3,793人ということで、減少率もかなり低い。このように、国内の4,000人足らずの地方自治体、特に大きな産業もない、産業集積もされていない下條村で、このように人口も減少させないで、子供さんも平均2.何人という高い出生率を誇っている。
このリーダーとしての資質が、このように一つの自治体を反映させ、消滅自治体というふうな不名誉な自体に陥らないと、このような事例もあるのですから、きちんとやはり政策の見直し、大衡村が、議会もですが、村長も、庁内の頭脳集団である職員の方々も、今回のこの衝撃的な発表に、幾らでも人口減、若年の女性が減らないような施策を一緒に取り組んでいかなければならないと思います。
あと、詳細については自席で行います。村長の丁寧なる答弁をお願いするものであります。以上です。
議長(萩原達雄君) 村長、答弁願います。
〔村長 跡部昌洋君 登壇〕
村長(跡部昌洋君) 答弁をいたします。
2点ほどの答弁でありますけれども、1点目のご質問ですが、日本創成会議が先月発表した人口減少の試算は、2005年、平成17年と2010年、平成22年の国勢調査における自治体間の人口移動の数値レベルが、2040年までに変化がなければそのままの数値レベルで継続していくという試算的なものが発表になりました。試算における出生率については、2012年の人口動態統計調査結果の全国平均の1.4倍を一律に使用して試算したものでありまして、大衡村は今のところ1.45ですけれども、今回の日本創成会議の試算結果が発表されたということであります。これまでも、人口減少とよく言われておりますけれども、このように数字的に発表されたのは今回初めてですけれども、これまであくまでも、今後30年先の推計した数字でありまして、今後自治体においては、人口減少を招かないように魅力あるまちづくりが最も重要であります。
次に、ことし5月末現在の本村の人口は5,715人となっており、近年本村の人口は増加傾向になっております。だから変化がないのではなく変化があります。主な要因は、自動車産業を中心とした企業立地が増加し、雇用機会が拡大していること、定住促進事業による助成制度や認定こども園、大衡村こども園の設置、万葉すくすく子育て医療費の助成など、今日までいろいろな政策を講じてまいりました。このあらわれが大衡村の今の姿にあるのではないかなと思っております。ときわ台も完売し、さらには五反田の部分もやや完売になっているのも聞いておりますし、あるいは松原の沓掛のところにある住宅団地も、やはりある住宅メーカーがてこ入れしたところ、今約10区画ぐらいの予約も出てきているということです。だから、あるメーカーのやっぱりそういう、ただこれは契約まではわかりませんけれども、まず今のところ予約は来ているというようなことも、やはり大衡村の今までの政策が皆さん方に理解をいただいて、そしてこのような形に進んできているのではないかなというふうに思っております。
今後も、これからの施策を継続するとともに、誘致企業の増加や若年層の移住で本村への住宅ニーズが高まっていることも受け、さらには塩浪地区の住宅団地の整備、これからかかりますし、あとは大規模開発で中心市街地形成計画、これも先日地権者の説明会を行いまして、やっと一歩進んだのかなと思っておりますけれども、これらも計画どおり確実に進めながら、今後の本村のさらなる人口増を図ってまいりたいと、このように思っております。
ですから、大衡村も今日までいろいろな政策を講じてまいりました。山路議員にはことごとく反対されましたけれども。でも、これが実際にいろいろな大衡村の住宅団地に来られた方々の話を聞くと、私たちがやっていた政策が理解いただいたからこそ、このような形で皆さん方が大衡村に住んでいただいたということでございます。
あとは、これについては一自治体でなんかとてもじゃないけどできませんよ。国を挙げて少子化の解消をしていかなければ、絶対に私はいいところと衰退していくところと伸びていくところ、たくさんあると思いますね。国の政策が、私は一番今回の発表のポイントではないかなと思っております。その結果、やっと国のほうでも動き出したようですね。私たちは、国のほうに大衡村の子育て事業等々について、国会議員に何回となく郵送し、大衡村でこういうことをやっているのだけれども、この事業は国がやらなければならないですよと、小さな村がやるのではなく、国を挙げて少子化解消をやっていかなければならないんだよと、何回も国会議員に私は郵便で送りました。なかなかそれに、そうだなという国会議員の方も若干おりましたけれども、まだまだその流れになっていないと。ただ、大衡村が医療費の助成を始めて、そしてあのときは本当に15歳までの医療費の助成でしたけれども、びっくりされましたね。ほかの町長さんから、ありがた迷惑だ、そんな政策やめてくれなんて言われましたけれども、それが今は隣接の町、市、全部倣ってきたんですよ。だから、私たちは先にやっていたものを倣うのではなく、いち早くそれを取り入れてきて、それが隣接の自治体が一斉にほとんど今最高15歳ぐらいまでですか、確実にしている自治体もたくさん出てきましたし、あるいは小学校までの自治体もきております。これも、私は大衡村が一つの先駆者となって示したのが、そのあらわれではないかと思っておりますし、いろいろな首長さんからも、大分ありがた迷惑な話もされました。
国でも、今回人口減対策戦略本部というのが、この前新聞に載りました。6月3日、きのう載りました。そして、これは政府の骨太の方針ということで、私から見るとやっとここに来たかと思います。ただ、これはまだ一つのこういうことの構想ですから、具体的にではどうやっていくというのは、恐らく数年かかると思います。こういうものを、国を挙げて少子化解消し、そして各自治体が各自治体のあるべき政策を掲げて、そしてそれを選ぶのが国民でありますので、国民がどこの自治体に行ったらいい暮らしができるか、どこの自治体に行ったら子育てができるかというものを、やっぱり私は選択してくるのではないかなと。
今ときわ台に92宅場が完売し、9割方皆さんが住まわれております。その方々に、私は一人一人ずっと今日まで交付金を交付する際に聞いております。なぜ大衡に来たのですかと、なぜ大衡村を選んだのですかと、どちらさまが選んだのですか、お父さんですか、お母さんですか、全部聞きました。それは、大衡村というのは知らなかったと、でも家を建てたいということで、いろいろなホームページ、インターネット、あるいは不動産屋さんに聞いて、そして大衡村に決定をしましたということは、半分以上の方々でしたね。最初から大衡村に来たわけではないです。宮城県内の全部の自治体を見て、そしてやっぱり今女性の時代ですね、女性の奥さん方が決定するようですね。ですから、仙台に勤められている方、仙台市から大衡に来ました、お父さんは仙台市に通うのはかえって時間がかかるようになりました。あるいは、大崎の岩出山に勤めている方が、大崎市から大衡村に家を建ててくれました。皆さん、勤めるところが遠くなっても大衡を選ばれるということは、それだけの大衡村の魅力が、今まで住民の方々が、いろいろな方々が、反対する方もおりますけれども、それはそれですから、みんなで一丸となって今日までつくってきたと、このあらわれが私は今の大衡村があるのではないかなと思っています。これに満足することなく、これからもやっぱりいろいろな事業を展開し、そして人口をふやしていくと同時に、大衡村に住んでもらうということも大事ではないかなと。それから、大衡村の魅力をもっといろいろな政策で掲げてまいりたいと、このように思っておりますので、山路議員も反対ばかりしないで、そういうものに積極的に賛成をしていただければ、より早道でそういう政策が生まれてくるのではないかなと、このように思っております。
議長(萩原達雄君) ここで、休憩いたします。再開を11時15分といたします。
午前11時03分 休憩
午前11時15分 再開
議長(萩原達雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続けます。山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) 村長の第1回目の答弁で、さまざま大衡村の子育て支援等、住宅団地造成等に努力して、人口もふえているんだと、そのようにおっしゃいましたが、今回の日本創成会議の提言といいますか発表は、遠い将来といいますか、大した将来でもないんですね。25年後の各自治体の姿というものを、正式なきちんとした数字であらわしているんです。今日はどうあれ、将来のことに対して責任をこれまた持つのも村長であり、議会であると思うんです。それで、今がいいから大丈夫だという、そういうことは通用しないと思うのでありますが、村長、まず自席につきましてさまざまな統計、数字を見ますと、まず最初に村長の感想、所感をお聞きしますが、隣の大和町が31.5%、同じ企業も集積します、トヨタもありますが、31.5%しか若年女性が減少しないと。同じ黒川郡内で仙台都市圏の中の富谷町、単独市になろうとしていますが、物すごい勢いでございますが、富谷は8.3%ふえるというんです。また、隣の色麻町がかなり低いんです、50%ちょっと上ですか、大衡より若年女性が急激に減らないと、50%を超えていますけれども、消滅自治体というふうに一くくりでは言われますけれども、この数字を見て村長の率直な感想をお聞きします。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 感想と言われても、感想なんかない。それぞれの自治体が一生懸命に、それぞれの政策を掲げて頑張っているなと。大衡村も、さっき、これで満足だ、ではないんだと、私は満足と言った言葉は一言もありませんよ。誰も、今までこういうことをやってきたから、さらにいろいろな政策を掲げてもっとやっていかなければならないんだという言葉を私は言いましたけれども、満足だという言葉は一回もございませんね。言わないことを言ったとは言わないでください。
議長(萩原達雄君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) 特に感想がないということは、村長、あなたは何も考えていないという、そういうことですよ、私はそう思います。少なくとも、大衡村をよくしよう、将来の大衡村に豊かなすばらしい資本を残していこうという、そういうふうに選挙のときはおっしゃっているのではないですか。何も感想がないんですか、本当に。何かあるでしょう。もう一度確認します。何も感想がないんですか、この数字を分析する気もないんですか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 感想は、さっき言ったでしょう、皆さん各自治体で一生懸命頑張っているなと。大衡村も今まで頑張ってきたんだよということですから、それ以上のこと何かあるんですか。
議長(萩原達雄君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) 大郷は62.8%の減少です。大衡は57.2%の減少予測と。それでは、大衡村は頑張ってきたけれども、何でこんなに若年女性が減ると日本創成会議で発表したんですか。どのように感じますか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) その会議に私は入っていないから、その数字がどのような形になってきたかわかりません。その会議の、こういうのが出たのがどうだと言われても、私は答えるものがございません。
議長(萩原達雄君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) いつものパターンで、議員の真摯な質問、真面目な質問、自分から真面目な質問と言うのもおかしいですけれども、一生懸命質問しているんです。答弁なさっていない。答弁できないんですか。したくないんですか。
それでは、質問を変えます。同じようなパターンでしょうけれども。
トヨタが進出している、現在いる岩手県金ケ崎、それから九州の宮若、それから静岡県の御殿場、この自治体、50%ラインに入っていません。トヨタ集積自治体、なぜ大衡だけが57.2%に上昇するのか、若年女性の減少が。分析してみようと思いますか。感想と、それからこれからどう分析していくか、分析する気がありますか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 突然そんなことを言われたって、答えることはございませんけれども。宮若市、あれも大分、何年前だったかな、五、六年ぐらい前だったかな、テレビの番組で宮若市の税収が減収になってきて大変だということで、大きなニュースとして番組として取り上げられて、私もたまたまその番組を見ておりました。それぞれの企業の関係は、よくなったり悪くなったりしていくのではないですかね。だから、それをいちいち取り上げてどうのこうのではない。やっぱり行政というのは長期的な観点から見据えて、少しずつやっていかなければならない。だから大衡村だって、今から20年前と今、どう変わりましたか。20年前のままだったら、私が何を言われてもしようがないですよ。大きく変わってきたのではないですか。それは、大衡村の住民初め、県民の方々からいろいろなご協力をいただいてきたということだと思いますね。逆に、参考に聞きたいと思いますけれども、山路議員は、ではどうしたらこの会議の発表されたやつを解消できると思うんですか。私は、先ほど私なりに申し上げました。山路議員はどういう考えでおられるのか、それを参考にお聞きしたいと、それによって議論したいなと思っております。
議長(萩原達雄君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) あと18分ありますから、最後に私の考えをきちんとまとめてきましたので、申し上げますから。ただ、今まで質問しても何にも答弁しない。答弁できないのか、しないのか、どちらかと。答弁しないほうと捉えているんですけれども。
大衡村の人口は、平成12年には6,133人でした。男が3,039人、女性が3,094人。うち20歳から39歳までのいわゆる若年女性人口は705人です。平成24年、総人口5,533人、うち男性が2,763人、女性が2,770人です。いわゆる出産可能な20歳から39歳までの若年女性が630人ですよ。だんだん減っているんです、若い女性。村長は、きちんと答弁しないんですけれども、多分事務方は答弁書をきちんと上げていると思うんですけれども、なぜ誠意を持った答弁をなさらないかと。毎回同じですね、誠意のない答弁。一体村長をやる資格あるんですかね、私非常に疑問に思いますよ。私たちは、真剣に村長にお聞きしているんですよ。村の施策、村長の考え方。それに答弁なさらない。この数字を見て、村長はどのように感じますか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 答弁しているでしょう。ただ、質問する内容が全然ちぐはぐだから答弁がなかなかかみ合わないだけであって、答弁していますよ。一問一答ですから、それなりに答弁はしております。私が言った、山路議員のあれを出してください、それによって議論しますから。(議員の声あり)それで答弁しろって。(「感想」の声あり)感想。(議員の声あり)感想って、そのとおりではないですか、数字、はい。
議長(萩原達雄君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) ちょっと誠意のない答弁であります。きちんと、この役場の統計から引いてきた資料でございます。15年で約80人近く若年女性が減っていると、これ間違いないんです。これ将来的に、2040年まで考えれば、あの日本創成会議の統計、資料、全くうそではないですよ、これ。絶対こうなってくる。なぜ大衡に若年女性が減少の原因をもたらしているか。一つには、さまざまな施策とられても減っていくというのは、やっぱり女性が働く職場がないということですよ、第一に。私はそう思いますが。企業進出しましたけれども、多額の7億円の企業助成支援を行って、女性方の企業は何社ありまして、大衡の女性何人ぐらい勤めてますか統計とっていますか。
議長(萩原達雄君) 村長。(「なければないでいいです」の声あり)
村長(跡部昌洋君) そんなことで、この会議のもとの解消になるんですか、そんなことを言って。議論したいんです、私、議論。そんな、それが質問と議論のことなんですか。女性の働くところがないなんて、真っ赤なうそですよ。全然、今大衡村の女性が働くところで、女性を採用したいんだけれども応募してこないというのが企業さんの悩みくらい、働くところがあるんですよ、大衡村では。全く山路議員は認識と実際の世の中の流れというのはわからないんですね。山路議員、ではあなただったらそれをどうすれば解消するということは言ってください。なぜ言えないのですか、それだけ考えていないんでしょう。考えてないと思うんですよね。
議長(萩原達雄君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) 年収1,000万円以上稼いだ村長が、部下職員100人近くを従えている。私たち議員1人。1人で資料を集めこつこつやっているんですよ。当然あなたがきちんとその資料を集めて、答えを出すべきではないですか。もう本末転倒だよ。そういう村長の答弁というのは近隣にはないですよ、本当にひどい、全然変わっていないね。私もいろいろ方策は考えておりますよ。そして、増田寛也さんが書いているこの記事読みなさい、勉強しなさいよ。それから、昨年2013年12月に出した「壊死する地方都市」という、この二つですね、読んでくださいよ。そうすると、地方自治体はどうあるべきかときちんと書いていますよ。1,000円もしないんですよ、中央公論という雑誌。ほとんど村長勉強していないことが、ここに明らかになっていると。
それで、いわゆる女子型の企業が少ないと、私はそう見ているんですよ。それならば、各工場、村内女性が何人働いているか、きちんとした把握している人数を出してみてください。出していないでしょう。いわゆるこれからは、若い女性が働く場を確保しなさいと、増田さんが言っているんですよ、提言で、きちんと。
それから、これからはいわゆる30万人規模の中核都市で、きちんと国と直接する、県は要らないんだと、県をなしで直接国と交渉していく、そういうような中核都市をつくっていかなければ、中央、地方の拠点、そういうものをつくっていかなければならないと、増田さんばかりではなくて、ほかの地域問題、人口問題に精通した方々は言っています。村長、大分出張、県外になさっていますけれども、企業誘致だけに村長大分エネルギー費やしていますけれども、もう一度原点に返って大衡村の人たちが住みやすい村、そして若い女性が喜んで定着して、子供は2人以上つくれるような環境をつくっていくと、そういう方針を、長野県下條村はやっているんですから、4,700人で。たしか予算規模27億円ちょっとだ。下條村に視察に行ったことがありますか。きちんと勉強する気はありますか。名古屋の企業訪問だけしないで、そういう先進的な自治体、本当に山の中ですけれども、一生懸命頑張っていますよ、村長以下。そういうところに視察に行く気はないんですか。
それから、このごろ見たんですけれども、北海道の富良野市、大学生までこれから医療費の助成を行うそうです、行っているんだな。議会としても視察に行きたいと思っているんですけれども。やはり、もっと熱い施策を、女性それから子供に、当然教育環境の充実も必要ですけれども、下條村では学校給食50%補助すると言うんですよ。あの小さな自治体がやっていることができないはずないんです、大衡で。きちんと真剣に、この大衡村の将来を見据えた施策が行われなければならないんです。何かうわさによると、村長はいつも出張ばかりしていると、なかなか庁内に落ち着いていないと。この大変な時期に、発表されたものはきちんと精査して、大衡村に何が足りないかと、きちんと対策を練るべきですよ。庁内にもそういうプロジェクトチームですか、そういうものを立ち上げて、もっとじっくりにですね、企業が来たからいいと、今まではトヨタが来たと、将来がもうバラ色だという、そのように感じてきました、私もその一員でありますが、それではこれからの時代、自治体として成り立っていかないのだと痛感しているわけでございます。
村長は、提言しろと言うんですから、一応私の考えをまとめてきましたので、村長はほとんど無視なさるでしょうけれども、一応述べてみたいと思います。
大衡村の地域戦略はどうあるべきかと、私は箇条書きにまとめてみました。
地域の希望出生率の目標の設定と、地域人口のビジョンの策定と、まず第一。下條村は2.4ですか、そのようになっていますが、将来の地域人口のビジョンの策定も行わなければならないと。過去にとらわれないで、新しいビジョンの策定が必要ではないかと思います。
第2点、若者に魅力ある地域拠点都市を中核とする新たな集積構造、その形成とそれを支える自治体間の地域連携の具体的構想を策定する。特に、黒川地域の連携を、これからきちんと中身の濃いもので、首長はもちろん議会もですが、役場もそれから住民も、地域連携を、具体的構想をまとめて推し進めていかなければならないと。ワンマンプレーで単独で、大衡だけが生きればいいんだと、そのような時代はもう終わったんですよ。
3番目、若者が結婚し、子供を産み育てやすい環境をつくる。これは下條村が実践していますけれどもね。これは、国の問題にかかわりますが、年収500万円モデルと言いますけれども、なかなかこれは大変だと思います。ただ、結婚、妊娠、出産の支援はできますね、村独自で。若年層の収入アップは、やっぱり国とか企業とかそういう問題にもかかわってきますけれども、結婚、妊娠、出産支援は各自治体でできることでありますから。それで、結婚機会の提供と。なかなか結婚できない女性も男性も多いわけですね。テレビできのうもやっていましたかな、お見合い大作戦ですか。やっぱり、もう一度地方自治体も、結婚できない若い男性、女性のために一肌脱ぐ時代がまたやってきたようですね。それがいわゆる結婚機会の提供はもちろんですけれども、妊娠、出産知識の普及と、これも当然保健福祉課中心に実施されていると思いますが、もっと充実させたものにしなければならないと。妊娠、出産、子育てのワンストップ相談の支援と、そういうことが考えられると。
それから、子育て支援も大事でございますが、ひとり親家庭への手厚い支援、多子世帯への支援、下條村もやっていますけれども、子供が多いほど有利になる、多子世帯への村、自治体としての支援策を考えると。税的なもの、社会保障的なものは、国もですが、国がやるべきことでございますが、村長も国のほうに出向いたら、国会議員の方々に、先生方に法律の改正をお願いすると、そういう大事な仕事もあるのではないかと思います。
それで、大事なのは、若い女性の働く場所の確保ということですね。ことしの役場職員、男子5名採用ですが、女子が一人の採用もなかったと、村長応募がなかったと言えばそれまででございますが、女子の働く場所の機会をもっと広げてやらなければならないと、そのように思うわけでございます。これも、やはり立地企業に、誘致企業にひとつお願いして、若い女性が働ける職場というものをひとつ考えてほしいと、それも必要ではないかと。また、自治体としても、若い女性が働けるような、働く場所の提供を創出すると、働く場所をつくっていくと、そういう考えも必要ではないかと思います。
私は、あと交通の問題ですね。いわゆる交通の利便性、非常に大衡村、4号線は間もなく解決すると思いますが、県道仙台大衡線が宮床でストップしたままと。やはり、あの線を早急に開通させ、いわゆる通勤の足、それから通学の足、学校教育の問題は、いわゆる中学校までは何とかスクールバス等が運行されていますのでカバーできますけれども、高校に入ると、とたんに親の負担が急激に増すと。そういうところを、若い女性の方々が大衡村では教育環境に適したところではないと、そのように考えると、村内に居住するのを二の足を踏むのではないかと、そのように思うわけでございます。現在、大衡村の女性の労働力、吸収をしているのは、やはり一番大きいのが介護施設、介護事業所等でございますね。それから、24時間営業のいわゆる小売店があるという。
それから、もう一つ、観光というものは、なかなか大衡が取り組み難しいと思うんですけれども、河北新報にも載りましたが、企業の立地を観光に絡めていくんだというふうなことをおっしゃっていますけれども、観光の問題ももう一度きちんと考えてみる必要があるのではないかと思います。大崎市が、比較的人口減少率が低い、鬼首とかああいう山間僻地を抱えながらですね。やはり、医療、観光、さまざまな面でいわゆる広がりがあるのではないかと、若い女性が働く職場のですね。それで人口減少率が少ないのではないかと、そのように考えているわけです。
村長に、山路の考えを述べてみよと言われましたので、一応述べて終わりにしたいと思います。以上です。答弁要らない。
議長(萩原達雄君) 答弁要らない。ないよ、もう時間。するの、では村長。
村長(跡部昌洋君) 増田さんが言っている割合に、大変ちゃっこい何か提案ですけれども、私から見ると。今まで大衡村でずっとやってきたことなんですよ、それは。それが、そのことがだから、私そういうことをやってきたんですよ、今ずっと。(議員の声あり)だから、人口も大衡村では宮城県内で4番目にふえてきているんですよ。あと、女性の職場がないと、全然認識……、もう女性の職場、1,000人ぐらい働……職場あるんですよ、2つだ3つ合わせると。皆さんが言っているのは、大衡村の住民が働きに何で来ないんでしょうというのが、よくこの前も言われました、何で応募するんだけれども、大衡村から来てくれないんですよねと。今度新たに大きな会社が立地します。募集かけております。残念なのは、女性が応募してこなかったということが言われております。ですから、もう少し実態を把握して、そして勉強するのはあなたこそ勉強しなければならないと。(議員の声あり)以上でございますので。あと、出張も私の仕事ですから、はい。(議員の声あり)
議長(萩原達雄君) 次に、通告順2番、赤間しづ江君、登壇願います。
〔6番 赤間しづ江君 登壇〕
6番(赤間しづ江君) 私は、汚染牧草の一時保管対策について質問をいたします。
3月の定例会でも、これに触れておりますし、またかという思いで村長はいらっしゃるかもしれませんが、村民の安心・安全という部分もあります。ぜひともいい答えを期待して質問をいたします。
これは、大衡村の農業振興、それから村民の安全・安心な暮らし、大衡村のイメージへの影響、さらには黒川行政事務組合の環境管理センター、焼却炉等の整備計画などにもかかわる問題であり、村民は一日でも早く進めてほしい、そんな思いがあります。したがって、この質問をいたします。
福島第一原発の事故で発生した放射性セシウム濃度が1キログラム当たり8,000ベクレル以下の廃棄物は、一般の廃棄物として市町村が処理しなければならないことになっています。大衡村では、大和町、大郷町とともに黒川地域行政事務組合でごみの焼却、埋め立てを行っております。原発事故によって汚染された牧草の量が余りにも多く、放射能の濃度をコントロールしながら一般廃棄物と混ぜて慎重に焼却処理をしなければならない。そのため、焼却処分されるまでのめどが立たず、それぞれの町村で一時保管。ゆえに、この一時保管という言葉が使われております。
黒川地域行政事務組合で焼却されるまでの間、この一時保管について、3月の議会で事業内容が明らかにされました。当初予算では、畜産振興費に435万円計上されました。1カ所に集める汚染廃棄物は、村有地2反歩、20アールという面積であります。村内に野積みされている汚染牧草のロールは634ロール、シイタケのほだ木7万3,000本という数字でございます。3年も経過しておりますので、劣化の激しいものは再ラッピングして運び、3段重ね84ロールを1ブロックとし、8ブロックにして遮蔽シートで覆う方式をとるということでございました。さらに、要件として平坦地で工事等の必要のないもの、作業効率のよい場所、人家から距離のあるところ、そしてきちんと線量を調査し管理する、こうしたことを踏まえて一時保管するとのことでした。
事業内容についてここまで検討し、予算措置したのであれば、候補地発表も同時になされるのではと思っておりましたが、議員の一般質問や総括質疑においても、村長から保管場所についての答えはございませんでした。この問題は、間を置けば置くほど、先送りすればするほど住民の不安が増し、難しくなるとお話をしてまいりました。3年間野積みされたロールの劣化はひどい状況になっていると聞きます。営農にも支障を来しており、何とかしてほしいと話し合いを重ねてきた畜産酪農家の皆さんの切迫した思い、困り果てているその様子に応えるためにも、一日も早く保管場所の決定、選定要件、経過を示して早く村民に丁寧に説明していかないと、この事業は進まないと思います。村民の間にも、積み上げられているのが汚染牧草であり、いつまでも放置されていることから、そのロールの存在そのものに疑いを持って見られているところもあるようです。たとえ線量が低いといっても、安全に管理してくれることを一日も早くと望んでおります。
去る5月21日の産業教育常任委員会での説明は、数カ所の候補地を挙げている、しかし、まだ内容を検討中とのことでございました。そこで、現段階でも保管場所を絞り込めないその理由は何なのでしょうか。ネックになっているのは何なのでしょうか。
2番目は、その保管場所の決定の時期をいつとするお考えなのか。
3点目には、放射性廃棄物など一時保管することになった、きちんとした村民への理解を得るための説明会等々、そうしたこれからの一日も早い施策推進のための具体的なスケジュールについて、村長の答弁を求めるものです。
議長(萩原達雄君) 村長、答弁願います。
〔村長 跡部昌洋君 登壇〕
村長(跡部昌洋君) 汚染牧草の一時保管についてのご質問でありますけれども、これは3月の第1回定例会の細川運一議員、そして赤間議員のそれぞれのご質問がございました。
まず、一時保管場所につきましては、1カ所に置いて保管するための必要な面積を確保できる村有地など数カ所について、担当課長が数カ所、まだしっかり決まった数カ所はございませんですね、どこまで担当課長が言ったかわかりませんけれども、しっかりした数カ所ではございません。それらを、だからいっぱいあります、村有地。その中でどこがいいかというのは、だから数カ所というのはそこだと思うんです、村有地いっぱいあるんですから。
そして、民間からの距離が離れていないのか、利用状況はどうなっているのか、周辺の土地の利用状況、トラックの搬入はどうなのかと、いろいろな問題がたくさん検討すべきものがございますので、最も適当な場所を選定し、まずもって地元の区長さんと相談しながら、そして決まれば住民説明会を行っていきたいというふうに思っております。
これについても、議員さん方にもどこかいいところがあったら紹介してくださいと言っているんですけれども、誰一人まだ1カ所も、赤間議員にも言っていたんですけれども、何回も、どこのここの場所あたりいいのではないですかという言葉すら出ていないものですから、だから、何だべ議員さん方も、こういう場所いいのではないかというご提言をしてくれればうんとよろしいのではないかなと思うんですが、私うんと期待して待っているんですけれども、いまだそういう話が来ていないものですから、私たちの事務方等でも、まず村有地を基本にやろうということで、ただやみくもにこの土地というと、これは大変な問題になってくるという、ある町の話も聞いているものですから、やはり決めたときは、そこで真っすぐに進まなければならないということがあるものですから、決めるまで私は時間が大変たくさんかかるのではないかなと思いますね。まして、赤間議員が何回も言いました、安全で安心な住民の不安を抱かないところといったら、そしたら今から何年かかるかわからないですよね。時期的には、今年度中に何とかやりたいなというふうには思っております。ですから、そういう安心で安全な、住民の不安の抱かない理解の得られるところというと、そうは私はないと思いますよ。だから、決まったときには、やっぱり議員さん方も一緒になってそれを推してもらわないと、ある反面で後ろのほうでは、あいつ反対するなんていう人はいないと思うんですけれども、いた場合のこと想定して話をしておりますけれどもね。だから、なかなか候補地のあれは難しいのではないかなと思います。だから、時間がかかるということは言えるのではないかなと思っております。以上です。
議長(萩原達雄君) 赤間しづ江君。
6番(赤間しづ江君) 村長、質問項目2番目、3番目に対しての、これはどうして答えていただかないんですか。大事な1問目ですよ。
議長(萩原達雄君) 村長、答弁するの、違うの。(村長の声あり)まとめてだよね、今。包含されていると私も感じました。赤間しづ江君。
6番(赤間しづ江君) 当初予算で430万円の予算措置をしたときに、なぜこの予算になったのか。そして、先例地を見ますとパイプハウス方式というところでやっているところもある、大衡村が遮蔽シート方式を選択したのはなぜなのか、というふうな質問をされたときに、村長は、できるだけ早く対策をしたいからだとおっしゃいました。これは26年度事業であります。もう既に6月に入っております。具体的な候補地を決めて進むという、その候補地を決めるということを一番先にしないでどうするのですか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 候補地を決めないとは一言も言っていません。その候補地を決めるために、いろいろ検討しているんだということですから。
議長(萩原達雄君) 赤間しづ江君。
6番(赤間しづ江君) その435万円の予算を敷いたときには、ある程度の候補地というものが頭の中にあったのではないですか。それを聞きたいと思います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 同じような質問を、前回の議会でも質問されたと思います。そのとき述べたとおりであります。
議長(萩原達雄君) 赤間しづ江君。
6番(赤間しづ江君) 同じ郡内で、1年も前にパイプハウス方式でやっているところもあるのです、大郷の場合なんですけれども。その情報収集等はどのようになさったのか伺います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 担当課長から答弁させます。
議長(萩原達雄君) 農林建設課長。
農林建設課長(齋藤 浩君) 隣接町のパイプハウスという形で一時保管を行っているところはございます。それにつきましては、そちらの担当課長のほうからそういった情報をお聞きしまして、場所等もお聞きしまして、あと実際そちらの場所を見に行っておりまして、その保管状況、あと設置の状況、周りの状況、そういったものについては確認してきたということでございます。
議長(萩原達雄君) 赤間しづ江君。
6番(赤間しづ江君) そういう状況を視察なり状況を聞いたりして、UVシート方式にそれを選択したというのには、先ほども申し上げましたように、一日も早く対応ができると、村長は3月の細川運一議員の質問に答えております。一日も早くという姿勢はどこにそのあれがあるんですか。考えられませんね。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) それは認識の違いではないですか。
議長(萩原達雄君) 赤間しづ江君。
6番(赤間しづ江君) 大郷のお話をさせていただきます。もう去年のうちにその対策をやっております。2回の住民説明をやったそうです、候補地を絞り込んでからですね。1回目、意見噴出だったそうです。そんなに安全だったら役場のそばに建てろと、今のその指定廃棄物ではないですけれども、そういうお声だった。もうこれでは収拾がつかないというふうなことで、それは住民の意見を聞くだけにして2回目に臨んだ。2回目は、いろいろな状況を丁寧に説明をして、理解をしてもらった。早く対策をしないとロールの劣化がひどくなる、これは目に見えているし、腐敗あるいはそのラッピングそのものの劣化による状況の変化が大変ひどくなっている。腐敗臭であったり、あるいはその小動物によるいたずら、そういったことも心配されたからだとおっしゃっていました。そして、危険なものをまき散らしているような状況ではということで、この2回の説明で大方の住民の合意を得られた。土地選定に当たっては、大松沢地区、ある程度土地をならす程度の作業だった。そして、いち早く取りかかった。線量の調査は、職員が定期的に行っていったと。しかし、汚染度、ベクレルも、あるいはその空間線量、シーベルトも下がってきており、現在では平常と変わらないところまできていると。そのために、定期調査から今は随時調査としていると。住民からの苦情等々はどうなのでしょうかというふうなお話をしましたら、ないと、非常に落ち着いてきている状況である。さらに、その方はこのようにもおっしゃっていました。この対策は、先延ばしすればするほど大変になると判断した。結果的に早目の対応でよかった。対応がおくれれば、今問題になっている指定廃棄物、いわゆるキログラム当たり8,000ベクレル以上のその指定廃棄物と混乱して、大変な状況になるところだったと、このようにお話をしておりました。このように、きちんと向き合って対応している隣の町があるわけですよ、村長。これ以上野放しにする状況を何とか早く解消してほしい、そういう意味で、また今回も一般質問するわけです。ですから、できればこの質問がいい形で保管場所発表という形になってほしかったと思うのですが、いかがですか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) ああ、そうですか。はい。
議長(萩原達雄君) 赤間しづ江君。
6番(赤間しづ江君) 職員の方々も、一生懸命情報収集をして取りかかっていらっしゃるんだと思います。もう3月の定例会でも同じようなことを質問され、質疑を受け、今回はさらにいい形で発表する絶好のチャンスだったのではありませんか、村長。もう一度姿勢を伺います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 先ほど第1回目の答弁したとおりでございます。(「休憩」の声あり)
議長(萩原達雄君) ここで、休憩いたします。再開を午後1時といたします。
午後0時03分 休憩
午後1時00分 再開
議長(萩原達雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続けます。赤間しづ江君。
6番(赤間しづ江君) あと40分もあるのかと。笑われましたが。村長の答弁が余りにも短過ぎて、元気もなく、何か私の耳に残らないあれなものですから、せめて村長、「はい」ではなく、対策に向けて努力しますとか、そのぐらいの言葉をぜひつけてほしいと思っております。
また、盛り返しになりますが、産業教育常任委員会の席で、課長は5カ所というふうなことを言って、あと数カ所と訂正をなさったんです。場所の決定は絞り込まれているというふうに考えていいんですか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) そういう質問するから、だからさっき言ったとおりですという、何か質問の仕方が悪いのではないですか。
議長(萩原達雄君) 赤間しづ江君。
6番(赤間しづ江君) 場所が決まらないことにはどうにもならないという問題ではあるんですが、まずこの事業は26年度で予算化した事業であると、400万円なにがし。再ラップというふうなことを申し上げられました、説明ありましたけれども、劣化は相当進んでいる状況というふうに聞きます。再ラップは難しく、袋状のものに入れ直しをしなければならないのではないかということも言われているようですが、その辺の認識はなされていますか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 担当課長から答弁させます。
議長(萩原達雄君) 農林建設課長。
農林建設課長(齋藤 浩君) 基本的には、傷みぐあいによって再ラッピングということでございますけれども、その状況がひどいものにつきましてはフレコンパック、1トンの大きな袋があるんですけれども、そちらに入れ込んでの保管ということも考えてございます。
議長(萩原達雄君) 赤間しづ江君。
6番(赤間しづ江君) 当初予算からさらに予算を見なければならないというふうな状況も起きているのかどうか伺います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 農林課長から答弁させます。
議長(萩原達雄君) 農林建設課長。
農林建設課長(齋藤 浩君) 当初予算につきましては、見積もりをいただきながら計上したものでございます。あと、これから実際のところの運搬とかそういったものが出てくれば、その際に再度積算し直しということも出てきます。また、先ほど言いましたように、再ラッピングあるいはフレコンパックというところについても出てきますので、その辺についてはこれから実際やる、発注する際に再度検討する項目というふうに思ってございます。
議長(萩原達雄君) 赤間しづ江君。
6番(赤間しづ江君) 原発事故から既に3年余り、3回目の長雨の季節に入ってまいります。私たちの心配するのは、それによってさらにまた困難であり、長引くことが予想される、ずれ込んでいくのではないかということが心配されるのですが、その辺をどのようにお考えですか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) ですから、一生懸命にこれからも取り組んでいくということですね。
議長(萩原達雄君) 赤間しづ江君。
6番(赤間しづ江君) 村長は、非常に企業誘致には精力的であります。しかし、一方で基幹産業である農業、これにも力を入れていないと言われないように、施政方針にでもきちんと述べていることでありますから、施政方針が場当たり的と言われないように、全て決断の早い村長、そういうふうなイメージで言われている方ですから、とにかく場所を早く決める、発表する、その村長の英断にかかっていると思います。最後に伺います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 一生懸命に取り組んでいるところでございます。
議長(萩原達雄君) 村長、マイクをもうちょっと自分のほうに。俺にさっぱり聞こえない、村長何をしゃべっているか全然聞こえないんだ。もう少し自分のほうに向けてしゃべってください。終わり、ああそう、はい。
次に、通告順3番、齋藤一郎君、登壇願います。
〔4番 齋藤一郎君 登壇〕
4番(齋藤一郎君) 通告順番3番の齋藤一郎です。一問一答方式で質問をいたします。
仙台北部中核テクノポリス圏域において、先端技術産業等の集積を図り、雇用機会の拡大を図るため、工業団地造成するという目的でありました。お隣、大和町に造成しました仙台北部中核工業団地、それと連携して本村にある第2仙台北部工業団地も造成、整備をされ、トヨタ自動車東日本を核とする関連企業の立地が相次ぎ、産業振興の中核的拠点を形成しているところであります。
その工業団地に企業立地が進んでまいりますと、当然そこで働く従業員の方々もふえて多くなってまいります。当然、通勤には自動車でございますので、時間帯によって、あるいは交代時間帯、交代制で企業もいろいろ操業しているわけでございますので、そのある一定の時間帯には、かなりの長蛇の自動車の列になっているのが現状であります。一例を挙げますと、衡下の地区内でございますが、夕方の帰宅時間帯になると、国道4号と県道大衡駒場線がタッチする古館下地内のガソリンスタンドからNTTの電話の交換所付近まで、自動車の長い列となっているのが現状であります。地区の人たちは、当然そういう状況を見ておりますので、買い物等へ吉岡方面にと考えている人の中には、最初からもう別のルートを利用している方もおります。
ことし春の1カ月以内に、県道大衡駒場線の衡下地区等で立て続けに3件の交通事故が発生しました。そういうことは、今までにはありませんでした。3件続けて事故があったというのは、それはたまたまそういう状況だったのかもしれませんが、そこで村長にお伺いしますが、古館下から第2工業団地に向かいます都市計画道路の重要性、まだ未整備区間ございますけれども、その都市計画道路の重要性をどのように認識しているものなのか、現在の心境をお伺いいたします。
次に、未整備区間があるために、奥田集落内の生活道路である村道を、通勤のため車が盛んに往来しております。周辺に住んでいる住民は、事故に遭わないように不安を抱えながら生活しております。そういった状況を考えた場合、未整備区間の整備の見通しや今後の整備促進策をどのように考えているのかお伺いするものであります。よろしくお願いいたします。
議長(萩原達雄君) 村長、答弁願います。
〔村長 跡部昌洋君 登壇〕
村長(跡部昌洋君) いろいろ体のことをご心配していただき、ありがとうございました。林野防御の際、風邪を引いたものですから、あそこからなかなか風邪が抜けなくて。寒くて、下は暑かったんですけれども上の人は寒くて、大変な防御の訓練のときだったんですけれども、あれからちょっと風邪がなかなか治らなくて、皆さん元気のないということで心配をかけて済みませんでした。そのうち元気になりますのでご安心いただきたいと思います。
まず、村として都市計画街路古館奥田線の重要性をどのように認識しているかという質問でありますが、そもそも昭和44年に宮城県と通産省が共同して行った仙台北部工業団地造成調査が契機となりまして、昭和49年に仙台北部中核都市構想、そのときは人口7万人、面積にすると2,000ヘクタールと発表されました。職住近接型の都市としての方向が定められ、その後昭和55年に仙台北部中核都市基本計画が策定をされて、昭和59年には我が国の技術先端化の流れを受けて、仙台北部中核都市新基本構想に見直され、昭和59年9月に工業団地造成工事に着手しているという経緯でございます。その後の経済情勢の変化や、セントラル自動車の工場移転計画などによりまして、住居地域が工業専用地域に用途変更されるなど、現在の形になってきたものでございます。
ご質問の路線につきましては、このような経緯の中で、奥田地区の開発に伴う都市計画街路古館奥田線として、平成3年に村で計画決定した道路でありますが、その後村道古館大森線の一部が県道大衡駒場線となりまして、村道から県道に格上げになって県道大衡駒場線となって、都市計画街路古館奥田線の整備について、今度は村から県のほうに所管することになったものでございます。村といたしましても、重要な路線であるという認識はしております。県道大衡駒場線は、国道4号線から竹ノ内地区の村道奥田工業団地西線、塩浪竹ノ内線の交差点までの区間及び村道奥田大森線との交差点から村道楳田戸口線との交差点の区間においては、両側に歩道が整備されておりますが、竹ノ内線交差点から奥田荒屋敷交差点までの区間については、片側の歩道となっております。また、沿線の住宅の状況により歩道が設置されているため、歩行者が道路を横断しなければならない構造となっております。第2仙台北部中核工業団地を含む仙台北部中核工業団地への通勤車両や物流トラックなどの通行が増加している状況であるのも認識しておりますし、歩行者の通行、特に小中学生への通学等に不安を感じていることについても、村でもある程度認識をしているところでございます。竹ノ内沢団地の子供たちが、交通量の多い県道を横断しなければならないため、竹ノ内交差点までの区間については歩道を設置してほしいと、衡下の中川区長さんから要望がありまして、県に対し、その歩行者の安全確保の観点から歩道設置について要望しております。県では、地域からの要望に対し、当該区間について歩道設置の計画を立て、本年度に工事を実施する予定になっております。この工事についても、大き目のあれではないですけれども、仮的なものといっても過言ではないと思いますけれども、そういうふうなまず用地を見ながら歩道を設置していくというふうなことでありますので、その内容につきましては、衡下の中川区長さんにもお伝えしております。この工事に当たっては、現在の県道の敷地内に組み立て式の歩道を設置する計画となっておりますが、先ほど言った組み立て式の歩道を設置する計画になっておりますが、施工の関係上、一部隣接地の使用が想定されるため、その地権者からの承諾をいただくことが必要であると思いますので、交渉の際には村も、幾ら県道でも村も協力して進めてまいりたいと、このように思っております。今後、県からの具体的な施工計画が示された段階で、地権者に説明し、承諾をいただいてから工事となる予定でありますので、歩道の設置により歩行者の安全が確保されるのではないかなと、そのように思っております。
次に、未整備区間の対応策、整備促進策についてのご質問でありますが、当該区間は、先ほども申し上げた経緯の路線でありますので、村におきましては、毎年度県道大衡駒場線の整備促進について県に要望しているところでありますが、当該路線は第2仙台北部中核工業団地に関連する重要な路線という位置づけもあります。ただ、齋藤議員も特に承知していると思いますが、この道路の予定地の一部が、まだ地権者の方々の筆界未定となっておりますので、そこが一番のネックだと思いますね、恐らく知っていると思いますけれども。ここがなかなか進行状況についていないということであります。こういうことも、齋藤議員も同じ地区の方が住民でありますので、ひとつその方にいろいろ説得していただきたいというふうに思っております、そうすれば早いのではないかなと思いますけれども。
なお、交通量が急増し、交通事故が多発しているとのことでありますが、村全体といたしましては、物損事故は増加傾向にありますが、死亡事故につきましては、平成22年12月20日に発生して以来、当初でも挨拶の中で言いましたけれども、1,231日の死亡事故ゼロということで褒賞を知事から受けておりますが、今後も厳しい交通死亡事故や交通事故が発生しないように、関係機関と皆様と協力して、交通事故が起きないように啓発をしていきたいと、このように思っております。以上です。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 県道、村道が、当時は古館下のガソリンスタンドのところから古館大森線という村道であったわけですけれども、県道昇格して大衡駒場線になったり、さらには古館大森線が荒屋敷地内からまた別の名称というふうになったりしたものですから、ちょっとこんがらがっているところがあるんですけれども、大衡駒場線のその歩道の関係は、お話は伺っておりますので、今村長が言われたように、ぜひその整備等についてはよろしくお願いしたいわけですけれども、今私が話しましたように、その都市計画街路を位置づけして線引きをしまして、それを将来工業団地に通勤する従業者のために、またほかの通勤者のために整備しますよというふうに街路決定をしているものですから、それは途中まで当然両方来ているんですけれども、その未整備区間ですね。確かに、村長がそれは筆界がまだ未定なものだから進まないと。しかし、私ども地区住民としては、平成19年の地区懇談会のときにも道路の整備については要望をしました。それは平成19年ですよ。その際も、村の答弁としては、企業立地を見ながら整備を進めていきますという答弁をしていますけれども、平成10年から数えて、もうどのくらいになりますか。村長が言われているように、自動車関連のいろいろな企業さんがもう張りついて、それこそ朝晩車の往来が、交代制でやっているものですから、私どもものほほんとして田んぼには行けない状態に今あります。ですから、あそこの道路も未整備区間の道路を早く何とか進めてほしいと。それで、私は重要だと思っているものですから、村長がその重要性、本当に重要な路線だと思っているのかどうか、また確認をいたします。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 思ってもおります。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 重要な路線だと思っていると。だとすれば、当然県などにも働きかけはされているんだろうと思うんですけれども、ではここ最近で結構ですから、具体的にどんな行動を起こされているんですか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 基本的には、地権者の了解をもらわなければ進みません、絶対に。なんぼ県にいったって、地権者の同意がなければだめですよと必ず言われますよ。じゃあ、地権者を無視して工事ができる方法があるんだったら教えていただきます。基本的に、地権者の了解がなければ、あの未整備区間は整備できないと思いますよ。だからこそ、大衡村でいち早くそれにかわる村道奥田工業団地西線、これをつくったんですよ。そうしたら、つくっている間にこちら側も何とか地権者の了解をいただいて、そしてあの未整備の区間を何とかしたいという思いでいるんですけれども、なかなか地権者の方々が同意してくれないと。そこがやっぱり一番ではないですかね、どうやっているんだなんて、あそこで逆立ちして同意してもらえるなら逆立ちしてもいいんですけれども、まず地権者の方々が一番だと思いますよ。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 村長は、逆立ちしてもと言いますけれども、じゃあ村長は、その地権者の方にもうお会いになって、何とかお願いしたいということを地権者の方とお会いしてお話をしたことがあるんですか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 以前は役場によく来られた方ですから、その際いろいろ話をしました。全然耳のふちにも……答弁で、だめだ、だめだの……ですからね。もしかすると、齋藤議員が行ったら承諾してくれるのではないかな。ぜひお願いします、協力。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) こっちも真面目になって質問しているんですが、そんな冗談はやめてくださいよ。私も地権者で、あの人といろいろトラブったことがありますから。ですから、村長もそれは地権者の方が役場に来られる方だと、私も職員時代それは何回かお会いしていますからわかっていますけれども、逆に、その重要な路線だと認識しているのであれば、役場に来たからというわけではなくて、逆にこっちから足を運ばなければならないのではないですか。やっぱり、今どんどん立地企業もふえてきている、それによって通勤の自動車もかなりふえている。なかなか厳しいので、それを村としても、この路線を何とか街路決定をして通したいと。村長言ったように、確かにそれは奥田工業団地、工業団地ってどこにあるのかわかりませんけれども、その西線を開通させて、それを今やっていますけれども、しかし村長もご存じのように、トヨタ東日本の通勤用の入り口もこっちの奥田のほうにもあるじゃないですか。どうしてもこっちを通らなければならないんですよ。すると住民が本当に大変なんです。ですから、そこの集落内、片側に歩道しかない集落内を通さないで、そのことをやっぱり村長も1回行ったからだって、必ずしもわかりましたということではないと思います。しかしながら、村長が足を運んで誠意を私は粘り強く見せることだと思うんですよ。確かに、それを行ったからだって、そうなるとは私はあの状態から見て考えられませんけれども、しかし村長が全然お宅に訪問もしないで、全然筆界未定でわからなんだと、それでは進まないではないですか。集落でも19年から何とかしてほしいと要望しているんですよ、どうですか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) あのね、今言ったよね、なかなか承諾しない人だよと。そういう人なんだから、ましてこれは県道ですから、県を差し置いて村がやるということないでしょう、県といろいろ話をして進むというのが常識ですから。だから、そういうふうに説得できる齋藤議員もあるんだったら、齋藤議員もそんなに心配しているなら行って説得してください、そして私のほうに言ってください。そして私は県のほうに、こういうんだよということ話しますから。議員だって一つのそういう心配しているんだから、そういう協力もあってよろしいんじゃないかと思いますけれどね。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 村長、そんな開き直りではなくて、それは県道どうのこうの、都市計画街路云々といった場合、やっぱり村が誠意を見せて交渉する。それは、今村長が言ったように、確かにそれはそのとおりいくかどうかわかりません。しかしながら、そういう誠意を見せながら、さらに県にも何とかそれも一緒にというふうな、そういう話の進め方に、これは県のものだから、県の事業だから、それでは進まないじゃないですか。私は、この道路を早くつくってもらいたいと、ここ一般質問に立つきっかけになったのは、私もこの春に育苗センターで働いていて、その働いている事務所にいたときにドカンと音がして、事故だと思って道路に出たら、乗用車が横転していたんですよ。人が出られなくて困っていて。それを走っていって、ちょうど車がいろいろ来たものですから、みんなで何とか起こして助け出した。そしたら、その前後にまた事故が立て続けに3件あったと、そういうことなんですよ。そんなことは、この地域では考えられなかった。だから、それを何とかしてほしい、万が一のことがあったらどうしますか。せっかく村長が企業誘致して、ああよかったと喜んでいますけれども、地域住民がそういう形に大きな事故に巻き込まれてしまったら大変なことですよ。ですから何とか、すぐには、期間がかかったものですからそんなに簡単にはいかないとは思いますけれども、村長が1回も足を運ばないで、用地が決まらないからだめだでは進まないじゃないですか。それは、村長が行政のトップですから、多分担当者は足を運んでいるんだろうと思いますけれども、その誠意を見せなければだめですよ。私はそうだと思うんですよ。私はそこをお願いしているんですよ。いかがですか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 先ほど言ったとおり、齋藤議員、じゃあ俺も行ってやるからという言葉が何で出てこないんですか。そんなにあれだったら俺も行ってやるからという言葉出たっておかしくないと思いますよ、私は。(議員の声あり)だって、開き直っているのではないですよ、それだけ難しい人なんだから、みんなでやっていかないと、この問題なんか解決しないと思いますよ。一番わかっているんですから、なかなか大変な人ということで村でも有名な方ですから。俺も行ってやるからという言葉あれば、私も県も喜ぶのではないですか。何か言っていること、村でやれ、俺はもう高みの見物だというような質問では話にならないと思います。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) あのね、村長、村長がまず誠意を見せることですよ。全然行きもしないで、一緒に行ってお願いしなければ云々と言いますけれども、村長1回も足も運ばないで、そんなことはないでしょう。そうでしょう、だってそういうふうにして物事は進めていかないと、担当者も、担当者行く、なかなか厳しい、では課長が行って、さらに歩み寄るための条件を持ちながらそれを進む、でもいかないときは、それはやっぱり行政のトップである村長が行かなければだめではないですか。村長が1回も足も運ばないで、なかなか境が決まらないんだ、それはおかしいという話、あげくの果てには、議員もでは一緒に行くと、それはおかしいと思いますよ。村長がまず自分で姿勢を見せなければだめではないですか。私はそう思うんですけれども、違いますか。いかがですか、私の考え。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 私は、ちょっと齋藤議員が言っているのは、齋藤議員もだからそれを言えばいいと思いますよ。何で齋藤議員はそれを、そうだな、俺もいってくれと何で言わないんですかと、特にあなたは親しい人なんだから、私はどちらかというと親しくない人ですから。あなたが隣接地で親しい人なんですよ、同じ地区民で。そんなに心配しているんだから、私も心配しているけれども、県でもあそこはある程度、当分あそこはできないということも言っておりますよ。それは、地区の方々もみんな言っているんですよ。ですから、進んでいないのはそこだと思いますよ。だから、かえって地区の方々みんなで行って、何とかあそこやってくれやと言えば、かえって私なんか行くよりも、県が行くよりもずっと進むと思いますよ。そういうものも一つの促進の一つではないですかと言っているんですよ。それを、何か俺は行きたくなくて、村長が行けと、そういうふうにしか聞こえておりませんよ。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 何ですか、村長、私が親しい間柄のような。私なんか話したことないですよ。そういう面で、では村長がまず足を運ぶと、そういう予定というか計画がありますか。
議長(萩原達雄君) 村長、計画ありますか。
村長(跡部昌洋君) ありません。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) やはり、そういうことだから、地区住民としての行政懇談会の際に、19年にお願いをしたと、第2工業団地なりそれを整備するということは、企業をどのぐらい張りつけて、張りつければどのぐらいの従業員数になる、そのためにはインフラ整備としてどういうふうな整備をしたらいいのかと、そういうことでいろいろ決定をしてくるわけです。今言ったように、村はその都市計画街路が難しいので、奥田工業団地西線をとりあえず整備をしたと、それはわかります。でも、本来はそこでないでしょう。都市計画決定した路線を整備しますよと、私そこだと思うんです。いや、私もお願いして行ったんだけれども、なかなか厳しくて、今こういう状況ですというなら私はしようがないし、地域としてもそれは今後のことについて考えていかなければならないと思うんですけれども、村長が全然足も運ばない、今から行く気もない、そんなことではどうするんですか。村長はそれで重要だと言っている、重要性を認識していると言ったんじゃないですか。ですから、私はやはり村長が足を運んで、さらにその状況を県なりに伝えて、あのスタンドから工業団地に向かう真っ直ぐな縦軸を早急に整備してもらわないと、万が一の住民に大事故なりが発生したら大変なことでしょう。企業誘致によって住民が犠牲になっていいんですか。そういうことではないでしょう。ぜひ、地権者の方にそれはいろいろ言われるかもしれません。そんなことはしようがないではないですか。村長が足も運ばないで、担当者だけやったってどうしようもないではないですか。まず1回行ってみてくださいよ。もう一度確認して、私は質問をやめたいと思います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 衡下地区関係の道路関係は、齋藤議員も職員時代にあそこに都市計画道路をつくった件についても今でも言われております。あれ何年前のこと、それの整備もしなければならない、でもなかなか難しいと思いますけれども。その前に、やっぱり地権者の同意というのは大事ですから、これは県の事業ですから、今回西道路、西線もつくったものですから、慌てないであの道路の整備を図っていくべきだと、こういうふうに思っております。
議長(萩原達雄君) いいですか。
次に、通告順4番、佐藤 貢君、登壇願います。
〔3番 佐藤 貢君 登壇〕
3番(佐藤 貢君) 通告順4番、佐藤 貢です。私は、国道4号(4車線化)の調査の進捗状況について、一括で質問いたします。
国道4号線大衡枛木地区から蕨崎地区の約4.5キロメートルの区間は、まだ2車線道路であり、拡幅整備の早期着工が待たれる路線であります。宅地化が進み、企業の工場立地の増加に伴い、朝夕のみならず日中でも交通渋滞が目立ち、県内においても混雑度の最も高い区間とされており、地域住民や企業からも4車線化の早期着工を望む声が高まっています。
こういった中で、新聞等によると、東北地方整備局において有識者による委員会を立ち上げ、4車線化と迂回路の検討、また地域住民や企業立地へのアンケートも実施していくと、そのように報道されています。新規事業採択の前段となる計画段階評価に向けた調査をしていると伺っておりますが、今はどのような段階なのか、新たな情報があるのかお伺いします。
また、4市町村を初め沿線自治体を加えた国道4号拡幅改良建設促進期成同盟会並びに役場庁内で立ち上げているプロジェクトチームは、早期事業採択の実現に向け、国への要望活動を積極的に実施してきましたが、これからも引き続き活動を行っていくのか、今後の道路調査の見通しについてお伺いします。
議長(萩原達雄君) 村長、答弁願います。
〔村長 跡部昌洋君 登壇〕
村長(跡部昌洋君) お答えをいたします。
国道4号線の関係でありますけれども、現在2車線道路となっている国道4号の一本木交差点から大崎市三本木までの約5キロの区間の4車線化に向けた調査の進捗状況についてのご質問でありますけれども、国道4号の拡幅整備につきましては、第5次大衡村総合計画大衡村国道利用計画及び大衡村都市計画マスタープランにおいて、大衡村が今後発展していくために必要な不可欠な交通インフラとして重要な施策を位置づけられているところであります。本年度の施政方針におきましても、4車線化の早期事業採択への取り組みを重点項目として推進しているところでございます。
また、平成24年度までは、大崎市長を会長とする富谷町、大和町及び大衡村の各首長と各議会議長で構成する国道4号拡幅改良建設促進期成同盟会において、大衡地区の4車線化の新規事業採択に向けての要望活動を実施してまいりましたが、宮城県内のそれぞれの地域においても、事業採択に向けた要望を別々に行うよりも、国の道路予算の確保が大変今厳しい状況になってきておりますし、ましてこの国道4号線は、震災関係の予算は余り該当ができないことから、一般の予算でこの事業を進めていかなければならないという、いろいろなこの予算関係も厳しい状況でありますので、宮城県内で関係する市町村が一体となった事業の採択に向けた要望をする方法が、より今までの国道4号線拡幅改良建設促進期成同盟会よりもさらにこの要望をするには効果的だろうということで、昨年の10月に国道4号に関係する県内13の自治体の首長と、未改良区間を持つ5市町村の議会議長、さらには国道4号の整備を望む企業6社を賛助会員として同盟会に入ってもらって、そして昨年の11月に地元選出国会議員と国土交通省に対し、強力に要望活動を推進してまいりました。このような要望活動では、非常にまれなことでありますけれども、まれというか初めてだというような話を聞いておりますが、賛助会員でありますトヨタ自動車東日本、YKK AP、大和ハウス工業、アルプス電気株式会社、4社の方々にもこの賛助会員になっていただいて、そして4社の方々と一緒に要望活動に参加をしていただき、各社からそれぞれ直接国土交通省の方々に、今のこの道路の必要性、こういうものを訴えていただきました。
これまでの要望活動の継続と、昨年度に実施した非常にインパクトのある要望活動の成果もあり、国道4号の大衡地区の整備の必要性が国に認められました。計画段階評価を進めるための調査として、概略ルート、構造の検討、平成26年度に進めることが、平成26年3月28日に東北整備局から発表されました。なお、平成26年度に東北地方で新規に位置づけられた路線は4路線です。その4路線のうち3路線は高規格道路であります。そして、大衡村の一般国道は、東北で一つだけ認めていただいたと、そのことによって、新しく予算をつけてもらったと。これも、長いいろいろな活動の中で私たちも粘り強くやってきた、その成果が今回あらわれてきたと。ただし、これからまだ何段階もいくものですから、全部で6段階だったかな、課長。だからそのうちのあと残り3段階か。6段階ぐらいあって、そして予算をつけてもらったんですから、あと4つの段階を踏んで、そして事業に着手するとなるものですから、ホップ、ステップ、ジャンプですね、そのホップに今回予算が計上していただいたということでございます。東北では、大衡村のこの4号線が一つだけ認めてもらったということで、私も大変関係機関に感謝を申し上げたいと思います。
計画段階評価に向けた調査の進捗状況につきましては、既に昨年11月から国土交通省東北地方整備局仙台河川国土事務所、宮城県大崎市及び大衡村による検討会を立ち上げ、大衡地区の新規事業採択に向けての課題整備や資料の収集、沿線住民の意向調査や自動車産業関連初め、先ほど言ったいろいろな企業さんの、周辺の企業さんなどのヒアリングを実施し、その分析を行っているところでございます。ですから、ここまで行くにも大変だったのだけれども、やっとここまでこぎつけたということで、本年4月からは仙台河川国土事務所において、正式に新規事業採択に向けての前段となる計画段階評価に向けた調査として、当地区の交通状況や道路網の課題などを調査し、地域の道路網の中での必要性、整備効果の整理などを進めている段階にあり、村に対しましても、黒川消防署大衡出張所に配置されている救急車の救急搬送先、こういうものもさらに説得力が出てくるということですから、余り救急車は出動してほしくないんですけれども、たまたまある面を考えれば、この救急車の出動回数も、大衡村地域あるいは隣町から大崎市に救急車が行く回数がこのくらい多いんですよと、あるいは大崎市からこちらのほうに来る場面もあると思いますね。そういうものも訴えていかなければならないのではないか。ただ道路が交通量が多いからといって、道路を整備してくださいと、今そういう時代ではないんですよ。そういう時代はもう終わったんです。先ほど齋藤議員の話にもちょっと関連しますけれども、そういう時代は終わったんですね。国に行くと、そんなことは承知していますと言われます。いかに地域住民なり、そしてこの交通量の確保、そして今言った救急車の関係、あるいは消防車の関係、こういうものをこれから段階的に調査をしていかなければ、次のホップ、ステップのほうに行かないと思いますね。でも、その前段が認めてもらった関係上、今後は社会資本整備審議会道路分科会東北小委員会の開催があるんです。そして、大衡村内だけでなく広い地域からの意見を聴取するような予定になっております。4車線化の実現に向けて、さらに一歩前進したのではないかなと思いますけれども、その前進がさらに前進するように期待をするものであります。
なお、渋滞が著しい国道4号河原交差点につきましては、早期に解消を図る必要があるということで、あの河原交差点、平成26年度に交差点の改良が計画されておりまして、既に4月24日に入札が告示され、6月12日に入札がされる予定になっておりまして、その入札の結果によって、あの道路の工事が始まっていくということで、局部でありますけれども、あの交差点も渋滞になっている場所ですから、その緩和も図られるのではないかなというふうに思っております。
なお、この4号線関係は、私とよく萩原議長も一緒に同行していただいて、そして国のほうに要望活動をしてまいりました。萩原議長とも話しておりました。やっと少し明かりが見えてきたねなんて言って、その会議の中であちらさんから出てくる答えが、大変このごろいい答えが出てくるものですから、さらにそのいい答えをストップすることなく、それをもっと伸ばしていきたいということで、国土交通省初め宮城県の国会議員、あるいは東北の国会議員のお力を借りて進めてまいりたいと、こういうふうに思っておりますので、まずもって明かりが今までと違って見えてきたということも言えるのではないかなと、そのように思っております。
議長(萩原達雄君) 佐藤 貢君。
3番(佐藤 貢君) 実現に向けたこれまでの要望活動が、このように要望活動に努力された結果が、このように国の一歩前進した対応だというふうに理解していますけれども、先ほど地域住民の要望等の話もありましたけれども、これも今まで地域住民の要望、意見、そういったものも反映されてきたものなのか、今からそういったものを詳細にやっていくのか、その辺ちょっとお伺いします。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 今までの地域住民からの要望、あと村の要望、あるいは県の要望、それを一つにして国のほうに訴えてきているんですね。ただ、今まではやっぱり国も重要性は認識しているんですけれども、ただ国自体が、一般道路の整備に係る予算がどんどんここ10年減ってきているんですよ。減ってきている中ですから、なおさら事業の予算が見えてこなかったんですね。でも、今もふえているわけではありませんけれども、そういう企業さんの声、あと私たちも長年言っていた方々の声、あるいは国会議員の皆さん方の声、あと村井知事さんの声、そういうものを国のほうでは吸い取っていただいたということで、よく国のほうに行って言われます、「東北で大衡だけですよ、一般国道で予算認められたのは、あと認めてもらっておりませんよ」と。そう言われると、私たちあの暑い中、国土交通省の会館に行ったり、あるいは国会議員の会館に行った、その成果が今回出てきたなというものですから、これからもそういう住民等の調査も、あるいはその周辺の企業さん等の声もさらに吸い上げて、いろいろなアンケート等もあるようでありますので、それらをもっといいアンケートが出てくれば、国のほうでもさらに見ていただくことができるのではないかなというふうに思っております。
議長(萩原達雄君) 佐藤 貢君。
3番(佐藤 貢君) 最後になりますけれども、これからも引き続き要望活動を行っていただきたいというふうに思います。それから、これからといいますかしばらく先の話になると思いますけれども、この4車線化が実現された後の、この沿線の土地利用、そういった考えを今持っているのか、もし計画があるのであればどのような方針なのか、その辺をお伺いして質問を終わりたいと思います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) この路線について、まずルートが決まらないものですから、村の都市計画のは、ちょっとなかなか引けないと思いますね。むやみに引いてしまったら、それこそ促進の妨げにもなるものですから、実はそういうこともないわけではないんですよ。例えば、大衡の4号線の関係ですね、その役場周辺の関係、今あちら側に中心市街地をつくろうということも言っております。でも、国の用地も一部道路の4車線化したことによって、国の道路の用地も入っている、実はですね、あれも一つのこれからの大きな課題になってくると思いますね。ですから、まずもって用地を、しっかり路線を決めてもらって、その後に、では村がその周辺をどうしていくかという計画もつくっていかなければならないのではないかなと思いますので、そちらのほうを見据えていくことによって、やっぱり道路の関係が一番だと思いますので、そういうことも一つのこれからの課題とし、そしてその後の仕事として、そういう周辺の土地利用計画、こういうものも立てていかなければならないのではないかなと、このように思っております。
議長(萩原達雄君) ここで、休憩いたします。再開を2時15分といたします。
午後1時56分 休憩
午後2時15分 再開
議長(萩原達雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続けます。
次に、通告順5番、小川ひろみ君、登壇願います。
〔1番 小川ひろみ君 登壇〕
1番(小川ひろみ君) 通告ナンバー5番、「教育行政について問う」と題し、一問一答でご質問いたします。
少子高齢化、グローバル化など、全国的に課題となる状況が直面しております。少子高齢化は、現役世代で1人のお年寄りを支えた胴上げ型、ピラミッド社会から、1人で1人を支える肩車型社会へと突き進んでいます。文科省は、教育改革、土曜日の授業の復活、グローバル化に伴う英語教育などを打ち出しております。次世代の子供たちの負担は、10年、20年、30年と年月が進むにつれさまざまな分野において負担増になることは目に見えています。その中で、若者の流出を防ぐ施策も考えていく必要があるのではないでしょうか。そして、今後の教育行政の取り組みは、地域の実情や実態を踏まえた施策が大事になると思われます。村長施政方針、教育行政は生きる力を育むために、学校だけでなく家庭や地域社会全体での協働が大切で、それぞれ連携を図りながら推進していくという理念であります。魅力ある大衡のまちづくりの施策として、今後この理念の生きる力を育むもとで、大衡における学校教育、生涯教育の方向性をどのように考えるのかお尋ねいたします。
(1)学校教育・生涯学習に対する試みは。
(2)大衡における一貫教育をどのように考えるのか。
(3)民設民営のおおひら万葉こども園と小学校との連携をどのように考えるのか。
(4)高校生、大学生の活用をどのように考えるのか。
(5)地域間・世代間の交流、企業との連携をどのように考えるのか。
以上5つのことについてお尋ねいたします。
議長(萩原達雄君) 村長、答弁願います。
村長(跡部昌洋君) 教育長から答弁をさせます。
議長(萩原達雄君) 教育長、登壇願います。
〔教育長 庄子明宏君 登壇〕
教育長(庄子明宏君) それでは、今後の大衡村における学校教育、そして生涯教育における方向性をどう考えるのかという質問についてお答えしたいと思います。
本村の教育行政につきましては、自立、協働、創造モデルとしての生涯教育社会の構築、これを目指し、3月の村長施政方針要旨にもあるように、第5次大衡村総合計画において「みんなで学び、みんなで育む、生涯学べるまちづくり」を実現するため、基本計画及び毎年度の定める教育基本法に基づく学校教育の目標並びに生涯にわたる学習、文化、スポーツ活動の推進等のため、事業計画を立案して現在取り組んでいるところです。
さて、ただいまいただきました5つのご質問につきまして、ご質問の内容がゼロ歳から高齢者までという長いスパンにかかわることですので、第2問と第3問、学校教育上の課題と捉え、1問と4問と5問の生涯教育にかかわることについての、大きく2つに分けてお答えしたいと考えます。
初めに、学校教育上の課題について申し上げます。
大衡村における一貫教育をどのように考えるのかというご質問ですけれども、一貫教育の形態については2つに分けることができます。1つは、この4月に開校した隣接の色麻学園では、中学校の敷地内に小学校を新設し、渡り廊下等で接続するという、学校自体も一体化している施設一体型の一貫校ということになります。もう1つは、一貫教育の理念を引き継ぎながらも、小学校が別の場所にあるという施設分離型の一貫校もあります。いずれにいたしましても、可能な限り小中合同で行事を立案したり、学校目標を立案したり、小学1年生から中学校3年生までの9年間を見越したカリキュラムをつくることで、英語や数学、理科など小学校の乗り入れの授業を展開し、中1ギャップの解消を図ったり、小中学校が連携して一貫した考えのもとで教育活動を行う、または運営しているところです。施設分離型の多くは、小学校が合併し、小学校が1小になり、中学校1校という形態をつくり、学校経営をしております。
本村は、小学校、中学校が各1校であり、また各学年60名前後の少人数の児童生徒の学校です。小学校を卒業したら、そのまま中学校へ進むという児童が大半数であり、同じ仲間と9年間学ぶという環境にあります。このような中、本村では児童生徒を指導する先生方は、小中学校の教職員で構成する小中研究協議会を定期的に開催したり、相互に情報を交換あるいは共有し、さらに全職員がお互いに授業を参観しながら学習状況の把握を行い、強い連携をとりながら学習指導を実践しており、まさに一貫教育とそれほど変わらない形態で進められています。今後、一貫教育を既に実践している町村の実態を把握し、9年間を見越したカリキュラムを構築し、本村の現状において一貫性のある教育を検討していきたいと考えております。
次の、民設民営のおおひら万葉こども園と小学校との連携につきましてお答えいたします。
おおひら万葉こども園幼稚園部が開設されてから2年経過し、平成26年度の新入生で2期目となります。新入生の大部分がおおひら万葉こども園の卒園児であり、万葉こども園から小学校へのスムーズな引き継ぎが必要であり、おおひら万葉こども園と小学校の緊密な連携を図ることが大変重要であると考えております。特に、民営の万葉こども園は、独自の教育方針を持つことができるということからも、なおさら大切なところであると考えております。
小学校では、先生方が万葉こども園に出向き、園児の様子を見学する機会を設定し、入学する児童の状況を確認しております。また、卒園時の引き継ぎの際には、万葉こども園の担任の先生と小学校の担任の先生が直接情報交換を行い、現状の把握に努めながら連携を図っていると認識しております。今後、さらなる連携が図れるよう、教育委員会としても後押ししていきたいと考えております。
大きな2つ目になりますが、生涯教育に対する試みについてです。
生涯教育につきましては、大変間口の広い分野であり、生涯学習の推進、社会教育推進体制の充実、家庭教育を初めとする学習事業の充実、公民館・分館活動などの地域活動の充実、生涯スポーツの振興や魅力ある地域文化の醸成を目標に掲げ、継続的に事業を進めているところです。これらの事業が、村民一人一人希望を抱き、健康で豊かな生活を営むことができる村づくりにつながるよう努力しております。
しかし、高校生、大学生を含めた地域間・世代間交流、企業との連携につきましては、「みんなで学び、みんなで育む、生涯学べるまちづくり」という意味合いから、大変重要な課題でもあり、今後村民の皆様のご意見なども頂戴しながら検討する価値のある課題でもあります。高校生や大学生が住みなれた大衡村に愛着を持って、将来大衡村に貢献するための動機づけとして、夏休みなどの期間を利用し、イベントや各種事業にボランティアとして協力してもらえるように、さまざまな機会を捉え、大衡村の情報を発信する必要があるとも考えております。
また、地域間・世代間の交流及び企業の連携については、本村にある大衡城青年交流館や万葉クリエートパークなどの交流施設を最大限に活用し、スポーツやイベントなどの開催を通して、村内外の人々の交流の機会が図れるものと考えております。
また、本村にはトヨタ自動車東日本株式会社を初め、多くの企業が立地しております。それぞれの企業では、村に対して多くの社会的貢献をいただいております。これらの企業では、さまざまな情報や人材を保有しており、これを村の事業に活用するためには企業からの協力が欠かせません。教育委員会といたしましては、現在学校教育や生涯教育の事業の中に、企業や事業者や近隣の大学など協力をいただきながら事業を実施していきたいと考え、引き続き連携強化を図ってまいりたいと思っております。
以上で答弁を終わります。
議長(萩原達雄君) 小川ひろみ君。
1番(小川ひろみ君) 新教育長となって2カ月、夢膨らむ答弁をいただきました。教育行政は、将来を担う子供たち一人一人を尊重し、育てることが重要になってくると考えます。学校の勉強だけでなく、生涯学習による自然体験や生活体験、社会体験が非常に大事になる、そして役割を持つと思われます。先ほど教育長が言われたように、一貫教育についてですが、文科省は学制改革として小中一貫制度を自治体の権限を持たせることを検討しているところのようです。このことにより、地域の事情に合わせたカリキュラムの編成は不可欠になるものと思われます。そこで、大衡村においては、現在義務教育1村1校であり、9年間のどこにも行かない同じ教育を受ける、転校とかそういうことのない一貫した教育と同じようなことになっているという答弁も今いただきました。その中で、現在の6・3制から4・3・2制や5・4制になることや、5年生からの英語教育を正式に導入することを検討していることから、この小中連携により教科担任の問題も効率的に配置できるのではないかと思われますが、教育長はどのようにお考えでしょうか。
議長(萩原達雄君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) 今小川議員さんが申し上げられましたように、昨日の毎日新聞、それからけさの河北新報のほうにも、そのことについては書かれておりました。小中一貫教育を制度化し、その大綱は首長が総合教育会議を招集し運営していくということのようです。今お話ありましたように、今まで6・3制という制度をとってまいりましたけれども、1974年あたりから、今現在2014年までの間の子供たちの成長率が、2年間ぐらい心身ともに高くなっているということを踏まえますと、6・3制ではなく4・3・2制とか、あるいは今ありました5・4制とか、さまざまな形態をこの地域に合わせたものを見つけながら取り組んでいかなければならないなというふうに考えております。
また、一貫教育のメリットということを考えていきますと、一つは不登校がふえる1年生の壁が現在課題となっております。また、6・3制の区切りの弾力化をそこから求めることによって、ある程度解消されるだろうというふうに思われます。また、文科省では、小学校英語を5年生から正式に教科にすることを検討しており、小中一貫教育によって系統性や連続性、あるいは英語教育が可能になるということは紛れもない事実だと思っております。また、一貫教育をとることによって教科担任制も導入しやすくなるということから、効率的なのかなというふうに考えております。少子高齢化に伴い、学級数や児童生徒数の減少に直面する小中学校の統合も進めることができるだろうと期待されております。
ただ、一方、1小1中ということで9年間同じ子供同士の人間関係が構築されるということも、ある意味では課題ともなっております。今国会で成立する見通しの教育委員会制度改革法案と、それから学校の統廃合については、市長と教育委員会で構成する総合教育会議で協議するとしております。小中一貫校が制度化されれば、新設は同会議での協議対象になることには間違いないと思います。しかしながら、今現在の大衡村の1小1中の状況を考えますと、必ずしもその導入に対応していく必要も今のところはないようにも思え、かつそれ以上に、現在の6・3制の中で小中の連絡を密にとり合いながら、一貫して9年間のカリキュラムをつくって対応していくべきかなというふうに考えております。
議長(萩原達雄君) 小川ひろみ君。
1番(小川ひろみ君) 今教育長が言われたように、大衡村は1村1校であり、9年間同じ人とともに学ぶわけで、そのことによりマイナスな部分も考えることは確かなことだと思います。そのマイナスの部分の一つとして、いじめ問題も出てくるかと思います。また、不登校の児童の対策も、またこれは課題になると考えます。現在、大衡村における不登校、いじめなどの問題点はあるのか、ないのか、お聞きいたします。
議長(萩原達雄君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) 小中一貫とか、あるいは中高一貫とかという教育は、それのみの箱物であってはいけないというふうに考えております。5つの要点を考えながら、まず頑張る子供がそこにいるというのが一番大切なところだと思います。そして、2つ目に熱意のある教員がいて学校を理解してくれる。そして、3つ目が学校を理解してくれる保護者がいる。4つ目は、学校が計画する行事等に地域の人たちも親身になって入り、取り組んでくれるもの。5つ目が、いろいろな条件整備が必要になってくると思うんですけれども、その中にあって教育委員会が主体的に動かなければならないというふうに考えております。
現在、小中学校において、まず不登校生徒については何人かいることは間違いありません。いじめについては、現在のところ小中学校からの報告は来ておりません。今現在、確実だというふうな問題ではないと思います。いつそういう問題が起きるかというのは、進めてみる中で突然に出ることも考えられます。ですから、早急な対応、防止策等を常日ごろから構築して、万が一起きた場合には即対応するということが大変必要かなというふうに感じております。少なくとも、滋賀県の自殺事件がありましたけれども、あのような事件が起きないようにするために、今現在いじめ防止対策の基本方針を小中学校とも出して、検討しているところであります。以上です。
議長(萩原達雄君) 小川ひろみ君。
1番(小川ひろみ君) 教育長の答弁において、すごくわかりやすく、また頑張る子供、熱意のある教員、理解する保護者、行事に地域の住民が入る、とてもこの課題は大きな課題でもあるし、また私たちが努力すればこれはかなうものではないかと思いますので、この大衡の教育行政がますます夢を持って膨らんでいく教育行政になることを願うものであります。
また、次の質問の、民設民営のおおひら万葉こども園と小学校の連携についてですが、やはりこちらは十分な意見交換をすることにより、将来の宝物、財産となる子供たちへの、そのときどきの年代に合った取り組みが、そして個性を大切にすることが大事であると思われます。そのことについて、教育長の考えをお聞きいたします。
議長(萩原達雄君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) この件につきましては、先ほど述べたとおりではございますけれども、今小川議員がおっしゃいましたように、やはりゼロ歳から5歳までという、生まれてから活動できるまでという極端な成長の中で、子供たちが一つのこども園という中に入るわけですから、やはりここは万葉こども園のほうには、子供たちの個性や特徴をしっかり見きわめた活動をしていってもらわなければならないなというふうに考えております。
平成27年度から現実的に指導する子ども・子育て支援制度では、学校かつ児童福祉施設である単一の施設となる認定こども園の教育保育内容を定めた要領が4月30日に告示されました。その策定に当たっての基本的な考えは、一つは幼稚園教育要領と保育所保育方針との整合性をまず確保しなさいということが言われております。それから、2つ目に、小学校における教育についての円滑な接続につなげられるような配慮をしてください。3つ目、入園時期や在園時間の違いなども必ず出てまいります。その場合の子供たちの生活の連続性や、生活のリズムの多様性に対応した養育や教育をしていかなければならないということも問題になってくるかと思います。それから、4つ目なんですけれども、今のことにつきましては、5領域と目標というところがありまして、一つは健康、一つは人間関係、一つは環境、それから言葉、表現、それぞれ子供たちの年齢によって違うということが確認されておりますので、そこをやはり研修しながら進んでいかなければならないものと考えております。
議長(萩原達雄君) 小川ひろみ君。
1番(小川ひろみ君) こども園に行って、ゼロ歳から5歳まで、三つ子の魂百までもと昔のことわざにもあるように、とても人生においての影響力がすごくある時期だと考えます。生まれた環境も違うし、顔形も皆違うように、思いも個性も皆違うわけです。そんな中での、やはりこども園と小学校の連携はとても大切なことになると思いますので、これまで以上のその連携に対する取り組みをしていただきたいと思っております。
また、次の質問の、若者、高校生、大学生の活用をどのように考えるかという質問でございますが、教育長の言われたように、交流イベントや文化的行事への企画や、そういうものに若者の力を含めたプロジェクトの形成、それが活力ある地域社会になるのではないかと考えます。10年、20年後にもっと元気な地域になり、時代やニーズの変化に柔軟に対応した魅力ある村づくりの発信になるのではないかとも考えます。そのためにも、役場にある企画商工課との連携をすることも大切だと思いますが、その辺についてお聞きいたします。
議長(萩原達雄君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) 中学校、高校生だけではなく、やっぱり地域に眠る宝物というものはたくさんあると思います。その辺から魅力ある大衡村づくりをしていく必要があるなと考えます。特に、地域やPTAを主体にした土曜日などの時間帯での講座とか、高校生や大学生にお願いして塾ならぬ寺子屋をしてもらったり、あるいは子育て支援サポーター活用によるさまざまな活動の運営をしたり、中高生、大学生も含めて社会貢献活動の充実というのも大変重要なところだと考えております。それ以上に、大衡村という自然環境に恵まれたもの自体が、実は財産ではないかというところも考えております。これから、今小川議員さんの申しましたようなことを考えながら、情報収集等をしっかりして進めてまいりたいなというふうに思います。
議長(萩原達雄君) 小川ひろみ君。
1番(小川ひろみ君) やっぱり、交流イベントや文化的行事にもどんどん若者の力を含めたプロジェクトをつくって、今後柔軟な取り組みをしていっていただきたいと思います。
また、最後の質問にあります地域間・世代間の交流は、互いの立場を理解し、素直に受け入れ、助け合っていくことが一体となったまちづくりになっていくのではないかと思われます。そして、企業との連携は、企業のノウハウを最大限に活用することで、さらなる村の成長が期待できるようになるのではないかとも考えます。そして、そのことによって感謝の心を分かち合って、企業との連携がすばらしいものになっていくのではないかと考えますが、教育長の考えをお伺いいたします。
議長(萩原達雄君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) 3年前の東日本大震災、これは全国的にといいますか、かなり日本を痛めつけた震災ということで、誰しもが頭の中に、あるいは映像として残っていると思います。そして、地震に伴う大津波が押し寄せ、甚大な被害を及ぼしました。そんな中で、被害を受け避難生活を余儀なくされる中、多くの人たちが地域に住む人たちですが、お互いに助け合い、そして協力し合って、生きることを切実に感じたことと私は思っております。ということからしましても、それを象徴するような「絆」という言葉が選ばれましたけれども、子供だけでなく大人も含めて、国民すべての人々が社会力を高めるような必要があるのかなというふうに考えています。こういう気づきを後世にしっかりと伝えることが、ひょっとすると世代間、それから企業間であり地域間の交流にもつながっていくのではないだろうかなと思うところです。具体的には、これからこれをどう継続させていくかについては、さまざまな事例を検討しながら考えていかなければならないとは思いますけれども、まさしく小さい子供から大人までそういった交流をしていくことは、現在の社会の中では、大衡村だけではなく必要なことかなというふうに思っております。
議長(萩原達雄君) 小川ひろみ君。
1番(小川ひろみ君) 地域間・世代間、企業との連携は、生き方、暮らし方の再検討を自分自身で考え、導いていくことになるのではないかとも考えます。そんな中で、これからは高齢者、障害者に優しく、若者に魅力ある地域拠点都市の整備ではないかと考えます。そのためにも、対話や交流、雑談による情報交換が必要であると思いますが、高齢者、障害のある方、次世代を担う子供一人一人を尊重し、時代のニーズに合った地域の実情、実態に合った教育行政が求められると思いますが、その点についてお伺いいたします。
議長(萩原達雄君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) これも重なることでありますので、今おっしゃられたことを考慮しながら進めてまいりたいなというふうに思います。
議長(萩原達雄君) 小川ひろみ君。
1番(小川ひろみ君) 最後に、村長に伺います。これから、今教育長にも聞きましたように、高齢者、障害者に優しく、若者に魅力ある地域拠点の都市の整備ではないかと思っております。そのためにも、対話や交流、雑談による情報交換が必要と思われますが、村長はどのようにお考えでしょうか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) まちづくりの基本的なものは、その住民との会話、必ずしも若い者に限ったわけではないと思いますよね。そういう若い者に限ってどうのこうのという議論は、私は余りしたくないんですよね。住民との会話の中で若い人もいる、お年寄りの方もいるんです。私は、そういう考えで会話というのはすべきではないかなと思いますので、教育長も初めての答弁で、緊張しながらいろいろ答弁したと思いますけれども、基本的にやっぱり地域づくり、まちづくりというのは、それぞれの住民との対話から成り立って、そこからいいものが生まれてくるのではないかなと思います。私たちも、今までも大分議員さんからどうのこうの言われてますけども、会話、対話というのは必ずしもそこの会議を開いて会話じゃないですかね。いろいろな場面で、今言ったように雑談の中でも会話の一つだと思います。そういうものをやっぱりこれからもやっていくのも大事なことではないかなと、このように思っておりますけれども。
議長(萩原達雄君) 小川ひろみ君。
1番(小川ひろみ君) 今最後に村長にお聞きしたのも、私は若者ということではなく、高齢者、障害者にも優しく、若者にも魅力あるということでお尋ねしていましたので、若者、若者と言ったわけではなく、そういうことも私も考えていることを、また一つつけ加えさせていただきたいと思います。今後、教育行政というのはゼロ歳から自分の生命が終わるまでの長い期間における人生のプログラムというか、そういう中だと思いますので、今後とも大衡に住んでよかった、大衡に魅力を持てるそんな都市づくりに、今後いろいろな行政で励んでいただきたいと思って、この質問を終わらせていただきます。
議長(萩原達雄君) いいですか。(「はい」の声あり)
一般質問、これにて終了いたします。
本日の日程は、これで全て終了いたしました。
本日は、これで散会といたします。
大変お疲れさまでした。
午後2時56分 散会