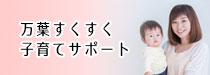本文
平成26年第4回大衡村議会定例会会議録 第1号
平成26年12月11日(木曜日) 午前10時開会
出席議員(14名)
- 1番 小川ひろみ
- 2番 早坂 豊弘
- 3番 佐藤 貢
- 4番 齋藤 一郎
- 5番 佐々木春樹
- 6番 赤間しづ江
- 7番 高橋 浩之
- 8番 細川 幸郎
- 9番 佐藤 正志
- 10番 遠藤 昌一
- 11番 山路 澄雄
- 12番 佐々木金彌
- 13番 細川 運一
- 14番 萩原 達雄
欠席議員(なし)
説明のため出席した者の職氏名
|
村長 |
跡部 昌洋 |
副村長 |
伊藤 俊幸 |
|---|---|---|---|
|
教育長 |
庄子 明宏 |
総務課長 |
早坂 勝伸 |
|
財務調整監 |
織田 四郎 |
住民税務課長 |
和泉 文雄 |
|
保健福祉課長 |
高嶋 由美 |
農林建設課長 |
齋藤 浩 |
|
企画商工課長 |
文屋 寛 |
都市整備課長 |
松木 浩一 |
|
教育学習課長 |
佐々木 修 |
会計管理者 |
木村 祐喜 |
事務局出席職員氏名
- 事務局長 齋藤 善弘
- 書記 西村 清二
- 書記 佐々木 敬
議事日程(第1号)
平成26年12月11日(木曜日)午前10時開会
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 一般質問
本日の会議に付した事件
議事日程(第1号)に同じ
午前10時00分開会
議長(萩原達雄君) 皆さん、おはようございます。
ただいまの出席議員は14名であります。
定足数に達しますので、ただいまから平成26年大衡村議会第4回定例会を開会いたします。
これより諸般の報告を行います。
議長としての報告事項及び監査委員から報告のあった例月出納検査結果の報告書については、お手元に配付しているとおりであります。
宮城県後期高齢者医療広域連合議会、黒川行政事務組合議会の報告書については、議員控室にそろえておりますので縦覧願います。
以上で諸般の報告を終わります。
陳情書については、陳情書文書表のとおりでありますが、今回は配付のみにとどめておきましたので、ご了承願います。
次に、各常任委員会の閉会中の所管事務調査の報告及び各委員会の行政視察に係る報告を行います。
各委員長に報告を求めます。
まず初めに、議会運営委員会佐々木金彌委員長、登壇願います。
〔議会運営委員長 佐々木金彌君 登壇〕
議会運営委員長(佐々木金彌君) おはようございます。私のほうから議会運営委員会の行政視察について報告いたします。
11月10日、11日にかけまして、福島県の原発のあった双葉郡の中の一つであります広野町に議会改革等、それから議会運営についてということと、震災後の経緯みたいなものを見たい点もありましたので広野町に行ってまいりました。
ここは人口5,200人、世帯数1,961戸ということで、大体大衡村と同じであります。議員が12名、東日本大震災によりまして避難を受けて、役場もいわき市に移転したというところであります。そして約3,000人が避難いたしまして、いわき市に2,900人、町内に住む者が887戸の1,750人というふうになっております。大変な被害に遭ったところです。現在、25年度の決算で復興予算が112億円だと、そういったもので運営されている状態でございます。
ここは議会広報等も3年間、全国大会で優秀等を得ているようなすごい優秀な議会活動をやっているところで私ども行ったわけですが、避難になりましてから議員の報酬は20%減、それから町長が30%減、教育長等も15%減だというような、本当にやりくりが大変な状態でやっていて、仮設に住む人が多くて、今もいわき市あたりから昼間、朝に車で来て、そして夜帰っていくという、高速料金等もただ、仮設住宅もただ、医療費もただということでありますので、そういった生活を続けていることが多くて、仮設に行って住民懇談会をやったりして、議会のほうももう住めるんだからぜひ帰ってきてくれと言っても、子供のいる家庭は拒否しているという状態であるそうです。そして放射能対策がまだ不安があるので、計画が困難だということですね。宅地造成が必要だということもありました。
町の中で、議会の研修費12万ぐらいとかいろいろなことがありますけれども、報告書のとおりでありまして、傍聴も多いのは、やっぱりマスコミ関係とかそれから町長さんが交代しているようなことでやっていますけれども、今、特に火力発電所で、当時は38億ぐらいで財政指数も1.2というすごくよい状態だったんですが、復興予算112億といっても本当に隣近辺、8市町村あるんですが、2つの村と町だけが住むことができて、あとは全部いわゆる除染作業等に通ってきているような町村でございました。
学童は、子供はいわき市からバス通学していると、それから学校給食は全て県外のものを使っていると、そういうことを聞きますと、本当に原発なり震災の大変さというのを身にしみて感じているわけでございます。今それでも広野町の駅前にジャスコが進出決定したり、中学校・高校の一貫校が開校する予定で進んでいるといった明るい状態も聞いておりました。
議会のこともいろいろ話が出ましたけれども、帰りに高速道路を帰ってくる際、他県ナンバーの機動隊が警備する中で、玄関口全てバリケード張られて、しかも田んぼ・畑は柳の木やカヤ、それからセイダカアワダチソウが出て、それらを刈り取ったりしている作業状態、そしてまた除染して汚染された土壌をトンパックで黒い袋に詰めて1カ所に100ぐらいずつ、それが何十カ所もあるという状態を高速から眺めるといろいろなことを、ゴーストタウンになるこういう町では大変だなということをつくづく実感してまいりました。早く安心して暮らせる日を念願して一つの報告としたいと思います。あとは内容を読んでいただきたいと思います。以上です。
議長(萩原達雄君) 次に、総務民生常任委員会佐藤正志委員長、登壇願います。
〔総務民生常任委員長 佐藤正志君 登壇〕
総務民生常任委員長(佐藤正志君) おはようございます。
それでは、総務民生常任委員会の事務調査報告をいたします。
所管事務調査については、廃棄物の再資源化の現地調査、各課の所管事務についてということで11月19日に実施いたしました。
配付の内容ですけれども、簡単に説明させていただきます。
廃棄物の再資源化について、大崎市の古川北宮沢の株式会社環境開発公社MCMというところを現地調査いたしました。そこの内容は、産業廃棄物の中間処理業、あるいはいろいろな特別廃棄物の収集業務をやっているというところで見学させていただきまして、大衡のごみ等々もかなりふえているということで、いろいろな面から見て分別収集というのが必要なのかなということで調査してきたところであります。あと、内容はプリントされていますので、見ていただきたいと思います。
次、各課の所管事務について。総務課については空間放射線量ということで毎日のように測定して、8月から10月末ということでプリントの検査のとおりでございます。
あと、職員の採用関係ということにつきまして、26年度は予定では上級保健師、上級栄養士の方々ということで、最終的に今現在の予定ということで、トータルは、保健師さんが1名、栄養士さんのほうが2名、あとプロの方、初級の行政事務2名ということで予定しております。以上が総務課の分。
財政課については、健全化判断比率ということで資金不足比率の状況について表に載せておりますので、記載のとおり見ていただきたいと思います。
平成27年、28年度の一般競争についても指名競争入札の参考募集ということで、塩釜地区と黒川地区の入札の契約が変わりますということで受け付けがそのようになっております。
その他、所管事務については特別会計、基金の設置などということで、報告がありました。
次に、住民税務課、平成26年度村税徴収の実績状況ということで、これも平成26年9月現在ということで表にしておりますので、見てください。
次に、条例の一部改正ということで、この改正が国民健康保険、母子・父子家庭の医療費、あと心身障害者医療ということで改正でございます。あと、臨時福祉給付金申請、あるいは子ども・子育て世帯の臨時特別給付ということで表に載せておりますので、見ていただきたいと思います。
次のページ、お願いします。
次のページの所管事務については、保健福祉課、平成26年度の特定健康診査状況についてということです。これについては各条例等の制定ということで、新型インフルエンザ、家庭的保育事業、特定教育・保育施設、あるいは放課後児童健全育成というような形で条例制定です。理由は記載のとおりでございますので、読んでいただきたいと思います。
また、下のほうにも施設の既設型のやつとあと地域型ということで表に載せておりますので、ごらんください。
次に、4事業の類型ということで、利用者は次の4つの類型の中から事業を選択するということですね。これは都市部というか、待機児童の解消を図るためということでの4事業ということで、詳しいことは今配付しております表のとおりでございますので、記載のとおりであります。見ていただきたいと思います。
以上、総務民生常任委員会の報告を終わります。
議長(萩原達雄君) 続いて、産業教育常任委員会佐々木春樹委員長、登壇願います。
〔産業教育常任委員長 佐々木春樹君 登壇〕
産業教育常任委員長(佐々木春樹君) おはようございます。
会議規則第75条の規定により産業教育常任委員会の報告をいたします。
まず調査事件です。所管事務調査、村内の企業の進出の現地調査を行っております。あと26年度請負工事の進捗状況について、その他事務についてです。調査年月日は平成26年11月21日です。
ページをめくっていただきます。村内進出企業の視察ということで、中央精機東北株式会社のほうに視察をさせていただいております。中央精機さんは、車のタイヤのアルミホイールとかスチールホイール、そういったものの製造をしているところでありまして、一通りの工場を全て見せていただきました。まだまだ、今の従業員が57名なんですけれども、今年度の新卒者の採用状況ももっと欲しいというふうなお話もありましたので、ますます頑張っていただきたいなというふうに見てまいりました。
請負工事です。農林建設課につきましては、震災後の混乱の時期と違いまして順調に全て進捗しているというふうな状況であります。都市整備課についても同じように順調に推移しているというふうに報告させていただきます。
その他の所管事務についてですが、教育委員会、大衡村心身障害児就学指導審議会条例の一部改正についての説明がありまして、今議会の議案62号でも審議される予定であります。「心身障害児」という表現が時代にそぐわないというふうなところでの改正になっております。
3ページでありますが、農林建設課の生産調整の状況の報告がございました。各行政区、ばらつきはございますが、達成率として101.7%で達成されていると。詳細については表をごらんいただきたいというふうに思います。
それから、25年度産の米の出荷状況についての報告もなされております。米価の下落で25%ぐらい減っているというふうな状況の中で、本日の新聞にも載っておりましたけれども、12月の補正で米価下落対策臨時交付金というものが提案されることになっていると、その説明を受けております。
都市整備課でありますが、大衡村の定住促進の補助金の状況について説明がされております。22年から交付しておりますけれども、総額で8,800万というふうになっております。分譲状況は表のとおりでありますので、ごらんください。
それから、おおひら万葉パークゴルフ場の利用ですけれども、来年の4月中に60万人の来場達成をするというふうな見込みの説明がありました。
企画商工課からは、大衡村の企業立地促進の条例について変更、これも議案の66号で提示されていますので、そういった説明を受けております。
最後に、大衡村防災行政無線放送施設更新事業ということで、各家庭の受信機の更新がこれから始まります。最近配られております大衡の広報にも載っていましたけれども、年明けから随時、各家庭の受信機を変更していくというふうな説明でした。委員会の中でもそういったものを悪用する業者等を入れないような対策をしてほしいというふうなお話になっております。
委員会の報告、以上で終わります。
議長(萩原達雄君) 次に、議会広報編集特別委員会高橋委員長、登壇願います。
〔議会広報編集特別委員長 高橋浩之君 登壇〕
議会広報編集特別委員長(高橋浩之君) おはようございます。
議会広報編集特別委員会は、11月12、13の両日、岩手県のほうに行って研修してまいりました。
視察地は、11月12日、岩手県岩泉町に行ってまいりました。ここは竜泉洞等が有名なところでございます。議会広報「いわいずみ議会だより」は、全国で平成3年より毎年入賞し、全国で最優秀賞2回、それから岩手県町村議会のコンクールで特選を10回というような大変すばらしい広報をつくっているところでございます。
創刊年月日が昭和48年3月20日。現在11月時点で169号を発行しております。
編集方針は、「おおひらむら議会だより」も同じなんですけれども、住民に読みやすく、わかりやすく、そして親しまれる議会報を目指して、町民と議会をつなぐパイプ役を果たすよう編集しておりました。
特徴的なところですけれども、一般質問の原稿は、議員の質問通告書、これは全文記載されておりますけれども、それから執行部の答弁書に基づきまして、編集委員が編集、つくっております。つまり一般質問された議員と答弁する執行部側の原稿の資料があるということで、それをもとに策定して原稿をつくって掲載しているというような形でございました。そして、編集委員会、そういう形ですが、2回開催されておりまして、編集委員と議会事務局で共同構成しているということございましたが、余りにも事務局にお任せしているのではということで、169号から編集委員が主体で編集することになりまして、編集委員会は9回行ったそうでございます。
研修の感想、各委員から報告書が上がっているので、それから抜粋させていただきましたが、表紙の写真が非常にきれいで被写体もインパクトがあり、文字等のバランスもよく大変好印象であったと。「まちの笑顔」をテーマとして表紙の写真を撮影しておりまして、100枚以上の中から選んでいるというような話でございました。
次に13日、この次は岩手県の雫石町を訪問して研修させていただきました。こちらは平成4年5月20日、11月現在で91号発行されておりまして、こちらも全国なり岩手県の町村議会コンクールで入賞歴があるところでございます。
特徴的なのが、全国的にも珍しい横書きの広報誌で、見やすく読みやすいということを特に数字関係ですね、いろいろな予算・決算等々の数字が横書きであるために大変読みやすいという印象を受けました。あと、一般質問者の中でも顔写真に吹き出しをつけて、議員の本音や「私はこういうことが聞きたいんだ」というような主張、そしてそのときの気持ちを一言入れるような感じの工夫がされておりまして、大変読みやすい広報でございました。そして、在京雫石町友会の会員から「ふるさとへの便り」というような形で首都圏に住んでいる方から投稿があって、それらを町民の方に紹介するというようなページもあり、住民参加型の大変すばらしい広報だったと思っております。
視察研修の総括といたしまして、どちらの町も誌面上に多くの写真を取り入れており、写真の画質もきれいで、特に表紙は被写体含めバランスがよく仕上がっておりました。また住民の声を多く取り入れているのもよかったと思います。写真と訴求力のある見出しの大切さを実感した研修でしたし、全国コンクールに入賞する広報誌の違いをまざまざと勉強させてもらったところでございます。
これからも大衡村の議会広報、議会だよりのますますのいいものをつくっていくという糧になった研修でございました。
以上、報告いたします。
議長(萩原達雄君) 以上で閉会中の所管事務調査の報告及び行政視察に係る報告を終わります。
それでは、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
日程第1 会議録署名議員の指名
議長(萩原達雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を議題といたします。
会議録署名議員は、会議規則第115条の規定により2番早坂豊弘君、3番佐藤 貢君の2名を指名いたします。
日程第2 会期の決定
議長(萩原達雄君) 次、日程第2、会期の決定を議題といたします。
本件について、議会運営委員長に議会運営委員会の報告を求めます。佐々木金彌委員長、登壇願います。
〔議会運営委員長 佐々木金彌君 登壇〕
議会運営委員長(佐々木金彌君) 議会運営委員会の報告をいたします。
本日招集されました平成26年第4回大衡村議会定例会の運営に関しまして、11月26日に議会運営委員会を開会しておりますので、その結果について報告いたします。
本定例会に付議されました案件は、村長提出案件が16件であります。
内訳は、専決処分1件、条例制定5件、条例改正11件、規約の変更1件、財産の減額貸付1件、そして26年の補正予算7件ということでございます。
議案に先立ちまして一般質問を行うこととしております。本定例会は、9名の議員から16件の質問が通告されておりました。しかし、そのうち1件が本人の申し出で取りやめとなり、15件の質問となっておりますので、報告いたしておきます。
以上の議案審議でありますので、本定例会の会期につきましては、本日からあす12日までの2日間とすべきものと決定いたしました。
以上、結果報告といたします。
議長(萩原達雄君) ここでお諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から12月12日までの2日間とすることにご異議ございませんか。
〔異議なし多数〕
議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、会期は本日より12月12日までの2日間と決定いたしました。
ここで村長に招集の挨拶及び提案理由の説明を求めます。村長、登壇願います。
〔村長 跡部昌洋君 登壇〕
村長(跡部昌洋君) 皆さん、おはようございます。
本日ここに、平成26年第4回大衡村議会定例会を招集しましたところ、議員皆様方におかれましては何かとご多用のところ、そして傍聴者の皆様方にも大変お忙しい中、傍聴していただきましてまことにありがとうございました。
ここに招集の挨拶並びに提案理由のご説明をさせていただきたいと思います。
師走に入り、大雪も過ぎ、日増すごとに寒さが大変厳しくなってきております。けさも外気は0度でしたけれども、大変寒い日が毎日毎日続いておりますけれども、早いものでことしもあと20日余りで新しい年、ひつじ年を迎えようとしております。
国会の解散により衆議院が11月21日に解散され、第47回衆議院議員総選挙が12月2日告示、14日の投票に向け選挙戦の終盤を迎えようとしております。今回の選挙の焦点は、消費税10%への引き上げを1年半先送りする方針を表明した上で、安倍政権の経済政策であるアベノミクスの成果が最大の焦点となっておるようであります。そのほかにも集団的自衛権の行使や原子力政策など、そういうものもよくテレビニュース等では言われておりますが、今後の日本の進路を決める大変大事な選挙でもあろうと思いますので、棄権をされないように投票されることを私たちは願うものでございます。
ことしは自然災害が大変発生した年でもあります。2月には2週続けて東日本が記録的な大雪に見舞われ、交通の寸断により住民生活に支障を来しておりました。
8月には、広島県北部で大雨による大規模な土石流が発生し、9月には御嶽山の噴火によって多数の死者、そして行方不明者も発生しております。また、先月には長野県北部が震度6弱の地震があり、住宅の倒壊や多数のけが人が発生しておったようであります。夜間の発生にもかかわらず死者が出なかったことは、私もテレビニュース等を見て大変よかったなと、そのように思いながら、地域住民による互助の体制の機能が発揮され人的被害を最小限にとどめることができたんじゃないかな、このように考えられます。
本村といたしましても、先月、陸上自衛隊など関係機関の協力を得ながら開催をいたしました総合防災訓練の成果を生かし、今後の災害対応に役立ててまいりたいと、このように考えているところであります。
農業関係では、ことしも105という数字が発表されました。数値的には105でありますし、それぞれの農家の方々からは反収も例年より30キロ、あるいは60キロとれましたよという声も聞いておりますが、米価が下がりまして、その下がったことによって農家の方々の打撃も大変あったんじゃないかなと、このように感じられましたので、この後の補正予算で村のほうでも補助金として、けさも新聞に載っておりましたけれども、補助金を補正予算に計上してまいりたいと、このように考えております。
交通死亡事故ゼロが続いておりましたが、11月29日早朝、枛木地区内の国道4号線でバイクとトラックによる交通事故が発生いたしました。バイクを運転していた76歳の女性が亡くなりまして、平成22年12月22日から死亡事故ゼロが続いておりましたが、1,439日で途切れました。リセットになりました。私たちもそのニュースを聞いて大変がっかりしましたけれども、大衡村は国道4号線、国道457号線、2つの国道がある中でも1,439日の死亡事故ゼロが続いていたということは関係機関の皆さん、そして住民の皆さん方が一生懸命に死亡事故ゼロの啓発活動をしていただいた、その姿がこのような数字にあらわれてきたんじゃないかなと、このように思っておりますけれども、また気持ちも新たにしながら、大和警察署を初め交通安全関係機関、さらには住民と連携を図りながら交通事故発生の抑制に努めてまいりたいと、このように考えておるところであります。
さて、本定例会に提案いたしました案件は26件であります。
議案第50号は、専決処分の承認を求めるものであります。平成26年度一般会計予算の補正で470万円を増額するもので、第47回衆議院議員総選挙に係る経費の補正であります。
議案第51号は、大衡村特定防衛施設周辺整備調整交付金条例を制定するもので、防衛9条交付金を基金として積み立てるための条例でございます。
議案第52号は、大衡村新型インフルエンザ等対策本部条例を制定するもので、対策本部設置に関して必要な事項を定めるものでございます。
議案第53号は、大衡村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定するものであり、児童福祉法に基づき保育事業などを実施するための設置及び運営に関する基準を定めるものでございます。
議案第54号は、大衡村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を制定するもので、子ども・子育て支援法に基づき施設及び事業の運営に関する基準を定めるものであります。これについても毎日のように選挙の中でうたわれておりますけれども、これを条例化してまいりたいというふうに思っております。
議案第55号は、大衡村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定するもので、児童福祉法に基づき事業を実施するための設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。
議案第56号は、職員の勤務時間、休息に関する条例の一部改正で、勤務時間の改正並びに条文などの整備を行うものでございます。これについても15分勤務時間が短縮されるというような条例でございます。
議案第57号から議案第60号までは、人事院勧告により条例の一部改正を行うものであります。議案第57号は、議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正、議案第58号は、特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の一部改正、議案第59号は、教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条例に関する条例の一部改正を行うもので、いずれも期末手当の支給率を改正するものでございます。議案第60号は、職員の給与に関する条例の一部改正で、勤勉手当の支給率並びに給料表の改正、条文の整備を行うものでございます。
議案第61号は、大衡村特別会計条例の一部改正で、宅地造成事業特別会計への追加、あわせて条文の追加を行うものでございます。
議案第62号は、大衡村心身障害児就学指導審議会条例の一部改正で、文部科学省からの通知を受けましてこのことを改正するものでございます。
議案第63号は、大衡村国民健康保険条例の一部改正で、出産育児一時金の改正を行うものでございます。
議案第64号は、大衡村母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部改正、議案第65号は、大衡村心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正を行うもので、いずれも法律の改正によるものでございます。
議案第66号は、大衡村企業立地奨励金条例の一部を改正し、奨励金の交付期間を延長するものでございます。
議案第67号は、宮城県市町村自治振興センター規約の変更で、法人区分の変更により規約の変更を行うものでございます。
議案第68号は、財産の減額貸付で、アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社に対するゴルフ場用地の減額貸付を行うものでございます。これは花の杜ゴルフ場関係でございます。
議案第69号は、一般会計予算の補正で、2,529万円を追加するものであります。歳入の主なものは、固定資産税、国庫補助金の増額、また歳入が確保できましたので、地域振興整備基金からの繰入金の減額を行うものでございます。歳出では、障害者福祉費、児童保育費の増額、米価下落に対する補助金の計上、道路維持費並びに台風19号による災害復旧費の増額でございます。
議案第70号は、国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正で、2,007万6,000円を追加するものでございます。歳入は国庫負担金並びに繰入金の増額、歳出は保険給付費の増額でございます。
議案第71号は、下水道事業特別会計予算の補正で、381万7,000円を増額するものでございます。歳入は使用料の増額並びに繰入金の減額、歳出は下水道管理費の増額でございます。
議案第72号は、介護保険事業特別会計予算の補正で、348万1,000円を増額するものでございます。歳入は国庫補助金並びに繰入金の増額、歳出は制度改正に伴う委託料の増額でございます。
議案第73号は、戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正で、434万9,000円を増額するものでございます。
議案第74号は、後期高齢者医療特別会計予算の補正で、121万8,000円を減額するものでございます。
議案第75号は、水道事業会計予算の補正で、収益的収入並びに支出で29万3,000円を増額するものであります。資本的支出では建設改良費の増額でございます。
以上、合わせて26議案をご提案いたしますので、原案どおりご可決賜りますようにお願い申し上げ、招集の挨拶並びに提案理由の説明をさせていただきました。よろしくお願い申し上げたいと思います。
日程第3 一般質問
議長(萩原達雄君) 続いて、日程第3、一般質問を行います。
一般質問は通告順に発言を許します。
通告順1番、佐々木春樹君、登壇願います。
〔5番 佐々木春樹君 登壇〕
5番(佐々木春樹君) おはようございます。通告2件、行っております。
1件目は、今後の介護保険はどうなる。2件目に、万葉赤ちゃん誕生サポート事業に柔軟性をというもので通告をしております。よろしくお願いします。
2025年、平成37年には団塊の世代である方々が75歳以上になり、介護が必要な高齢者の数が急増すると見られています。これに備えるべく、国は社会保障・税一体改革及び社会保障制度改革国民会議の報告書に示された内容を踏まえ、平成27年度の施行に向けて介護保険制度改革が進められています。
制度創設以降の制度改革の経緯は、平成12年に社会保障構造改革の第一歩として介護保険制度が施行され、措置制度から社会保障による契約制度へ転換しました。その際、利用者によるサービスの選択、利用料、応能負担、自分の能力に応じてお金を負担することから応益負担、受けた利益に対してそれに応じたお金を支払うことへの転換、多様な事業者の参入の促進等が図られ、あわせて老人医療の一部を介護療養型医療施設として介護保険制度に取り込み、医療と老人福祉を総合化して新たな制度を発足しました。その後、介護保険制度、さまざま改正が行われ、現在に至っております。
平成12年の制度創設以降の大きな改正が平成18年に行われましたが、この改正では、まず介護保険のほかの事業、補助事業、これは税100%補助でしたけれども、それで実施されていたものが介護予防地域支え合い事業が介護保険の中に取り込まれ、その事業費は一部介護保険料も充てられることになった。また、要支援を要支援1と要支援2に分けて要支援の対象者数をふやすとともに、要支援の介護報酬を引き下げました。
さらに、地域密着型サービスを創設し、その事業者の指定を区市町村長として地域密着型の総量管理を介護保険事業計画とリンクさせることにより、地域密着型サービスについて多様な事業者の自由な参画に一定の制約を課しました。そして新たな地域の調整機関としての地域包括支援センターの創設、このように平成18年の改正は極めて大きな改正だったと言えます。
直近の平成24年度の改正では、介護保険施設の定義から「介護療養型医療施設」が削除され、同サービスは平成30年3月末をもって廃止されることになっています。また、自立支援の観点から、自立支援型ケアマネジメントや地域包括ケアシステムが提起され、訪問介護、通所介護について機能改善志向が打ち出されました。しかし、十分な展開はされていないんではないかなというふうに思っていますし、それが現状ではないでしょうか。
今回の制度改正は、平成18年の改正を上回る大きな改正・改革と言えます。現在、今ですね、平成27年度の制度改正に向けて国民会議報告書を踏まえ、社会保障審議会介護保障部会及び介護給付費分科会で改正の肉づけ、検討が行われているようです。平成27年度の改革は、医療・介護一体改革に向けた制度改革の第一歩として医療から介護へ、施設から在宅への方針・方向を踏まえた改革ではないかと捉えています。
また、社会保障の考え方として、自分の力で行う自助、互いに助け合う互助、互いに力を合わせて助け合う共助、そして公共機関が援助する公助を基本とする旨の整理、それらを踏まえ、平成37年を目標年度とした地域包括ケアシステムの完成に向けた第一歩という位置づけでもあると思われます。自分でできることは自分で行うことを原則に、公的サービスに頼る前に地域の互助の推進、その上で共助、それでも対応できない場合には公助というふうな考え方になっていきます。
要支援サービスの本体給付から除外や利用者負担の変更等が行われる見込みであります。これは26年、国会の立法改正を踏まえ、まだ決定されていませんけれども、このように大きく変わっていくだろうと考えます。特に大きいのは、まず1点目に、要支援1・2の対象者については介護保険本体の給付、予防給付から訪問介護と通所介護を外して対応するサービスについて地域支援事業を再編成するということ。個別のサービスでは通所介護の機能改革、特に定員10名以下の小規模型については地域密着型サービスへ移行させ、今後新たな事業所開設については保険者の管理下に置くということ。特定養護老人ホームの入居対象者を原則、要介護3以上とすることなどです。これからの改正を実施していく等、行政のトップである村長の力量、また考え方が問われてくるというふうに言われています。
そこで、通告にあるように、来年の8月から年金収入が280万円以上の人の自己負担が2割になると。厚生労働省では、在宅利用者の約15%の方、また特養に入居している方の5%が該当するというふうに見ておるようですけれども、村ではどのように試算しているのか。
また、要支援を対象とする予防給付のうち訪問介護と通所介護について、来年4月から3年かけて医療・介護総合確保推進法をもとに市町村が取り組む地域支援事業に移行されます。今までどこのまちでも全国一律のサービスだったものが、この改正によって市町村の財政状況、またトップの意識次第でサービス内容にすごい差が出てくる。いろいろな報道でもあるように「隣まちではここまでしてくれるのに、うちのまちではここまでしかしてもらえない」とか「負担が私たちはとっても多くてやっていけない。でも隣の同級生は楽しそうだな」というふうなニュースとかそういう報道もあったかと思います。そういったところで、村が来年から施行されるであろう改正に対してどのように考えているかをお伺いするものであります。
2件目の万葉赤ちゃん誕生サポート事業に柔軟性をというふうに題して質問しておりますが、平成20年3月に制定され、多くの妊婦さんにタクシー利用券が交付され、利用実績もまずまずというふうな報告も受けておりますし、申し分ないわけですけれども、その中でも交付を申請されない方もいるというふうなことも聞いていますし、「タクシー利用券は助かったけれども、もっと違うもの、例えば紙おむつとか粉ミルク、そういったものが支給されてもそれはそれで助かるんですけどね」という話もよく伺うようになってきました。
そこで、もともと妊婦さんを助けるという意味でのタクシー券ではありましたが、もっと支援していくというふうな観点の中からいろいろな選択ができる、そういう柔軟性を持って赤ちゃんサポートを改正していってはどうかというふうなことを通告しておりますので、村長、執行部の考えをお伺いします。以上です。
議長(萩原達雄君) 村長、答弁願います。
〔村長 跡部昌洋君 登壇〕
村長(跡部昌洋君) お答えをいたします。
今、佐々木春樹議員の質問を聞いておりましたら、本当に勉強されているなということを感じさせられました。
まさに平成18年度の改正からしばらく改正はなかったんですけれども、介護保険制度が今度大幅に改正になると。さらにはその自治体、自治体の判断もこれからは必要になってくると。今まで全国一律にやっていたものを、今度はそれぞれの市町村の、一番は財政状況なんです。財政状況によってその中身も違ってくると。早く言えば、国のほうで少し逃げたなと。国の方もお金もかかるものだから、各自治体に少しおんぶにだっこ、そういうものもなってきているのかなと、そのように改正文を見ながら感じさせられました。それらのことを踏まえながら答弁をいたしたいと思います。
介護保険制度は、平成12年の創立以来、所得にかかわらず利用者負担を1割としており、高額介護サービス費の負担割合も現在まで据え置かれていたところでございます。
平成27年8月、施行されるこの改正により、自己負担が2割となる、一定以上の所得者は基本的には第1号被保険者である高齢者本人の合計所得金額により判定を行い、世帯中で基準以上の所得を有する方のみ利用者負担が引き上げられるものであります。
本村では、利用者負担が2割となった場合、該当者の試算でありますが、平成26年11月1日現在の内容を見ますと、第1号被保険者数1,382人おります。要支援を含む要介護認定者は250人であります。第1号被保険者のうち基準以上の所得を有している方は32人です。第1号被保険者に対する割合は2.32%でございます。基準以上の所得を有している32人のうち要介護認定者は5名で、第1号被保険者に対する割合は0.36%であります。認定者に対する割合は2.0%となっており、負担割合が2割になると試算した場合も5名の方がいずれも居宅系のサービスを利用している方で、今後、年金などの収入が大きく、大きくといってもそんなに大きく変わらないと思いますけれども、変動があった場合も試算してみますと、今後5名ぐらいの方々がそれに該当してくるんじゃないかな。今現在そのようになっておりますので、ほとんどの方々が今までどおりの数字になってくるということで、傍聴の皆さんも聞いてくださいよ。ですから、ああ2割になるんだなと。でも、いざ試算してみると村内では5名ぐらいの方々が該当するんじゃないですか。そのほかに所得がまた出てくれば別ですけれども、今現在の数字を見ますとそのぐらいの人数になってくるんじゃないかなというふうに思っております。
また、特別養護老人ホームに入所されている方で利用者負担が2割になる該当者は、現在のところいないものでございます。
次に、予防給付が一部地域支援事業に移行することについては、社会保障審議会介護保険部会では介護保険制度の見直しに関する意見をまとめ、昨年12月に厚生労働省に報告しておるようであります。この意見書では、高齢化の進展や地域資源に大きな地域差がある中、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じてつくり上げていくことが必要であること、また今後の高齢化の進展やサービスの充実、機能強化を図っていく中で介護保険料も増加していることから、地域包括ケアシステムの構築と介護保険制度の2点の持続を基本的な考え方として、1、サービス体制の見直し、費用負担の見直し、次に平成37年度を見据えた介護保険事業計画の策定と、大きく3つの項目で意見がまとめられているようであります。
これらの意見をもとに、今後、具体的な整備内容が整備され、この内容を踏まえながら本村においても今現在第6期大衡村高齢者福祉計画、介護保険事業計画を策定しているところでございます。この後にこの件についても担当課長から答弁をさせます。恐らく皆さん、こう言ってもわからないでしょうから、答弁をさせます。
新しい介護予防日常生活支援事業の総合事業は、高齢者の日常生活を支える総合的多様なサービスを提供し、予防給付サービスを要求し、要支援者だけでなく要支援のリスクの高い方まで拡大し、切れ目のない支援を進めてまいりたいというふうに考えております。
この事業は、それぞれの地域の実情に応じてサービスが展開され、平成29年4月までに全ての市町村で実施し、予防給付の1、訪問介護と通所介護のサービスは平成29年度末に新たな総合事業に移行されるものでありまして、平成27年度、平成28年度は、移行に際して受け皿の整備に一定の時間がかかることもあると思いますので、市町村の選択によって実施できるとされております。
新たな総合事業では、生活支援サービスの充実として、既存の事業者のサービスに加えNPO・民間企業・ボランティアの活用についても検討が必要であります。移行に伴い要支援者に対するサービスの低下が生じないよう努めてまいりたいと、このように考えております。
新たな総合事業の内容により多様なサービス単位が想定されるため、平成29年度までの移行に向け幅広く情報収集をしながら、国・県の指導助言を受けながら、県内他町村との情報交換をしながら制度の実施に向けて適切に取り組んでまいりたいと、このように思っております。ですから、今の制度の中でそれぞれの自治体でとにかく財源を確保しないことにはサービスがなかなかできないということが言われると思いますので、財源の確保をしながらそれぞれのサービスをしていくと。ですから、ほかの隣のまち、まちとは違うようなものがこれからは出てくると思いますので、それらも他町がこうやったからこういうんではなく、村独自のそういうものもこれから検討していくべきでないかなと、このように思っております。
万葉赤ちゃん誕生サポート事業は、産婦人科医院のない本村において通院に係る負担軽減を図るとともに、安全・安心な通院手段の確保を図る観点からタクシー利用券の交付により健やかに出産し、あるいは出産後における有効な育児支援として平成20年4月から始めており、今年度7年目を迎えました。利用券は過去6年間で約360名の方々に交付しており、利用率は96%で、そのうち約6割の方が81枚以上を利用しているということでございます。
また、平成24年度に実施しましたアンケート調査では、約6割以上の方々から子育て支援に役立っておりますという回答をいただいており、その使途につきましても、本人及び赤ちゃんの健康診査、予防接種等に利用されており、当事業が子育て支援の一助になっているということは、私は言えるんじゃないかな。いろいろなお話がございます。タクシー券をもらったんだけれども利用しなかったという方もありますし、涙を流して助かりましたと。うちのお父さんが会社を休むことなく病院に行くことができましたと。この方、本当にうそではありません。涙を流して喜ばれました。
ですから、この事業について、タクシー券はそれぞれの選択肢ですから、利用する方は利用してくださいと。一応利用する状況になっているものですから、利用するか利用しないかはその選択肢の一つだと思います。ですが、そういう6割以上の方々が使っております。今までの議会でもいろいろ出ましたけれども、そういう方々の声も大事にしていきたいなと、このように思っております。
県内の一部自治体においても、粉ミルクや紙おむつなどの給付券を交付する事業を行っているところもあるようにも聞いておりますけれども、タクシー利用券の交付は、先ほどもお話ししましたが、健やかな出産と出産後の育児支援の考えから村独自の事業として始めたものでありまして、始めた当時は東京の何区でしたか、3万円で交付していたというのをネットで後から見ましたけれども、この事業の一定の効果や評価をいただいておることは事実でありますし、今後、佐々木議員が言ったような育児用品などの選択肢もどうかというご質問でありますけれども、これも一つの考えじゃないかなというふうに思っております。ですから、タクシー券を切るんじゃなく、選択肢の幅を少し広げることも一つじゃないかなと、このように私も考えておりますので、これについても検討してまいりたいというふうに思っております。
この後、保健福祉課長からさっき言った件について説明をいたします。一括ですから、なかなか質問できないと思いますので、答弁をさせます。
議長(萩原達雄君) 保健福祉課長。保健福祉課長にさせると言ったよね。保健福祉課長。
保健福祉課長(高嶋由美君) 今後の介護保険はどうなるということでございましたが、先ほど村長が申し上げましたように、まず第1点目の年金収入280万円以上の方の自己負担でございますが、(「村の、第6期の……」の声あり)はい。第6期介護保険計画につきましてご説明申し上げます。
まず、介護保険を運営する中で、先ほど村長が申し上げましたように、財政的な面が大事になっておりますので少し触れさせていただきますが、介護保険を運営するに当たりましては、給付費の半分が皆様から頂戴する保険料になってございます。そして国からは25%の補助、県から12.5%、村から12.5%になっております。(「第6期の大衡村高齢者福祉計画の内容を話してください」の声あり)はい、かしこまりました。どうも失礼しました。
第6期の計画は、まず1号被保険者の推移といたしまして、第6期は27、28、29の3年間の1号被保険者の推移と3年間の1号被保険者の中で介護を使われる方の推移を見定めた上で総給付費を決めて、それで運営してございます。その中で一番問題になりますのが、先ほど佐々木議員さんがおっしゃいました地域支援事業の介護サービスから居宅サービスの中の通所と、それからあと訪問の給付が抜けるということでございますので、そういうことを見越しまして平成29年度に居宅の予防サービス給付は減らしております。そして地域密着型サービスでございますが、こちらのほうは地域密着型サービスは1カ所ということで、次の計画の中でもその箇所はふやさない計画を今見込んでおりますので、29年度までにふえる予定はございません。
地域施設サービス給付費の推計でございますが、老人福祉施設は県内で総量規制がなされております観点から、大衡村では新たな老人福祉施設の建設は見込んでおりませんので定数もふえる見込みはないところでございますが、年々老人福祉施設は全部で約15名ほどの増を見込んでございます。老人保健施設のサービスは、3年間で増は横ばいと見てございます。
それらを見越しまして、要支援の予防給付の見直しをどういうふうにするかということで、先ほど申し上げましたように3年間かけて市町村が取り組む地域支援事業をどうするかをこれから調査しまして、そして最終年度の29年度に移行を考えてございます。その中で、要支援の中の地域包括システムというのは、介護保険を使っている方は医療保険も使っている。そうすると介護と医療を両方使う、そして両方負担するというのではなく、先ほど佐々木議員さんからご意見頂戴しましたように、病院から地域に戻る、それから施設から地域に戻って安心で安全な生活をするために医療と介護をどのように組み合わせて見守りをし、医療を切れ目なく、そして介護を切れ目なくしておくかということになりますと、要支援の方々はいろいろなサービスが必要になってございます。配食であったり見守りであったり、それから生活支援、お買い物をおつき合いするとかそういうような多様な生活支援のニーズがございますので、それを皆、介護保険の施設で賄うというよりは地域のそれこそ互助、共助というような中で、民間企業であったりNPOであったりボランティアであったり、地域資源をこれから発掘しながら2年間かけて整備をしていきたいと、そのような介護保険の計画を持っております。よろしくお願いいたします。
議長(萩原達雄君) ここで休憩いたします。
再開を11時25分といたします。
午前11時13分休憩
午前11時25分再開
議長(萩原達雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続けます。
佐々木春樹君。
5番(佐々木春樹君) 村長の答弁の中で、まず2割負担になる村民の数を提示していただきましたけれども、厚生労働省で試算している数値よりは随分低いのが現状であるということですが、先ほど第6期の介護保険事業計画の内容にも触れていただきましたけれども、そういった中で計算した場合、やはり厚生労働省で見ているのに近い数字が当村でも起こるのかなというところが聞きたかったところの一つでありますし、団塊の世代の方々、村長方の世代だと思うんですけれども、近い将来、必要になる、そういう年齢の方々が多いわけですから、やはり高度成長期、経済成長を支えた方々ですので、年金の多い方も随分いるんじゃないかなというふうなところであれば、この部分、非常に興味があったというところです。
それと、今後、自分でできることは自分でやって地域でできることは地域でやってというふうな、国が、悪い言い方をすれば逃げ腰というふうな法案改正でありますので、本日もこの議場に来ていますけれども、婦人会の方々とか地域の方々がこういう介護施設などでのボランティアとか、ひとり暮らし世帯の方々のところに顔を出すとか、そういった活動を非常によくやっているんではないかなというふうな中で、第5期の介護保険事業計画も随分見たんですけれども、なかなか解読できないというか、もう3カ月後には27年になるわけです。6期の計画が今提示されてもおかしくないじゃないかなというふうな感覚でおりますので、先ほど課長があれだけ答弁していますから、それなりにもう完成していて、近々計画書も出てくるのかなと思いますけれども、結局、法的な制度とかそういった部分よりも、今、村が置かれている状況が簡単に言うとどういう状況で、今後どういう方向を見ているというふうなお話を聞きたいというところと、やはり財政力によってサービス内容が変わってきますので、その財政状況を維持もしくはもっとふやして、こういったところに力を注ぐというふうな計画を立てているんですよとかそういった答弁いただければ住民の皆さんも安心するのではないかなというふうに思っていますので、その辺についてお願いします。
それから、万葉赤ちゃん誕生サポート事業の柔軟性というところで、村長「一つの考え方ですね」と、「6割の方々がいいと言っていますよ」、当然行政でやっている事業で5割以上、6割近くの方がすばらしい事業だと、助かっているというふうなことであれば全然問題ないとは思いますが、逆に言うと4割の方はどう考えているんだろうな、もしくは助かった方でも違う援助があればもっといいんだけどなという話も出ているわけですから、ぜひその辺は選択制にすれば、いや私は大丈夫ですから要りませんという人もいるかもしれませんし、ぜひおむつは必需品なので何とかいただきたいなとか、そういったニーズに応えられるような制度の改正をしていけるものではないかなと思いますので、その辺についてお願いします。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 赤ちゃんサポートですね、これ本当に、先ほども言いましたとおり100%が満足するというのは行政の中でないと思いますね。でも民主主義ですから、大方の方々がありがたかったというのも一つの民主主義の制度の中でよろしいことじゃないかなというふうに思っています。それが逆だったら、半分以上の人たちがだめだったと、余りよくないというなら考えなければならないんですけれども、そういう中で喜んでおられる方もおりましたし、先ほど佐々木議員がお話しあったとおり、選択肢の幅を持たせることもよろしいんじゃないかなというお話をされましたけれども、私も一つのいい考えじゃないかなというふうに思っておりますし、7年目に入ってきておりますので、一つの転換期にもなるんじゃないかなということで、その選択肢の幅をまた持たせながら、タクシーの利用券は廃止しないでそれも継続しながら、さらに選択肢の幅を持たせるということも考えていきたいと、このように考えているところであります。
介護保険については、保健福祉課長から答弁をさせます。
議長(萩原達雄君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(高嶋由美君) 先ほど申し上げましたように介護保険の中で要介護の方、それから要支援の方々、介護保険事業計画の中では一番大きな目的の一つとして保険料をどうするかということと、それから今後のサービスの体系をどうするかということを調べて、そして計画を立てているわけでございますが、29年度に地域包括支援をやっていくことに対しまして、今、地域包括支援センターのほうでは郡内の町と一緒に地域包括ケアシステムをどういうふうに構築していくかということを会議の中で何度ももんでいるところでございますし、それからこれからのケアマネジメントをどうするかということも検討中でございますので、今ある地域の資源、ボランティアさん、それから今まだないNPOさん、それから民間企業さん、そういうようなところでどのような支援をお願いできるのか、そしてどのような支援があるのか、これから調べていって計画に盛り込んでいっている最中でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
議長(萩原達雄君) 佐々木春樹君。
5番(佐々木春樹君) 課長、「いろいろな」とか、その「いろいろ」を聞きたいんですね。今求められているところ、やれること、やろうとしていることですね。また事業計画を作成するに当たっても、29年を目指すのではなくて年明け、来年度からもう計画に基づいていくわけですから、これは私の認識が違うのかもしれませんけれども、その計画が29年までに完成するというふうなものでつくるんであればまた別ですけれども、そうであれば逆に第5次介護保険事業計画、26年度今年度の分でいかに推移をして、その計画どおりにいったのかというところをお聞かせいただければよろしいかなと思うところと、介護保険料のほうですね、今度は支払うほうなんですが、今後村はどういった方向なのか、気になるところはその辺であります。
あと、赤ちゃん誕生サポート事業、7年目というところの中で、当時20年あたりはまだ農産物展示販売所もございませんでしたし、今はそこで地場産品の販売だったり県内産品の販売などを行えるようになったわけですから、おむつ券なりミルク券とかを発行してもそこと連携すれば配付もしていけるんじゃないかなというふうにも考えているわけですし、そういったところで村の施設の売り上げにも貢献するというか利用するようになる、みんながそこに集まるというふうな施設にしていく援助策にもなるんではないかなというふうにも考えますので、ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。
議長(萩原達雄君) まず、保健福祉課長。
保健福祉課長(高嶋由美君) まずいろいろなというのでご質問ございましたけれども、一つは今活躍なさっている婦人会の方やボランティアの方、もう一つは高齢者、団塊の世代というのは平成22年から24年に生まれた方々ですけれども、団塊の世代を見据える介護計画を立てるということも一つの今回の目標でもございます。
それで今現在、元気な高齢者の方々にもこの地域包括ケアシステムの中にも入っていただいて、元気な高齢者が多様な生きがいとそれから生活支援の担い手にもなっていただきたい。まず大衡村にある一番の資源は元気な高齢者でないかと私は思っております。元気な高齢者が見守りをする、それから買い物に付き添う、そういうような多様な要支援の方々のニーズに応えられるようなシステムをつくり上げていけたらいいなというふうに考えてございます。
それから、介護保険料のことにつきましては、これから介護保険料の算出を今進めているところではございますが、やはり給付費が上がるということを考えれば、介護保険料は今までの4,300円を維持するということは難しいんじゃないかなというふうに考えてございます。
議長(萩原達雄君) 次、村長。
村長(跡部昌洋君) 済みません、課長の答弁ちょっと間違っていると思いますけれども、まず第6次総合計画は第5次総合計画を見据えて、そしてその中で第6次計画に移すというのが第6次計画の私は役割じゃないかなと。そして3年ですから、第6次計画は3年をめどに計画するものですから、ですから第5次の計画の評価をしながら、そして第5次はこうだったんだけれども第6次はこうでいくべきでないかなということも策定の課題の一つではないかなと思っておりますので、それについても今課長もいろいろ話をしましたけれども、なかなか策定については難しいところがたくさんあると思いますね。その辺については担当課のほうで、今回入札でその計画をつくる業者が決まって今おりますけれども、ただ、それに向っても村で指導していかなければいけないですね。よく計画は業者がやると、業者が勝手にやっていくというのが多いんです、実は。隣の町と同じようなことがあるんですよ。そうじゃなく、やっぱり大衡村独自のものをつくっていくのも一つの計画の中身じゃないかなと、このように思っておりますので、第5次を踏まえたものを第6次にするべきだと。そのことによって3年間をまた見据えながらやっていくんですけれども、佐々木議員言っているように来年から始まるものですから、今ごろ具体的に出てきてもいいんじゃないかというご質問でありますけれども、まさしくそのとおりですけれども、もうしばらく中身についてはまだ発表できない点もありますし、修正しなければならない点もあろうと思います。ですから、それらも踏まえながら、皆さん方が安心して暮らせるようなものをつくっていきたいと。
ただ、難しいというものは難しいものですから、佐々木議員も何か、こういうものも計画の中に入れたらどうですかという話があれば、私たちも参考にさせてもらいますし、それを中身に入れるやら、そういうものもひとつ情報として教えていただければありがたいなと、このように思っております。
議長(萩原達雄君) タクシー。
村長(跡部昌洋君) タクシーはさっき答弁したと。
議長(萩原達雄君) いや、まだ聞いているんだ。
村長(跡部昌洋君) タクシー、さっき言ったとおりにしていってもらいたいと。
議長(萩原達雄君) さっき言ったとおり。はい。
佐々木春樹君の質問はこれにて終わります。
次に、通告順2番、遠藤昌一君、登壇願います。
〔10番 遠藤昌一君 登壇〕
10番(遠藤昌一君) 私は2件通告しておりましたが、議会運営委員長から報告のあったとおり、1件目については、以前から身に余る言動・行動、職員ひとりのみならず、その姿を見てまいりました。この姿勢を今後正していくためにも、また時間等もあり、今後の動向を見きわめていくため取り下げといたしました。ご理解願います。
2番目に移ります。2件目の自動体外式除細動器について伺います。
最近、各自治体では、公共施設のみならずコンビニ等あるいは民間にお願いし、急病に対応しているが、村では今後どのように考えているか伺うものであります。
最近、企業内や一部の施設で自動体外式除細動器、AEDを見かけるようになりました。しかしながら、大衡村においては設置場所、数は把握しておりませんが、一部の会社と公共施設に限られているようであります。突然の心肺停止は、時間、場所、誰にでも起こることであります。
心室細動のその有効な治療とされるのが心臓に電気ショックを与えることで、その役割を担う一つが除細動器と言われております。
一般人でも心肺停止に対処できるようになったきっかけは、平成14年、高円宮憲仁様がスカッシュの練習中に倒れ、40歳代で急死されましたが、病名は心室細動を起こしたと言われております。こうしたことがきっかけとなって、平成16年7月から医療従事者以外の人でも除細動器救命処置ができるようになったそうであります。
村長も、記憶にあろうと思いますが、平成15年に開催された愛知県万国博覧会の会場において、心肺停止状態になった来場者に対し一般の人が除細動器を使って救命したことが話題になりました。
除細動器を設置している自治体の一例を挙げると、兵庫県の宝塚市では「24hまちかど除細動器ステーション」と名づけ、市内の24時間営業のコンビニ店舗に対し、市が提供する除細動器を設置し、重篤な傷病者等が発生した場合、救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人、バイスタンダーというそうですが、その人が救命処置を行っているとのことであります。
心室細動が起こったとき、約10分で救命できなくなるというデータもあります。10分以内に心肺が正常に戻っても、それまでの低酸素の影響で脳などに障害が残ってしまうこともあり、少しでも早く救命処置することが除細動器と言われております。
村の地形や位置あるいは季節の変化によっては、現場までの救急車到着、全国平均時間7分と言われておりますが、全てが現着可能とは考えられないと思います。
村の母子・児童・障害者・老人などの社会福祉全般については、条例などにより各施策が講じられており、人口増加にあります。村営住宅や定住促進住宅初め施設等があるので、村民の声を聞きながら設置場所を検討するとともに、コンビニ等を初め可能な民間施設の協力を得ての設置を考えてはどうか伺うものであります。
除細動器設置にしても、ことわざにあるように「宝の持ち腐れ」として使われないのが理想であります。
私の印象に残っている言葉に、昭和47年、飛行機のハイジャックが発生したとき、政府は超法規的に、超法適用、当時の運輸政務次官を身がわりにして北鮮へ犯人を出国されましたが、この言葉の中に「人の命は地球より重い」という言葉があります。村長は緊急に早急に増設する考えがあるか伺うものであります。以上です。
議長(萩原達雄君) 村長、答弁願います。
〔村長 跡部昌洋君 登壇〕
村長(跡部昌洋君) 副村長に答弁させます。
議長(萩原達雄君) 伊藤副村長、登壇願います。
〔副村長 伊藤俊幸君 登壇〕
副村長(伊藤俊幸君) 私から答弁をさせていただきます。
ご質問の自動体外式除細動器、いわゆるAEDにつきましては、電気ショックを与えて心臓の働きを正常に戻し、心臓突然死を防ぐ効果が期待できる小型機器として村でもその有用性を認め、現在、村内の公共施設9カ所に設置しております。
24時間営業コンビニエンスストアや村の各住宅、そして特定・不特定を問わず多数の人が集まる場所にAEDを設置することは、突然、心臓が正常拍動できない傷病者がおられた場合に、その場に居合わせた方が救急車が到着するまでの間の応急救命の措置としても有効であると認識しております。
全国的に見ましても、自治体がコンビニエンスストア事業者のご協力をいただいて店内にAEDを設置する例が見受けられますし、自治会等がAEDを購入する場合に補助金を交付する例、公共的団体等が行う行事等へのAEDの貸し出しを行っている自治体もあるように聞いております。
平成25年8月に市内200あるコンビニエンスストア全店舗にAEDの設置を行った千葉県船橋市では、設置後、現在まで6件の緊急持ち出しがあったとのことでございます。
ご質問にもありますが、現在、村内5カ所のコンビニエンスストアにAEDは設置されておりませんが、今後、いざというときに救急車が到着するまでの貴重な命のリレーをその場に居合わせた方に行っていただくためにも、コンビニエンスストアに限らず、村内の公共・民間施設を含めてAEDの設置についての必要性等の調査をしてまいる考えでございます。
議長(萩原達雄君) 遠藤昌一君。
10番(遠藤昌一君) 答弁の中では現在9カ所、しかも公共施設に限定されているように捉えられます。しかし、これでは重篤の患者に果たして公共施設にだけ置いて対応できるかどうか。その辺ですよ。佐藤 貢議員も一般質問で、高齢者に対してのタクシー券の料金等の質問をされておりますが、これも大切ですよ。しかしながら、こっちのほうがまた大切だと思う、個人的にだよ。やっぱりそこにもっと力を。副村長も今後いろいろ調査しながら民間等にも配置するような考えでありますが、やっぱりまずもってこれを私としては急いでもらいたいんですよ、検討じゃなくて。副村長の考え、伺います。
議長(萩原達雄君) 副村長でいいですか。伊藤副村長。
副村長(伊藤俊幸君) 先ほどの答弁の中では、今後必要性等について調査をしてまいりますという答弁をさせていただきました。今すぐということでもございますが、どこに設置したらいいのか、あるいはコンビニさん側でどのような対応をしていただくことができるかとか、さまざまな調査すべき事項があるかと思います。まずその調査を進めてまいりたいという考え方でございますので、AEDの有用性について確認しながらとにかく調査を進めていきますという考え方でございます。
議長(萩原達雄君) 遠藤昌一君。
10番(遠藤昌一君) 執行部の考え、不一致では困りますので、村長からも答弁をお願いします。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 不一致ではありませんのですね。
これは今、先ほどの当初の質問の中でAEDは使われないほうがいいんだという、まさしくそのとおりだと思う。使われないほうがいいんですよね、万が一のためということですから。ただ、これについては副村長が答弁したとおりだと思います。
そして大衡村、船橋市みたいにだあっと大きいわけではありませんからね、この小さな大衡村で9カ所もう設置しているんだと。さらに公共施設にはほとんど入ってきておりますし、あと各集会所は誰もいないものですから、置いていてもしようがないものですから、コンビニについて、考え方として私は悪くないと思いますね。ただ、コンビニの方がAEDをどのように対応してくれるのか。コンビニの中にあっても誰も対応してくれなければだめなんじゃないかなということも、さっき言った調査の中でそういうことも調べていきますよと。コンビニの中にありましたと。しかし、いざとなったときは誰も使えませんでしたというのでは宝の持ち腐れになるじゃないかと。じゃそういうことも調査の中で検討していますよというのが調査の中身ですから、遠藤議員言ったように早急にと言ってもなかなかうまくないと思いまして徐々にやっていきたいと、そういうことも踏まえて、先ほど副村長が答弁したとおりでございます。
議長(萩原達雄君) これで遠藤昌一君の質問を終わります。
ここで休憩いたします。
再開は午後1時といたします。
午前11時56分休憩
午後1時00分再開
議長(萩原達雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続けます。
通告順3番、早坂豊弘君、登壇願います。
〔2番 早坂豊弘君 登壇〕
2番(早坂豊弘君) 皆さん、こんにちは。昼休みの時間のすぐ後ということで、疲れているところ大変恐縮であります。
今回、大幅に下落した米の概算金、つまり米の収入の8割に当たる出荷した後にすぐ支払われる一時金が25%も下落した形になりました。農家は、米の収入源としてこの概算金に所得として見出しています。農業分野では、必要資材の高騰や農業機械の高額化といった、収入に対し経費の値上がりといった実に反比例している構造となってきております。
今回、米価の大幅な下落は、来年度、さらには翌々年となるなど、その再生産ができないのではないかという声も多く聞かれています。本村の基幹産業でもある農業をいかに守り、そして構築しながら固めていけるのか、次世代の後継者につなぐことが将来的にできるのか、今真剣に取り組む必要があると考えております。
12月の一般質問の中で、この課題について3つの質問をしたいと考えております。
一つは、米の概算金が大幅に下落したこと、そのために村としての支援はという題を一つ掲げましたけれども、冒頭に村長の説明にもありましたとおり、補正予算の中で1,860万ということは、恐らくそのままでいけば30キロの米が200円の支援がいただけるのかなというふうに思っておりますけれども、この辺について、説明以外にもっと詳細があるとすればその辺もお聞きしたいなというふうに思っております。
2つ目、米価下落が極端に進んでいけば、これは受委託、そういう意味での田んぼ等、あるいは畑地等の集積にもかなりの影響を及ぼしてくるのではないかと。そうなったときに、これから進める人・農地プランにもかなり影響を及ぼすと。そういうふうになったときに、その対策として村としてはどのように考えているのかということをお聞きします。
3つ目として、米の価格不安定の中、農業収入安定のために畑地化対策を大きく進めていきたいという考えがありますけれども、一つは米にかわるブランド、そういう農産物の生産、そういうものをいかに進めていくのか。それは直売所、つまり万葉館や野菜市等にもプラスの影響を与えていくのではないかというふうに考えられます。
今、例をとってみますと、曲がりねぎが高価格で取引されているものの、まだまだ生産技術の向上、そして農地等の立地条件が整わないために品質にばらつきが生じてあります。これからは高価格で商品価値が高くなるもの、そしてまた流動性の高いものをつくる環境を整えるのが急務に求められているというふうに考えます。
参考までに、平成26年の米の販売進捗状況は、12月1日現在で宮城県産の米がまだ38%の売れ行きだそうです。6月までに米をある程度の販売推移を上げていくとすれば、なかなかそれも厳しい状況の中に今宮城県としてはあるわけなんですが、村としてもやっぱり米とそのプラスアルファになる農業生産物、野菜なりあるいはそれにかわるものであれば何でも結構なんですけれども、地場産品として考えていく必要が今あるのではないかというふうに考える次第であります。
2問目の質問としまして、BDF混合軽油、つまりバイオディーゼル燃料のことなんですが、それをさらに推進していく考えはないかなということをお聞きします。
今や農業分野では、さらなる経費の削減が求められています。しかし、農機具等の更新時期の延長や規模拡大等による経費の合理化等も考えて進めてもなかなか今はうまくいかない現状があります。また、それも限界に来ているのではないかと考えられます。その中でBDF燃料は、燃油高騰の中、あるいは不安定価格の中に使用を考えていけば朗報ではないかというふうに捉えられるわけですが、村としては、BDF、バイオディーゼル燃料を推進している。一つはバイオマスタウン構想を掲げながら、家庭から出る食用油をリサイクルしていくということでいろいろ考えているわけでしょうけれども、まだまだ知名度や理解度が上がってきていないと。これをいかに考えて、知名度・理解度を深めていけるのか。利用するに当たり、現段階では軽油減税分の33円が助成されることになっております。これも知らない人が多いのではないかと考えます。これはそういう食用油を集めているわけなんですが、もっともっと可能な限り集められるのかどうか、そしてこの制度を継続にしていけるのかどうか、その辺もお聞きしたいなというふうに思っております。これが理解度が上がってくれば利用者もふえてくる、そしてその対応はとれるのかどうか、その辺についてもお聞きしたいと思っております。
以上のことについてお尋ねします。
議長(萩原達雄君) 村長、答弁願います。
〔村長 跡部昌洋君 登壇〕
村長(跡部昌洋君) 答弁をいたします。
第1問目の農家の支援という、先ほど言いましたのは、これ以上言うことないんですよ、実は、やりますよということですから。だから、何を言えばいいかなと、さっきからいろいろ考えていたんですけれども、今回の件について、26年産米の稲作については私が言うまでもなくて、米の量はとれたんですね、全体的に。そして価格が下がったということで、じゃどうしましょうということなんですけれども、実際、農家で、私聞いてびっくりしたのは、前年よりも収入がふえたという方もおるんですよね。何なのと言ったら、収量が多かったから、当初予算を見たときよりもふえましたという方も何人かおりましたよ。そんなものかなと。ですから、一概に下落、下落という、全体的には下落なんですけれども、収量の多い方はそう言われる方が二、三人おりましたので、そういうものかなというふうに思いながら、でもやはり下落したのは確かですから、その補塡として村でも、農家の方が大変大きな打撃を受けていると。そこに私たちは企業誘致したことによって税収が幾らかずつ出てきております。その税収の一部を使ったそういう農家の皆さん方にもこういうときに還元も助成もいいだろうということで助成をさせてもらっておりますので、その件についてもひとつご理解と、そしてやるということも決まりましたので、この後の補正予算で可決していだければありがたいなというふうに思っております。
先ほども河北新報の方にいろいろ聞かれましたけれども、これは財源がなければなかなかてきないものですから、財源の企業誘致の恩恵を今回そういう形でも皆さん方にお示しをしていきたいということでやっておりますので、あとは随時一問一答方式ですから、後でまたいろいろお話をお聞きしたいというふうに思っております。
次に、受委託関係のご質問でありますけれども、この受委託関係も今後米の下落によってどうなんだというふうなご質問でありますけれども、これについてもなかなか今後の受委託関係もどうなのか私たちは余り知れておりませんし、今後の国の政策等々にも大きく左右されるんじゃないかなというふうに思っております。国の政策が農業に対していいものだったら住宅関係も大分出てくると思いますけれども、ただ、今の現状では、頼むほうは多いんですけれども、受けるほうがいないというのが現状でありますので、それらも村独自の受け手、貸し手のほうに制度でいろいろな支援をしておりますけれども、これもこれからどうなるのかということもありますけれども、何といっても国の制度によって、農政の姿によって大分この辺も変わってくるんじゃないかなというふうに思っているところであります。
また、あさひな農業協同組合においても実施するナラシ対策つなぎ金、これ理事さんだからおわかりだと思いますけれども、先日、農協のほうから利子補給について話がございました。これについても国・県・村・農協と、3体となった利子補給を6月ごろに国のお金が入ってくる間つなぎたいというつなぎ資金ですね、それを実質無利子で貸し付けることも考えながら、まず利子の補給を分担してやりましょうと。ただし、県のいろいろな事業の中で無利子のやつもあるものですから、ただ、つなぎ資金の制度も利子補給も考えながら何とか農家の方々に元気を出していただきたいということで、いろいろこれからも検討してまいりたいと思いますけれども、さらに何か答弁にならない答弁でありますけれども、でも実際やっているものですから、自慢をするわけではありませんけれども、答弁もなかなかできないものですから、やるということは事実であります。
また、畑地化におけるさらなる支援と大衡産ブランド野菜生産を考えてはどうかというご質問でありますけれども、平成23年12月の一般質問でも早坂議員から特産野菜の生産拡大をさせるための助成ができないのかというご質問がございましたね。地域水田農業ビジョンで振興作物としてナス、ホウレンソウ、白菜、ネギ、カボチャ、タマネギ、花卉などを指定しており、大衡村地域水田農業推進協議会を通して助成を行っております。
また、畑地化支援事業として暗渠排水整備に補助金、上限が50万ですけれども、その2分の1、あと畦畔を取り払った工事費として補助金、上限が30万円でありますけれども、そのうちの2分の1、排水路整備に補助金を上限50万ですけれども、その半分の助成を行っているところであります。
平成27年産米の生産数量目標については、本年より14万トン減の751万トンで、6年連続削減される方針が決定されました。今後、本村における配分などが示されることになりますが、減反分の水田を有効に活用するために畑地化による野菜の栽培などに取り組む方法もあるというふうに考えております。
現在、需要が好調な曲がりねぎの生産に取り組む方がふえておると。JAあさひなでは、仙台曲がりねぎのブランド化を目指してプロジェクトチーム、チームネギというものを設立して、平成30年には20ヘクタールの売上高1億円と、現状からの倍ですね、それを目指して取り組みたいというような考えのようでありますので、転作田の有効活用を図るために畑地化の推進と意欲ある生産者、あるいはJAあさひなとも連携しながらブランド化野菜の推進に取り組んでまいりたいと思っておりますので、過般のご質問があったとおりの内容でありますけれども、もし議員さん、何かいいものがあればひとつお聞かせ願いたいというふうに思っております。
2番目、現在本村が取り組んでおりますBDF、バイオディーゼル燃料についてのご質問でありますが、まず1点目のコマーシャルが足りないのではないかというようなご指摘でありますけれども、取り組み当初は村内全戸にチラシなどを配布して周知を図っており、現在は広報おおひらにバイオマスタウン構想の取り組み状況を毎月詳しく掲載して、BDF利用促進のための広報活動を展開しております。
また、今年度から本村が独自に開始したBDFを農業用機械に使用した場合、1リットル当たり33円の補助制度については、報道機関にも情報提供し、河北新報などの幾つかの新聞にも大きく掲載され、広くPRを図ってきておるところであります。
BDFの商品は大丈夫なのかというようなご質問でありますけれども、本村が取り組んでいるBDFは大崎市の千田清掃株式会社に委託をして精製しております。当初は揮発油の品質の確保などに関する法律の定めに基づいて、定期的に国の指定する分析機関でBDFを分析し、品質確保法の数値基準に適合しているかをその都度確認しております。国の基準に適合したものを製品として販売しており、これまでに村内の農業生産法人1団体と個人農家1名がトラクターやコンバインで使用されておりますが、BDFの使用によりエンジンなどのふぐあいが発生したという情報は入ってきておりません。通常の軽油と何ら変わりなく使用できるものと、そのような評価をいただいているところであります。あと、本村のトラック・バスなどの公用車にも常時使用しておりますが、何ら問題なく使用しておるところであります。
利用がふえた場合の対応はとれるのかということでありますけれども、現在本村でも年間約1,500リッターの廃食油を回収しておりまして、それから約1,200リッターのB100、バイオが100%燃料のB100が精製され、それを軽油と混合してB5燃料ということで、年間2万4,000リットルの製造が可能でありますので、それから見れば、何ぼ使ってもらっても大丈夫だということですから、どんどんまず使っていただきたいと。ちなみに、早坂さいで使っておるんですかね。それもお聞きしたい。(「使っております」の声あり)ああそうですか。そこのやつね、さらにPRをしていきたいというふうに思っております。
議長(萩原達雄君) 早坂豊弘君。
2番(早坂豊弘君) 概算金が下がったことに対して支援等ということで、それはきょうの新聞にも載りましたし、冒頭に村長がいろいろその辺、補正予算の中でということで説明もありましたので、それはいいとして、(2)番の今一番懸念されている、村長も今説明ありましたけれども、受委託の中で受け手がこれから少なくなってくるんじゃないかということが懸念される一つの材料になるんでないかなというふうに思うんですが、人・農地プランの中でも農地の集積、そしてまたいろいろ集落営農というのを考えていった場合に、受委託に影響が出てくる状況では大変まずいと思うんです。米の価格が下落するということは、一つの懸念材料がそこにもあるということなんですけれども、その辺もし詳しく説明できればお願いします。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 担当課長から答弁させます。
議長(萩原達雄君) 農林建設課長。
農林建設課長(齋藤 浩君) 米価下落に伴う受委託に関するご懸念ということだと思います。確かに平成26年産米の概算金が大幅に下がったということがございまして、今まで農地法の3条の貸借あるいは基盤強化法、そういったもので利用の貸借を行っているというものがございまして、それらの方々について契約の中で決めている金額あるいは米としての数量、それをお払いしながら経営を行っていくということになってございまして、それがたまたま今回切れる方もおりまして、今後新たに契約を結んでいくという方もございます。また、再契約をする際にやはり米価が下落したということもございまして、今までの反当たりの金額あるいは数量、そういったものがやはり見直しをされておりまして、簡単に言えば下がった金額でそういった契約で行っていくというようなものが多くなってきているように見えております。
また、今回、契約の途中であっても、やはり契約に基づいて貸借を行って、そのお金といいますか使用料を支払うのが大変だということで合意解約を行うというような方も中に出てきてございまして、そういった意味から考えれば、確かに受委託、利用集積、そういったものに影響を及ぼしてくると、来ているというようなことは言えるかと思います。
ただ、今後それがどういった形で推移していくのかと。この下落の傾向がことしで終わりなのか来年も続くのか、その辺に対して国の農政のほうがどうなるのか、そういったことがまだ見えない段階において、なかなか村のほうで今後の見通しをはっきりと申し上げるということは難しいんでございますけれども、国のほうでは中間管理機構、先ほどは人・農地プランというお話もありましたけれども、中間管理機構という制度になって、今大衡村ではまだ一人しか受け手の申請をされていない、そういった状況になってございますので、出したいという方がいても受け手がいないという段階で、なかなか進んでいないというのが現状でございます。
それについても使用料というのが必ず発生するものですから、そういったことについて受け手がどのくらいの利用料金ということを乗せて、設定いかんによっては出てくるか出てこないかというのが非常に難しい問題だなというふうに思ってございます。そういった形で米価下落がやはり農家の集積、そういったものに影響を及ぼしているということは言えるかと思います。
議長(萩原達雄君) 早坂豊弘君。
2番(早坂豊弘君) このことについてまた質問いたします。
私も何件かの方から話をいただいているんですけれども、先ほどの話の中で私がした説明なんですけれども、米の進捗状況が38%、12月になってもそれだけしか売れていないと。ということは、例えば卸問屋であったり、JAもそうなんですが、特に関東のほうのJAは50万トンまだ売り切っていないという話をいただきました。そうすると、来年のこれも米価に影響してくるんでないかなというのは懸念されるわけなんです。
今、米の流れというのはなかなかいい情報が伝わってこないわけですけれども、その中で、農業に関しては集積なりあるいは受委託というのもこれからもっともっと進んでいかなければないのかなと。それも一つの集落のシステムなのかなというふうに考えるんですけれども、ことしは確かに村のほうでも米価下落対策臨時交付金というのがまず補正予算の中で上がってくるわけなんですが、長期的に見た場合、どういうふうにか考えられる方向性というのは見出せるのかどうか、その辺お聞きしたいと思います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 担当課長から答弁させます。
議長(萩原達雄君) 農林建設課長。
農林建設課長(齋藤 浩君) ただいま在庫のお話が出ましたけれども、国のほうに去年6月時点で222万トンの在庫があって、前年同期の224万トンに次いで過剰な在庫、これが国全体であるということで、それらの影響も受けて米がなかなか上がらないといいますか、下落しているということでございます。また、それらを受けて27年産米の生産数量目標というのが設定されましたので、それに基づいての標準的な収量、そういったものによって米の価格についての安定性が図られていくんだろうというふうには思ってございますけれども、なかなか難しい問題だなというふうに思っているところでございます。
議長(萩原達雄君) 早坂豊弘君。
2番(早坂豊弘君) それでは、まず集積、そしてまたいろいろ集約化される中で、田んぼが田んぼとして使われるのではなくて、畑地化を進めながら野菜をつくっていって、まず副収入のような形で収入を上げていくという方向性があります。先ほども曲がりねぎを例にとりましたけれども、いろいろそういうものが大衡村の中でブランド化が定着化してくれば、大衡村に行けばこういういいものがあるよという話も伝わっていくと思うし、それは直売所でも販売の売り上げにもつながってくると思うんですけれども、ただ、そこにかかわってくるのは村でも例えば畑地化対策20万の補助金ですとかいろいろ考えてもらってはいるんですけれども、生産技術にもいろいろ技術格差がありますし、先ほども言ったように農地にも立地条件がかなり異なっているところもあるのが大衡村だというふうに理解しているわけなんですが、その辺どういうふうに考えるのかをお聞きします。
議長(萩原達雄君) 農林建設課長。
農林建設課長(齋藤 浩君) 畑地化支援事業につきましては20万円というお話が出ていますが、20万円ではなくて、畑地化する支援事業といたしましては、村長答弁しておりますけれども、暗渠排水整備の場合に補助率2分の1で上限50万、畦畔撤去については2分の1補助で上限30万、排水路整備については補助率2分の1で上限50万という形のハード的な助成措置は行ってございます。
それで、これから来年に向けての転作関係の畑地化についてということでございますけれども、26年産の転作関係の内容を見ますと、花卉を除いた場合ですけれども、転作でネギをつくっているというのが一番多くて2万9,134平米、これがネギの作付の転作という形になってございます。また、JAあさひなさんのほうでのネギ部会がございますけれども、平成24年にはネギの作付者といいますか、そういった方が11人だったんですけれども、26年には14名にふえていると。面積についても121アールから171アールというふうに、面積そのものもふえているということで、JAさんのほうで行っている曲がりねぎのプロジェクトといいますか、そういった活動が実を結んできているんだなというふうに思ってございます。
ですので、村といたしましても、ネギ、曲がりねぎをつくる際の助成関係についてJAさんのほうとタイアップをしながらそういった助成措置も設けてございますので、そういった取り組みについては村のほうとしても支援をしていきたいというふうに思ってございます。
議長(萩原達雄君) 早坂豊弘君。
2番(早坂豊弘君) 大衡には反収で正直言って50万近く上げている曲がりねぎ農家もおるわけなんですが、そういう方がいれば、野菜でもいろいろ先進農家がいると思うんですけれども、そういう方をプロモーターに掲げながら生産技術の向上、そしてさらに今言ったように補助事業に当たる畑地化対策の中で暗渠とかいろいろ進めながら、そういう事業展開というのはこれからもっともっとやっていく考えはあるのかどうか、その辺お聞きします。
議長(萩原達雄君) 農林建設課長。
農林建設課長(齋藤 浩君) 生産技術の向上につきましては、先ほど申したように、チームネギという組織が農協のほうにもできておりまして、その支援体制が図られてきているということと、あとは普及センター、そういったものと技術的なところについてはご相談をしながらやっていくということになろうと思ってございます。
議長(萩原達雄君) 早坂豊弘君。
2番(早坂豊弘君) 農協のほうも知っています。ですけれども、農協の場合は黒川郡全体で見ているんですね。私が考えたいのはやっぱり大衡のブランドというのをまず真っ先に出さればいいのかなというふうに思っていたんですけれども、そういう意味での黒川郡の中でも大衡が特に突出していいものがあるんだというふうにもっていければいいのかなという考えでお聞きしました。いかがですか。
議長(萩原達雄君) 農林建設課長。
農林建設課長(齋藤 浩君) ぜひ郡内でも大衡が突出したというような状況になることが望ましいというふうに私も思いますので、その辺についてはいろいろ農協さんのほうとタイアップをしていきたいというふうに思います。
議長(萩原達雄君) 早坂豊弘君。
2番(早坂豊弘君) 次に、質問事項の2件目です。BDF燃料についてお聞きします。
私、いろいろ資料をもらったんですけれども、実際に食用の廃油を集める場所、店等がリストアップされていますけれども、その辺のPR等はされていますでしょうか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 担当課長に答弁させます。
議長(萩原達雄君) 企画商工課長。
企画商工課長(文屋 寛君) 廃食用油の回収の関係でございますが、当初は役場で回収しておりまして、すぐさま各地区の集会所のほうに広げまして、廃食用油の回収活動を村内一円に広げていったと。昨年から集会所ではなくて各地区のお店屋さんとかあと事業をやっているところとか、そういった一般の方の軒先といいますか店先といいますか、そういったところをお借りして回収に努めているという状況でございまして、都度、村の広報誌でも大きく説明を載せていますし、あと全戸にチラシ等も配布させていただいたり、あとそれから掲示看板ですね、集積所の縦長の看板、そういったものも掲示させていただいて広くアピールをしてきたと。先ほど村長が申したとおりでございます。
議長(萩原達雄君) 早坂豊弘君。
2番(早坂豊弘君) 今、軽油の価格もばかにならなくて、農協等でも免税軽油の手続ということを進めているんですけれども、あれも結構手続が面倒でなかなか使いづらいというリスクもあるんです。そういう意味でBDF燃料というのは、先ほども話されたとおり、33円分の助成があるということでは使うのにすごいメリットがあるものだなというふうに考えるわけなんですけれども、ましてや今いろいろ畜産農家あるいは生産組合等でも大型機械が入るようになってきました。そうしたら燃料もかなり利用されているんでないかなというふうに考えるんですけれども、これがもっと普及してくればそういう意味での生産コストにつながるんじゃないかなというふうに考えるんですけれども、その辺の考えはどうですか。
議長(萩原達雄君) 企画商工課長。
企画商工課長(文屋 寛君) バイオマスタウン構想につきましては、そもそもの基本的な考え方といいますのは、地域の循環型社会、そういったものを資源の有効活用、循環型社会をつくりましょう。あとそれから自治体みずから低炭素社会、二酸化炭素を排出しない環境に優しい自治体をつくっていきましょうというのが当初のというか、それが基本的な狙いでございまして、その中の一環としまして廃食用油を回収して、環境保全の啓発も高めながらやってきましょうというのが本来の目的でございます。
今、議員さんおっしゃいますように、農家の使用を広げていくということ、これも大きな狙いではあろうと思いますので、その辺に関しましても使用されている農家の方から33円の補助というふうなご要望もございましたものですから、村としてもそれを対応させていただいたという考えでございます。
議長(萩原達雄君) 早坂豊弘君。
2番(早坂豊弘君) 確かに今課長言われたとおり、バイオマスタウン構想は環境そしてリサイクルという意味での構想だと思うんですけれども、やっぱり使用する人が多くなればなるほど理解度も深まってくるんじゃないかなというふうに考えるわけなんです。いろいろ広報誌等、あるいは新聞等でも、村長の説明にもありましたけれどもコマーシャルはしているんだよというんだけれども、なかなか、私もつい最近になって知ったわけですけれども、実際これをやっぱり使うことによって経費の削減にもつながるんで、使う側の立場に立ったコマーシャルもやっぱり必要なのかなというふうに思うんですけれども、いかがですか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 今、早坂議員、最近知ったという話聞いて私びっくりしましたけれども、もっと前からPRしているものですから、「最近知った」では私たちの今までのPRが全然わかってもらえなかったなというふうに思っております。ですから、私たちもいろいろな広報を使ったPRしております。議員さん方もPRしていただきたいと思います。そのことによって村全体がいい形になって進んでいくものですから、そこが村ばかりでPRする、何するというんでなく、議員さん方もそれをPRしてもらえれば農家全体の方々がPRになるんでないかなと思いますので、その点もやっぱりご理解とそしてご協力をお願い申し上げたいというふうに思っております。
議長(萩原達雄君) 早坂豊弘君。
2番(早坂豊弘君) 最後に流通についてお聞きします。
大崎の千田清掃さんのほうに製造して販売してというか、やってもらっているということなんでしょうけれども、例えば普通の軽油のように注文すればすぐ入ってくるような体制はとれるのがどうか、その辺、最後にお聞きします。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 課長からお答えします。
議長(萩原達雄君) 企画商工課長。
企画商工課長(文屋 寛君) 現在、大崎市古川の千田清掃さんのほうで精製をしていただいております。注文をしていただければ千田清掃、たしか2キロか3キロでしたか、ローリー車を持っていますので、そちらのほうで大衡村のほうまで配達をしていただくというふうな体制はとってございます。ただ、20リッターとか50リッター、細かい数量だとなかなかその辺の対応は難しいかと思います。例えばドラム1本分とかせめて100リッター単位ぐらいですか、そういった形でのご注文であれば2キロ、3キロのローリーで配達をしていただけるというふうな体制はとってございます。
議長(萩原達雄君) いいですか。
次に、通告順4番、小川ひろみ君、登壇願います。
〔1番 小川ひろみ君 登壇〕
1番(小川ひろみ君) 通告に従い、「英語教育をどう考える」「旧園舎の今後は」と題し、2問一括でご質問いたします。
初めに、英語教育どう考えるでご質問いたします。
文部科学省は、現在、小学校5年・6年生で必須となっていた英語・外国語活動を正式教科に格上げし、小学3年生から英語教育を開始する方針を発表いたしました。
最近の子供たちは、テレビやALTなどを通じて外国人や異文化と接する機会を相当持っており、英語活動への抵抗力は少ないと言われています。大衡の子供たちの環境も、ALTや学友と接しており、変わりないように思われます。特に学友とのかかわりは刺激になっているようです。そして小学生の柔軟な適用力は、将来の実践的コミュニケーション能力を育成するために大事になり、英語力の向上にもつながるのではないでしょうか。また、グローバル化が進展する中で必要性が高まり、小学校での英語教育を充実させることは、次世代を担う子供たちに国際的なコミュニケーション能力を育成することにもなると考えます。
現在、取り組んでいる本村での英語教育は、どういう状況での指導でしょうか。今後の英語教育における教材やIT機器の活用、人材の活用を積極的にやっていく必要があるとも考えます。本村の英語教育は、こども園・小学校・中学校と連携することが大事になると思われます。定期的な情報交換、専門家を加えての研修をすることにより、特色ある独自の体制での施策が行われるのではないでしょうか。村長の考えをお伺いいたします。
次に、旧園舎の活用についてご質問いたします。
村立幼稚園から万葉こども園になり3年がたちました。旧幼稚園舎は現在、維持に年間60万円の経費が費やされている現状です。震災での被害で修繕した箇所もあり、このままの状態ではもったいない施設です。今後の経過次第では老朽化も進み、改修での活用も費用がかさむことになるのではないでしょうか。そして、解体してでの活用が望ましい状態にもなりかねないと思われます。
旧幼稚園舎の活用については各部署よりさまざまな要望が出されていると思われますが、そろそろ方向性、具体案を示す時期ではないかと考えます。村での宅地開発は、塩浪団地分譲が28年度予定されております。土地を買い、家を建てるという大きな夢、大きな買い物には周辺施設、環境が大きな要因になることと考えます。そして、福祉の充実、教育の充実なども影響するのではないでしょうか。旧幼稚園舎の今後の方向性、具体策を伺い、2つ一括質問し、村長の考えをお伺いいたします。
議長(萩原達雄君) 村長、答弁願います。
〔村長 跡部昌洋君 登壇〕
村長(跡部昌洋君) 第1問目は、後から教育長に答弁をさせます。
第2問目の旧幼稚園舎の今後の活用ということでありますけれども、旧幼稚園舎の跡地については、こども園ができてから3年を経過し、今こども園の園児数も大分ふえて、先日、発表会がありました。その発表会のときに、午前と午後の2回に分かれて発表会がありましたけれども、立ち見席がいっぱい出るくらい多くのご父兄、家族の方々が来られて発表会を見ておられまして、村のほうにも、あるいはこども園のほうにもよかったというお手紙などもいただいておるくらい本当にこども園をつくってよかったなというふうに思っておりまして、ただ、旧幼稚園舎の跡地はどのようにしたらいいのかというようなことだと思いますけれども、年間62万円ほどかかっておりまして、これは必要経費、できるだけ少ない経費で何とか建物を維持していきたいということで、今、鋭意維持しておりますけれども、幼稚園の跡地の活用については、細川議員から今までもご質問がございました。その折、いろいろ答弁をしておりますけれども、今年度の施政方針にも出ておりますけれども、障害者の社会参加を促すための多機能型障害者施設の誘致、これを考えておるということはそのときもお話しした覚えがございます。このような施設への活用もこれからやっぱり大事じゃないかなというふうに思っております。
また、平林地区の地区計画の中での旧幼稚園跡地は公共公益地区指定でありますので、公共施設以外の建築は認められませんが、障害者支援施設は公共施設に該当するものでありますので、施設整備には支障がないものと、このように思っております。ですから、簡単にいろいろなもの転用できるかというと、できないんですね。公共公益地区指定というものがありまして、この中に公共施設以外のものは認められないというものですから、公共施設のものをやっていきたいということであります。
また、改修による活用、または解体による活用かとのご質問でありますが、跡地活用の方針と一緒に判断していくものがあると思いますので、ですから、解体ありき、存続ありきじゃなく、じゃ次に何をやるのかと。その目的を持ってこの跡地の利用が図られるものと、そのように思っておりますので、もうしばらくその辺も見ていただきたいというふうに思っております。
以上であります。あと教育長から答弁をさせます。
議長(萩原達雄君) 教育長、答弁願います。
教育長(庄子明宏君) ただいまの大衡村の英語教育をどう考えるかというふうなご質問についてお答えいたします。
内容としては、現在の英語教科としての活動はどうなっているのか。2つ目としては、英語教科に対し外部の人材の活用はどのようになっているのかというふうな内容でございました。
まず、一つ目の現在の英語教科指導についてどのようになっているかということについてお話をいたします。
学校における外国語活動は、その国の言語や文化について体験的に理解を深め、外国語の発音や基本的表現になれ親しませながら、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図るものと考えております。
文部科学省では、高度情報化、そしてグローバル化など、変化の激しい現代社会に対応した環境づくりを進めるため、小・中・高等学校を通じた英語教育全体の抜本的な充実を図ることとしています。平成23年度より新学習指導要領が全面実施され、小学校の第5・第6学年で年間35時間、1週間にすると1時間という時間の中で外国語活動が必修化されました。
本村におきましては、小学校では平成21年度から教育計画に基づき外国語活動、そして年間35単位時間をとって英語教育に取り組んでいます。さらに、1学年から4学年まで英語に親しむ時間を設け、年間10時間の英語教育を実施しています。
国では、小学校3年生からの英語教育の開始などを含む学習指導要領の全面改定案を先月20日に中央教育審議会に諮問いたしました。子供がみずから課題を見つけ解決を図るこれまでの知識偏重から、主体性重視の教育内容への転換も打ち出しております。小学3年生からの英語教育については、今後の審議状況を見守り対応してまいりたいと考えております。
2つ目の英語教科に対しての外部の人材活用についてのご質問ですけれども、小学校での英語教育は、児童の発達段階や学習負担を考慮して、英語とのよい出会いを実現するために担任の教師とALTが連携を図り授業を行っています。特に外国人であるALTの英語を児童が直接耳にすることによりコミュニケーション能力の育成を図り、英語が身近なものになることなどが成果としてあらわれています。これまでの実績を踏まえ、担任教師とALTとの連携を通して英語教育の推進に取り組んでいこうというふうに考えております。
議長(萩原達雄君) 小川ひろみ君。
1番(小川ひろみ君) 本村で28年度の塩浪団地計画もございます。そこに住むと思われ、将来家を求める方々の条件としては、周辺施設の整備や福祉・教育問題を一番先に調べるのが、今から住む家を求める可能性の高い若い移住者や誘致企業社員の方々がもし家を求めるとしたらそういう周辺施設を必ず見て、また考えると思われます。そのためにもあのままにしておくのではなく、なるべく今後の具体策なり方向性を示して活用するようにするのが一番じゃないかと考えますが、村長の考えをお伺いいたします。
また、2番目の質問の英語教育についてですけれども、NPO法人が宮城県において、留学生や海外留学経験者、同世代の仲間と国際交流を通じて協調性・積極性・自主性・国際性を養うことを目的とした国際交流イングリッシュキャンプというのが震災後行われています。外国語に触れたり外国の生活や文化などに触れるという、先ほど教育長言われた答弁にもありましたが、外国語文化などになれ親しんだりすることなど小学校段階にふさわしい体験学習が行われています。
本村においても、国際交流イングリッシュキャンプなどを経験させる事業など、人材育成の一環として考えて、留学生や留学経験者を外部の活用、人材活用の一つとして考え、またNPO法人の活用も必要な時期になっているのではないかなと思われますが、その辺についてお伺いいたします。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) この旧幼稚園の園舎について、今までも議会等でも何回となくご質問され、私たちも鋭意この跡地利用を考えておったところであります。
先ほども申し上げましたとおり福祉関係の多機能型の施設、こういうものを今メーンに考えてきておりますので、じゃ、これはいつできるのと言っても、時間がかかるものもありますし、あるいは国・県の補助金も該当になる場合もあるようであります。ですから、あしたにやろうというわけにもいかないものですから、そういう該当になるものは該当をさせて、そしてやるのがよろしいんじゃないかなと。さらには施設を民間にお願いするというのも一つの方法だと思いますね、運営をですね。ですから、民間の方々も取り入れた、そういう施設の運用方法もよろしいんじゃないかなということで、今鋭意検討しておるところでありますので、これに関した団体がおります。こういう方々にもその話をしております。ですから、もうしばらく国のそういう補助金制度に該当させるか、あとやってくれる方がおるかということも今から、今も詰めておりますけれども、相手のほうもなかなかですからね、なかなか同士でなかなか進まないというのも一つ言えると思いますので、この跡地利用を今言った公共的なもの、そして福祉的なもの、これをメーンに考えておりますので、それらの施設全体でなく、あと教育委員会で何か残った施設、残ったというよりも空きスペースももし出た場合は教育委員会の中で何とかできないかな。さらにあの施設の下の遊戯室なども何にしたらいいのか。あそこだと下りですから、障害を持った方が果たしてそういうものができるのかと。じゃそれも踏まえてどうしたらいいのかということも今検討しておりますので、その辺も一朝一夕にこうしますというわけにいかない。そのくらい、少しずつは前に進んでいるということですから、62万円はかかります。それ以上のものが生まれてくるという可能性もあるものですから、首を長くして待っていただきたいと、このように思っております。
またこの後、教育長からも答弁させますけれども、英語関係ですね。今こども園でも積極的に英語を教えてきております。幼稚園、保育園児の方々ですね。ある家庭に行ったら「うちの孫、ABCDEFGとうちの中で口ずさんでおりますよ」というお話も聞いております。私は、それが小学校、中学校にも進むという段階の中でいい姿が出てきているんじゃないかなと。その点についても教育長が先ほど述べたとおり、恐らく何か隠し玉を教育長持っているかどうかわかりませんけれども、この後、教育長から答弁をさせたいと思います。
議長(萩原達雄君) 庄子教育長。
教育長(庄子明宏君) ただいま小川ひろみ議員さんからご指摘がございましたように、日本の英語教育の方向性は大分修正され、これから変化していかなければならないところに来ているなと思いますし、調べたところで言いますと、隣国の中国、それから韓国、台湾等と比較しましても大分おくれていることがわかります。特に海外旅行者で日本に来る中国人、韓国人、そして台湾人の英会話を見ていますと普通にしゃべられるということで、私自身も本当に驚いてしまいます。
中国では2001年から英語教育を導入して小学校3年生から始め、週4回以上の授業を3・4・5・6年の段階でやっているという現状があります。中学生になると週4回以上の授業、高等学校も4回以上の授業があるということで大分身についているのだなというのがわかります。
それから、韓国におきましてはさらに4年早く、1997年から英語教育が小学校3年生から開始されております。中学校では1・2年生は週3回、3年生は週4回、そして高等学校では週4回、さらに選択教科においても三、四時間の英語教育が課されているというふうなところであります。
さらに、台湾も同様に、2001年から小学校3年生からの英語教育の導入をしているようです。
じゃ、日本はということですけれども、グローバル化した英語教育の対応といたしまして、やっと2014年、ことしですね、ことしの1月から有識者会議を設置いたしまして英語教育について今話し合われているところであります。そして、下村文科大臣のお話によりますと、東京オリンピックが開かれる2020年を目安にして、小学校3年生・4年生については英語を体験的に学習する英語活動という時間、5・6年生におきましては英語を教科として持っていく。さらに中学校では英語は英語で行うと。高校に行きますと、英語で英語の授業を行うのは当然なんですけれども、さらに英語による討論会あるいは話し合いを中心としたものをするということで、英語教育をもっと盛んにし、目的としてはグローバルな社会をつくっていこうというふうなところで進めている状況であります。
ちょっと名前を忘れてしまいましたけれども、先ほどのイングリッシュキャンプですか。そのほかインターナショナルキャンプというのもあるんですけれども、同様に日本に来ている外国人の留学生を1カ所に集めまして、調べたんですけれども、ことしだけでも旭川、フジ、東海、京都、関西、福岡、つくばなどでもインターナショナルキャンプというのが行われておりまして、1回に日本人参加者も含めて大体40人ぐらいの参加者でやられているというふうなことも聞きました。ただ、それはあくまでも全国単位であって、ばらばらでありまして、身近にあるようなところではないなというふうに考えられます。ただ、誰でも出られますので、こういう話も今後、小中学生には、これは中学生ですけれども、中学生には話していかなければならないことかなと思っております。
さらに、中学校の校長先生と話す機会も多々ありますので、英語教育の話を聞きますと、やっぱりALTと英語の先生の存在をなくしてはならない、ここは一番重要な問題であって、教職員の研修、そしてALTの国際交流、そして教材研究、この3つがないとなかなか英語教育はうまくやっていけない。
さらに、先ほど村長からも出ましたけれども、こども園の英語はかなりうまいものがあるということを考えますと、幼・小・中の連携のとれた英語教育も今後必要になってくるんじゃないだろうかということで検討しています。
そんなことを考えながら、黒川郡内にもALTは何人かおります。それから、この近くですと明泉幼稚園というのが高森のほうにあるんですけれども、ここでは外国の方を先生にして英語教育をやっております。この辺との連携を図りながら中学校・小学校で国際交流の場を設けるなどするのも今後必要なのかなと思いますし、先ほどイングリッシュキャンプというお話もありましたけれども、日本に留学している外国人を独自に考えるとすれば、大衡村にホームステイさせていただいて、そういう環境をつくって交流していくのも一つの方法かなというふうに考えています。
いずれにしましても、これからの英語ということにつきましては、受験英語ではなくコミュニケーションを図るための英語だということを今後考えていかなければならないというふうに考えております。
議長(萩原達雄君) 小川ひろみ君。
1番(小川ひろみ君) 村長からの旧園舎についての答弁で、62万円以上の大きなものができるという期待感を持ってそちらの質問は終わらせていただきたいと思います。
英語教育どう考えるかというご質問で、今、教育長からも答弁いただきましたが、教育長の言うように日本は英語教育について随分おくれを持っております。日本で英語教育の中で覚える単語数は3,080語、中国では6,150語、韓国では8,200語、台湾では5,180というように約倍近いおくれをとっているところが現実のようであります。その点につきましても、やはり一番の問題は日本全体の問題だとは思いますけれども、大衡において20年前にコンピューター、パソコン授業、研究授業がありました。20年前に1人1台ぐらいのパソコンがあってすばらしい教育をしたのが大衡村のその時代にあったわけです。そういう関係で、家庭環境ではなかなかできない教育を学校の中で皆同じに教育させるということが一番の目的になっていくんではないかなとも私は考えるところです。そして、だからこそ学校において生きた教育、そして生きた教材、そういうものを求め、留学生や留学経験者の方々の人材を活用していくのも一つの手ではないかと考えるわけです。
また、先ほど村長も教育長もおっしゃいましたが、こども園においても英語のちょっとした遊び、そういうものやっているようです。本村においてこども園・小学校・中学校との連携がとても大事になると思いますので、定期的な情報交換やそれに専門家を加えてどんどん伸びるような英語教育にしていただきたいと思いますが、その件について最後にお伺いいたします。
議長(萩原達雄君) 庄子教育長。
教育長(庄子明宏君) 外部の人材活用については先ほど申し上げたとおりでございます。
今後、今お話がありましたようにICT活用ということを考えまして、教材開発も含めて幼・小・中の連携をとりながら英語教育について考えてまいりたいなと思っております。
議長(萩原達雄君) ここで休憩いたします。
再開は2時25分といたします。
午後2時10分休憩
午後2時26分再開
議長(萩原達雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続けます。
次に、通告順5番、細川運一君、登壇願います。
〔13番 細川運一君 登壇〕
13番(細川運一君) 通告に従いまして、大衡村デイサービスセンターと健康増進施設について質問をいたします。
平成4年の第6回臨時会において、デイサービスセンターの工事請負契約が審議されております。建設と設備工事の契約金額の合計は1億4,450万9,000円でした。建設面積は427平方メートルで、鉄筋コンクリート平家建てです。1,056平方メートルの土地を永楽会から無償で借り受けるというものでございました。担当の課長は審議の中で、運営を七峰荘に全面委託をする。村が七峰荘に支払う業務委託料の中には人件費も含まれ、委託料の4分の3は国と県からの補助金であると説明をいたしております。
平成5年3月に事業が開始されまして、健康チェックや食事、入浴の提供、レクリエーションなどの通所介護が行われてまいりました。平成18年度からは永楽会を指定管理者として無償で管理及び運営を委託して今日に至っております。
平成25年度の永楽会事業報告書によりますと、利用定員25名に対しまして1日平均19.9人で、年間の稼働率は79.6%というものです。
デイサービスセンターは、事業開始から20年以上の間に多くの村内の高齢者の方々に利用され、通所介護を通して福祉の向上に貢献をいたしてまいりました。しかし現在は、施設の建設も含めて、介護サービス提供の主体は社会福祉法人や民間事業者となっております。施設自体を自治体で設置する必要性は、特別な地域を除けばほとんどありません。指定管理者基本協定では、1件につき10万円以上の修繕は村の負担となります。これから建設や設備の修繕が必要となった場合や解体しなければならないときは村の費用と責任において実施しなければなりません。村が永楽会に指定管理料を支払っていないということは、デイサービスセンターの運営は赤字にはなっていない上に適切に運営されているものと理解をいたします。永楽会が運営している七峰荘に隣接しているデイサービスセンターを指定管理者制度で管理していくのか、デイサービスセンターを譲渡することのどちらかが村の利益になるか判断すべきだというふうに考えます。
デイサービスセンターは行政財産ですが、今後の財政負担を考えれば、今まで施設を村と協力して適正に管理運営してきた社会福祉法人永楽会に譲渡することが行政改革になると私は思っております。譲渡することが地方自治法や補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に照らして可能なのか。法的に可能であれば永楽会と協議をすべきと考えますが、村長の所信をお伺いします。
2点目として、健康増進施設について質問をいたします。
平成26年第1回定例会の施政方針の中で、村長は、健康増進施設等を視野に入れながら地域活性化交流施設の整備を図っていくと述べておられます。万葉クリエートパークと第二仙台北部中核工業団地に隣接する交流施設の整備は、民間事業者による集客施設整備が頓挫したことで、現状はおおひら万葉館とコンビニエンスストアが営業しているのみでございます。ニーズを的確に把握して、より多くの皆さんに利用していただける施設の整備を図っていくとも述べておられますが、施政方針の中で健康増進施設という表現で活性化施設整備の一つの方向性をお示しいただいたということは、私は評価をいたします。村民体育館、パークゴルフ場、村民プールなどは健康増進施設なのだと思います。温浴施設も広い意味では健康増進施設に含まれるのかもしれません。また、体力や筋力を維持強化するためのトレーニング機器をそろえたスポーツジムのような施設なのかもしれません。汗をかけばシャワーや浴槽などが必要になってくるのだというふうに思います。
施政方針は予算に計上される各種の事業の説明とともに、村長がこれからの実施計画に反映させようとしている政策や事業を示すものだと私は思います。健康増進施設の整備を視野に入れたのはなぜなのか、また施設のもう少し具体的な内容と整備計画をお伺いいたします。
以上を1問目として村長の答弁を求めます。
議長(萩原達雄君) 村長、答弁願います。
〔村長 跡部昌洋君 登壇〕
村長(跡部昌洋君) 答弁をいたします。
まずもって大衡村デイサービスセンターの件についてでありますけれども、大衡村のデイサービスセンターは、ここにも書かれているとおり行政財産であり、大衡村のデイサービスセンターは老人福祉法第5条の3に定める老人福祉施設であり、在宅の虚弱老人等に対し、通所の方法により各種のサービスを提供し、生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上などを図るとともに、その家庭の身体的・精神的な負担の軽減を図ることも目的としておりまして、平成4年度に国及び県の補助金を受けて建設したものでございます。先ほど議員さんが話したとおりであります。土地については永楽会からお借りしているというものでございます。
整備計画においては、設置後の運営を隣接する社会福祉法人永楽会へ委託することとし、平成5年3月の開設以来、永楽会に管理運営を委託して、平成18年度からは管理委託から指定管理者と、そういう制度に移行し、現在に至っております。
指定管理者であります永楽会の報告によると、デイサービスセンターの利用登録者数は平成23年度から平成25年度までの3年間の平均で70.3人、さっき言った数字とちょっと違うかもわかりませんけれども、利用人数は1日平均17.3人という内容のようであります。
管理運営に要する経費については、制度上、これは制度上ですから、介護保険の報酬に充てられておりまして、村からの委託費は発生しておりません。基本協定により施設の増改築など1件につき10万円以上の修繕については村が負担すると、これは指定管理者の協議の中でやっておりまして、10万円以上の修繕については村でしますよと。これらについても今までは10万円というあれがなかったんですね。ことしから、おかしいんじゃないのということで管理者制度の中で一律に全部同じような形で10万円以上の修繕は村が行いますよという協定をさらに結びまして、同じ目線で同じ姿にさせていただいております。
施設建設からもう22年が経過しておりまして、今後サービスの水準を維持していくためには、これは村である限り維持費というのはかかるものですから、一概に幾らかかるというのはございませんけれども、かかることは確実であります。ですので、これからの姿を見ながら、平成12年度の介護保険制度の施行によりまして現在村内に5カ所、大和町や大崎市など周辺地域にも民間の法人の設置するデイサービスセンターがあります。公設デイサービスセンター設置と比較すると利用者の選択幅が広がってきておりますし、必ずしも公設の意義が少しずつ否めない事実になってきているんじゃないかなと。当初のデイサービスセンターは村に1つでありましたけれども、その後、民間の民設民営のデイサービスセンターが徐々にできておりまして、大衡から大和にという方もおりますし、大崎に行っている方もおりますし、加美に行っている方もおるように聞いております。ですから、それぞれ選択をして、デイサービスセンターの利用をしているというのが現実であります。
なお、永楽会への譲渡は可能なのかというご質問でありますが、この施設は国・県の補助金を受けて整備した施設ですので、通常、譲渡する場合には補助金などに係る予算の執行の適正化に関する法律によって財産分与の制限の適用を受けます。しかしながら、近年の急速な高齢化の進展や社会経済情勢の変化に対応するとともに、既存ストックを効果的に活用した地域活性化を図るため、包括的承認事項というのがあるんですね。この包括的承認事項にこの施設は該当します。なので、譲渡は可能だということでございます。
村のデイサービスセンターの場合は、事業開始後20年以上経過しておりますので、用途変更や無償譲渡、貸与することによって補助金の返還の義務は生じないというふうにも聞いておりますので、このようなことから、行政改革の一環として施設の設置目的や運営方法及び周辺の民間デイサービスセンターなどがたくさん出ておりますので、譲渡も含めて今後考えてまいりたいと、このように思っております。
次に、地域活性化交流施設の整備につきましては、当初の構想時点から温浴、レストラン、宿泊、健康増進、コンビニ、農産物展示販売施設などの整備計画を想定しておりました。最初の計画の中にこれらも入っておりました。その中で、現在はご承知のとおりコンビニと農産物展示販売所、万葉・おおひら館が整備されております。ご質問の健康増進施設につきましては、先ほど申し上げましたように計画段階から位置づけしていた施設となっていたものであります。
健康増進施設は、幼児から高齢者まで、全ての地域住民が健康で充実した豊かな生活を過ごすことのできる村づくりの拠点施設と考えており、さらには村内企業の就業の方々、フィットネスによる健康づくりも可能な施設になるものと考えております。また、介護予防及びメタボ対策による健康運動事業の充実を図る上でも効果的な施設であろうというふうにも考えております。
この施設計画の具体化でありますけれども、温水プール、トレーニングジム、フィットネススタジオ、風呂・サウナなどが想定されますが、現時点においてはまだ未定であり、今後の整備手法、これらもいろいろ考えながら管理運営形態を含めた、あるいは先進地の事例なども参考にしながら、地域活性化交流施設整備区域の未着工エリアの活用も考慮しながら検討してまいりたく皆様方のご意見を賜りたいと、このように思っているところでもあります。以上です。
議長(萩原達雄君) 細川運一君。
13番(細川運一君) 2点目の健康増進施設についてお伺いをいたします。
今、村長のほうから、当初の計画の段階から健康増進施設は中に入っていたんだと。そしてその具体的な施設名が温水プール、サウナ、トレーニングジム等だと、そのような具体名が出たんですけれども、それが一つの検討課題とはなっているけれども、必ずしもそれに限定したわけではないというようなお考えなんだろうというふうに思います。
私が今回この質問をさせていただいたのは、施政方針の中でこういう具体的にあえて表現なさったということは、担当課を含めてある程度具体的な施設を内部段階ではご検討なさっているんではないかという判断に基づくものでございまして、それを議員とすればやはり一応途中経過といえどもお伺いしておいたほうがいいと。ある日突然、全協が開かれて青写真が出てくるというのでも困りますので、その辺のところの途中経過をチェックしていくというのも議員の使命だと思って質問をさせていただきました。
健康増進施設というのは、総合計画の中で私見てみたんですけれども、具体的な施設の建設について触れられているのは総合保健福祉センターの整備という表現での施設整備の記載はございます。この健康増進施設というのはこの施設と同じものなんでしょうか。それとも含有するものなんでしょうか。それともまた別の一つの健康増進施設だという考えなんでしょうか。村の考えをお伺いいたします。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 担当課長から答弁をいたします。
議長(萩原達雄君) 保健福祉課長。違うの。都市整備課長。
都市整備課長(松木浩一君) お答えいたします。
この健康増進施設につきましては、村長ご答弁しましたように、当初構想の中の温浴施設、レストラン、宿泊施設等々に当初から構想として入っていたものでございますが、民設民営でやっていた、協議した時点では入っていなかったものでございますが、先ほども申し上げましたように、この健康増進施設という施設につきましては、住民、幼児から高齢者、それから工業団地等の就業者、さらには介護予防、メタボの対策の運動事業等にも重要な効果的な施設だというふうに考えていろいろ検討している段階であり、長期総合計画にある福祉施設と兼ねることもできる施設だろうというふうに考えているところでございます。
議長(萩原達雄君) 細川運一君。
13番(細川運一君) 村長の視野の中のどの辺に、ずっと遠くのほうに見えるものなのか、ある程度二、三年後ぐらいに実施計画に反映させるようなプランなのか。こういうのが整備されたほうがいいなと思っているものではないと思うんですよ、施政方針の中に具体的に書き込みされているわけですから。施設を整備したいというご意思があるんだろうというふうに私は理解いたします。そして、そのような健康維持のためにスポーツジムみたいな施設があったらいいんじゃないかという需要は村民の中にもあると私は思います。健康志向がますます高まってきていますので、そういう需要はあると思います。実施に移す、どのくらいで具体性を持って実施計画に反映させたいというようなお考えが希望としてあればお伺いをしたいというふうに思います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 実はあそこの施設周辺を整備したいという某不動産会社が動き始めたときに、こういう施設もということも出てまいりました。その過程の中で、地域の方々あるいは企業の方々等々から、大衡村はクリエートパークについてはあるんだけれども、就業者は早番・遅番があるんだと。その早番・遅番の中で余暇の時間を健康づくりにしていきたいものはないですかという話もございましたし、住民からは泉のスパ、あそこにあるようなものができませんかというたくさんの声があって、私もそうだなと思って某不動産屋さんといろいろ話をしておった過程はございました。
しかしながら、震災後その会社が手をおろされたものですから、その点でリセットになりましたけれども、何とかこのような施設を健康づくりにできないものかということで、遠くにもあるような、近くにもあるような、どっちともとれないような感覚で施政方針にも載せましたし、私たちは目指すものとしてそれを掲げてきております。いろいろ見させてもらいましたけれども、大変な多額の金額もかかると。じゃPFI方式はできないのかというものも大変検討に検討を重ねてきておりますし、今も没になったわけではございません。しかしながら、震災後の世の中の流れというのは、もう手を挙げて率先してやってくれるという方が震災後、なくなってきたんですね、実際には。ほかの事業が忙しくてなかなか手を出せないというのが今の流れでありますので、私たちはじゃ次の防衛補助金、あるいは国のいろいろな補助金、こういうものも取り入れたものができないかということもいろいろ今も検討しております。これについても防衛の方々とも話をして、いろいろな施設を見に行ったりもしております。ですから、全然やめたわけではありませんけれども、遠くにあるような、近くにあるような、そういう形で今模索をしているということでありますので、そういう点もひとつご理解をいただき、そして私はできればこういう施設をやりたいという思いでございますので、そのやるための手法、これを今検討しているというものでありますので、時間がかかるんじゃないかなと思いますけれども、ひとつ心はそういう気持ちでやってきているということもご理解をいただきたいと、このように思っております。
議長(萩原達雄君) 細川運一君。
13番(細川運一君) 村長はトップセールスの傍ら全国各地をいろいろお歩きになっていると思うんですけれども、大衡村が整備するような施設の類似施設を視察なさったというご経験があるならば、何県にあるこのような施設で、行政でかかわって建設した施設だよとか、企業等にお願いしてつくってもらってやって運営しているこういう施設もあるよというようなことで、具体的に私たちが「ああ、あそこの施設か」というふうに納得できるような施設をもしお挙げいただけるんであれば教えていただきたいというふうに思います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) まだ教えるまではいかないですね。いろいろ検討して検討しておりますので、「何だ、こんなところか」なり「何、こんなにお金かかるのか」となるものですから、皆さん方にお示しできるような姿が出てくればお話ししたいと思いますけれども、今の段階ではまだ模索しているということでありますので、その時期が来れば。ただ、お金がかかるということはあるようでありますので、やっぱり温浴施設等々もあるものですから、大変な多額の金額がかかるということでありますので、その補助金もいただきながら整備していきたいなと、このようにも考えております。
議長(萩原達雄君) 細川運一君。
13番(細川運一君) 今まで村がいろいろ施設整備をしていきました。そして私たち議会もいろいろな質問なり質疑をしてきた経緯がございました。そして私思うのは、建設的な議論は少なかったのかなというふうな実感を持っております。なぜかというと我々議会が、村長さんがそういう施設を整備する計画に至った考える過程みたいなものがいろいろあったと思うんです。そういうようなもののプロセスが私たちはわからない、最終決断だけを示される、その中での決断もわかれば余計な不毛な議論もする必要はないし、合意できる中で建設的な討論の中で施設が整備されていくんだろうというふうに思います。
まして、温浴施設という多大な税金がかかるような施設だとすれば、まずこの施設の総合計画への位置づけ、さっき防衛の予算というふうにおっしゃいましたけれども、財源措置、それから維持管理費のランニングコスト、そういうようなソフト面の説明も一緒に建設のハードのプランと同時にお示しをいただくようにすれば、議会としても建設的な審議ができるのではないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。将来のためにお願いをしておきます。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 今の、やるんだったら頑張ってやりなさいというような一つの推進のほうのお言葉にも聞きましたけれども、宮城県で近くにあるのは泉のスパですね、ごみの焼却施設のエネルギーをもらってやっていると。ですから、ここで一番近いのは、あそこにもし行かれたときはごらんになっていただきたいと思います。大変立派な施設でありますけれども、ただ、お金も大分かかったようでありますので、ああいうものの少し小さいものもどうかなというふうに思っております。ただ、具体的に方針が決まるような形になれば皆さん方にお示しもしますけれども、今の段階ではなかなか言えないんですけれども、先ほど細川議員さんの、そういえば議会に示せば議会も理解するよという言葉を信じながら、これから前向きに進めてまいりたいと、このように思っております。
議長(萩原達雄君) 細川運一君。
13番(細川運一君) どんな行政目的達成のための施設でも、ないよりはあったほうがいいのは当然ですし、それも村単独で設置するよりも広域で利用を考えたほうがいい施設もございますし、そういうランニングコストも含めたことがきちっと説明されて、これくらいの税負担で維持できるんだよと、だけれども、これくらいの施設ができるんだよということを総体的に評価できる判断を示していただければ建設的な意見交換なり審議ができるというふうに思います。
健康増進施設についてはそれくらいにさせていただきます。
デイサービスセンターについてお伺いをいたしますけれども、20年以上もたっているわけです。そして鉄筋コンクリートづくりですか。そして平成27年度から29年度までに新しい地方の公会計を原則として自治体は導入しなくてはいけないことになっておりまして、そのための下準備として固定資産台帳の整備ということが求められているんだと思うんですけれども、デイサービスセンターの帳簿価格というんですか、もし把握なされているのであれば今のデイサービスセンター、1億何ぼでかかったんだけれども、価値とすれば、帳簿価格とすればこのくらいだよというのももし把握なさっているんであればお伺いをしたいというふうに思います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) これについて行政財産でありますので、担当課長から答弁をさせます。
議長(萩原達雄君) 保健福祉課長。建物の残存価格だと。今の評価額。
保健福祉課長(高嶋由美君) 申しわけありませんが、今は把握しておりません。
議長(萩原達雄君) 細川運一君。
13番(細川運一君) 今回、デイサービスセンターについて情報公開請求をさせていただきました。知りたい部分は黒塗りでございました。その中でも、黒塗りされていない部分を見ますと、財産目録の中に大郷町のデイサービスセンターってあるんですよ。それが1億1,300万の取得価格としての簿価として載っているわけです。これは大衡より1年後に建てた施設なんです、大郷のデイサービスセンターね。ということは、大郷のデイサービスセンターはもう譲渡されているんでないかなというふうに私は理解したんですけれども、そういう認識でよろしいんでしょうか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 担当課長から。
議長(萩原達雄君) 担当課長、わかる。保健福祉課長。
保健福祉課長(高嶋由美君) いつ譲渡されたかは把握しておりませんが、譲渡されておると聞き及んでおります。
議長(萩原達雄君) 細川運一君。
13番(細川運一君) 多分、毎年財産目録というのは変わるから、毎年度出されてくるものなんだろうというふうに思います。その中で、お互いに似たような時期にデイサービスセンターを建てているんで、そして大郷は私もいつ譲渡したんだかわかりませんけれども、その情報というのは担当課がその書類を見ればわかるんですよね。村長さん、デイサービスセンター、大郷で譲渡したみたいなんだけれども、大衡村でこのことについて検討してみなくてはいけないんでしょうかなというような議論は今までなかったわけですか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 今まではなかったですね。細川運一議員からのこの前の質問ありましたね、委員会でしたかね、そのときが初めてでありますので、今までそういう譲渡関係の話はなかったです。
議長(萩原達雄君) 細川運一君。
13番(細川運一君) じゃ、いつ譲渡したかわからないということは、有償だったか無償だったかということもわからないということですか。
議長(萩原達雄君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(高嶋由美君) はっきりはわかりません。
議長(萩原達雄君) 細川運一君。
13番(細川運一君) 永楽会が出している情報を見ますと、一応施設の七峰荘、デイサービスセンターに隣接している七峰荘も随分古くなっておりますので、当然建てかえのための積立金をしております。見ててみると数億円でございます。もう少しで積み立ての目標額になるんだろうというふうに思います。それを設定しているのが大体平成40年に建てかえという一応の計画を永楽会ではお持ちのようでございます。ずっと指定管理を続けていって、平成40年間際に近くなってから解体費用かかるから譲るからというんでは、今まで村と協調してデイサービスセンターを運営してきた永楽会に対して私は失礼だと思います。ある程度もっと前の段階、今の段階、修繕をかけなくてもいいような状態で永楽会に協議を申し入れるというのが今まで協力していただいた永楽会に対する最低限のそこは礼儀ではないかと思うんです。まずそのことが村のためになるからなんです、私の考えでは。永楽会の利益を私は考えているわけではありません。ただ、でも、村に本部がある社会福祉法人でありますので、お互い、いつの時代、どのような協力関係で福祉の向上に行くかもわかりませんので、その築いてきた関係というのは大切にしていかなければいけないんだろうというふうに思います。
村長は譲渡を含めて検討なさるというようなことでございますけれども、いつまで検討がされるんでしょうか。村長がデイサービスセンターを永楽会に譲渡するとデメリットだと、これが悪いことだと、短所だと思うことは何なんでしょうか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) デメリットはないと思います。
議長(萩原達雄君) 細川運一君。
13番(細川運一君) デメリットがないんでしたら、やっぱり最高責任者である村長の決断一つなんだろうというふうに思います。大郷の前例もございますし、法律的にも可能だということであれば、村長が担当課長に早く譲渡の方向で永楽会の意思を確認して、その方向性で協議をしなさいということをご指示いただけないでしょうか。
村長(跡部昌洋君) そのように指示をしてまいりたいというふうに思っております。
議長(萩原達雄君) 次に、通告順6番、齋藤一郎君、登壇願います。
〔4番 齋藤一郎君 登壇〕
4番(齋藤一郎君) 齋藤一郎でございます。
2件通告しておりますが、一問一答方式で一般質問をいたします。
まず、現在進められている塩浪地区の団地計画は、都市計画マスタープランに位置づけられておりますけれども、これほど大衡村にとって一大事業が既に今年度から動き出しているにもかかわらず村の基本計画には載っておらず、平成25年3月発効した実施計画、この実施計画は3年ごとのローリングの計画でございますけれども、その3月発効した平成25年から27年度の実施計画にすら載っておりません。村にとって一大プロジェクト事業が村長の計画性のない思いつき計画でしかないものと私は考えております。それだけに、今回の事業計画はプロポーザルによらない形での進め方をするとすれば、リスクのほうも高い事業推進方法だと私は思っております。しかし、私どもその事業を承認した議会とすれば、推進状況を把握しながら事業を見守っていかなければと思っております。
そこで、今回全員協議会で説明された中でその工事の施工管理費が含まれておらないようでありますが、職員が直接施工監理をしていく方法をとるのか、またコンサルに依頼して進めていく監理方法をとるのかお伺いするものであります。
2つ目に許認可関係の見通しでありますが、計画では27年度から工事着手とありますが、宮城県と関係してまいりますけれども、年度内にそれらの手続関係が完了するのかどうか、その辺の見通しを伺うものであります。
3つ目は、開発に伴う防災調整池の考えでありますが、現在のため池を堤体かさ上げし、防災調整の役目と農業用水の確保を図っていかなければならないわけです。そのために地元水利組合との協議がどの程度進んでいるのか伺うものであります。
通告しております2件目でございます。
平成24年5月26日の新聞報道を受け、28日の私どもに対する全員協議会では事実を村長は話しておらないと思っております。資料一つ出さず口頭のみに終始したわけはなぜでありましょう。平成25年第2回定例会6月議会で村長は「資料を出さなければならないという規定は何もない。口頭で説明しているから問題はない」と答弁しております。私は、事の重大さを明らかにしたくないがために口頭説明に終始したと理解をいたしております。違いますか、村長。元職員の500万前後の横領がありながら、2件の上下水道料金、1件の水道加入金、合わせた90万六千幾らかのことにだけ絞った話しかしませんでした。私は、最初からきちんと資料で全容を明らかにし、今後の防止策をきちんと示していただければ我々は今までここまで引きずることはなかったというふうに思っております。
2点目、5月28日の全員協議会で、97万何がしの件だけ私どもに説明をしました。26日が新聞報道ですから、新聞報道される前の5月9日に400万5,217円を弁済されている事実がありながら、何ゆえ私どもの全員協議会で話さなかったのでしょうか。400万円の弁済された事実を村長は知っていながらなぜ報告しなかったのでしょうか。過去の25年6月議会で私の一般質問に「そのことについては通告されていないから答弁しない」と話しておりましたが、今回通告して答弁を求めておりますので、その事実をお話しください。
3点目、給水条例の中に開発負担金取扱規程がありますが、平成20年度から24年度までに給水申請を取り扱った中で、負担金を一部免除や全額免除をした経緯があるのかないのかお伺いをいたします。
また、98条特別委員会の中で、今回の事件が明らかになる前に私は年度ごとの給水装置の新設申請件数を調査したことがありますけれども、件数で大きな差があるように思いますので、管理台帳等にそういうものが欠落しているのではないかと考えますけれども、その辺は事実がどうなのかお伺いをいたすものでございます。よろしくお願いいたします。
議長(萩原達雄君) 村長、答弁願います。
〔村長 跡部昌洋君 登壇〕
村長(跡部昌洋君) お答えいたします。
塩浪地区団地整備につきましては、過日の議会全員協議会でも説明させていただきました。整備販売について、当初民間事業代行方式として執行することを計画し、プロポーザル方式によって事業代行者を公募したところでありましたが、結果的には希望者がなかったために整備手法を大衡村直営に切りかえるということで、これも議会の皆さん方にお話をし、ご理解をいただいたと。そこからまた一歩一歩前に進んでいるということでございます。
したがいまして、造成工事につきましては村発注により施工することとなっておりますが、ご質問の工事の施工監理につきましてはこれまでも実施してきましたし、地域活性化交流館施設整備事業や大瓜工業団地造成事業などと同じですので、村が直接施工監理する計画でございます。今までも造成工事については村が監理をしておりますので、あえて今回も村が今までどおりの監理をしてまいりたいと、このように思っております。
次に、造成工事に向けた各種手続の状況でありますが、現在、都市計画法に基づく地区計画の変更の手続を進めております。これにつきましては計画案の縦覧を行うとともに、12月2日に住民説明会を開催しており、これらの結果を踏まえて現在、宮城県へ事前照会を行っているところで、来月中には手続が完了する、そのようになっておるようでございます。
また、これと並行して、住宅団地整備に係る測量調査、設計を進めており、この作業がまとまり次第、森林法に基づく林地開発届出及び都市計画法に基づいて開発許可申請を行うこととしておりますので、造成工事着手まで許可を得る予定になっております。
下水道処理区域の変更につきましては、吉田川流域下水道の計画見直しに合わせて平成27年度内に事業許可変更などの手続を行う予定にしておりますので、これまで県と事前打ち合わせを行っております。下水道につきましては、造成工事完了後の平成28年度での工事を予定しております。工事着手までの事業許認可変更の手続が完了するようにも進めております。
次に、この地区のため池のかさ上げの関係でありますけれども、防災調整池の整備に係る地元水利組合との協議でありますけれども、これまで地元水利組合による利用形態について聞き取りをさせていただいております。これを参考に、ため池の機能を確保した防災調整池とすることで現在、測量調査、設計を進めているところでございます。水利組合へは設計案ができた段階で相談をさせていただくということで、水利組合さんとも了解を得ているということでございます。
次に、公金横領事件の関係でありますけれども、まずもってこれまでも何回となく謝罪をしてまいりましたが、これまでの報道などで議会、住民の皆さん方に大変ご迷惑をおかけしましたことに改めておわびを申し上げたいと思います。
1点、2点目の質問でありますが、これについても同年9月、齋藤議員の一般質問の中で、当時、担当課長あるいは私がお答えしたとおりでありまして、調査中ということでお答えをしております。
3点目の質問につきましては、開発負担金を免除した実績はないという報告でございます。
4点目につきまして、ちょっと意味がわからないんですよ。98条の検査特別委員会での作成したものの中の、ちょっとこれ意味わかりませんので、また後で質問をし次第、お答えをしてまいりたい、このように思っております。以上です。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 団地の区画整理のほうから質問をいたしますけれども、今村長が、役場が直接施工監理をしていくと。それなりに人事配置等でいろいろされているんだろうと思いますけれども、そうした場合に異動させてやっていますけれども、専門に、もう現場に張りつくように、そういう形での施工監理をしていくのか、それとも役場庁舎内に自分の席を置いてそこから現場にちょこちょこ行ってみるという、そういう形なのか。村長の考えはどういうふうに思っているのか、その辺をお聞かせいただきます。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 何ら今までと変わりないと思います。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) その計画を見ますと非常に盛り土、高低差がある計画なものですから、やはり村が造成を進める。過去のほかの自治体であったように地盤沈下したり、結局業者さんもそれなりに成果を出していかなければならないし、経営としての考え方もしなくてはならない。そういう面ではこの2カ年で一気に進めていくと。そういった中で、担当職員なり施工監理する役場が見えないところで進められると、余計な心配かもしれませんけれども、そういう危険率があるんじゃないかと思うんですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 優秀な大衡村の職員でありますので、ご心配はないと思います。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) それで安心しました。それで村が直接造成を進める。それで、分譲完了まで村がかかわっていくのか、業者さんに分譲関係を委託するのか、その辺はどうなんでしょうか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 担当課長から答弁をさせます。
議長(萩原達雄君) 都市整備課長。
都市整備課長(松木浩一君) ご質問の分譲につきましては、現在、委託業務ということで、直営じゃなくて専門の業者にその辺を委託していきたいというふうに考えてございます。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 私も村が直接分譲にかかわるんだったら大変だなと思ったものですから、委託をして進めていきたいということであれば安心をいたしました。
それでは、水利組合といろいろ協議という話ですけれども、私もこの質問をつくるに当たって、苗代沢ため池がどういう状況なのかなと思ってため池台帳を調べてみたんですけれども、そこには載っていないんですよね。平成2年の県農政部で調査したため池台帳に載っていないということで、村はその辺はどういうふうに判断していますか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 担当課長から答弁いたします。
議長(萩原達雄君) 都市整備課長。
都市整備課長(松木浩一君) お答えいたします。
所管であります農林建設課の農林班のほうに確認して、うちのほうでは村の底地、村のため池だということで把握してございます。実際、水利組合、どこで管理しているんだというその辺お聞きして、代表の方とどういうふうな今利用形態になっているかということで事前にお話を聞かせて、常時は使っていないため池でございますが、夏場の渇水期等に水が不足した場合使っているんだということで、堤体等も組合の方が来て草刈り等の維持管理はやっているということも把握してございます。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 現在、転作化率がこのように進んでおりますと、そのため池の必要性、今課長が言ったように現在使っていないんだろうと思いますけれども、いずれ近い将来的に転作がなくなると、そういった場合、農家の営農意欲が強くなって作付をしたいというふうになってきた場合は、当然農業用水としての利用も出てくるんだろうと思います。そういうことが支障ないように、その辺にそういう形で一体どのぐらいの、もともと苗代沢ため池の貯水量というか、私も「あれっ、これ何で載っていないんだ」と不思議に思ったんですけれども、その辺をきちんと把握して、その辺を県のほうにため池台帳にぜひ載せていただくように相談するということが必要かと思うんですけれども、いかがでしょうか。
議長(萩原達雄君) 都市整備課長。
都市整備課長(松木浩一君) お答えいたします。
現在、村長答弁のとおり、現場において測量調査、本日はボーリング調査をやってございますが、そういった中で水利組合さんのほうの機能を担保できるような構造で設計ができ次第、水利組合さんと説明会を開催していきたいというふうに思っております。
それから、ため池台帳の件につきましては、農林建設課の農林班を通じてその辺を適切に処理できるように内部で協議してまいりたいというふうに思っております。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 苗代沢ため池を使っての洪水調整、防災調整をしていきたい。そういった場合に、下流の善川に当然放流されるんだと思うんですけれども、その際、放水量というか、放流に当たっての県との協議というのは必要になってくるんですか、必要ないのか、その辺をお伺いします。
議長(萩原達雄君) 都市整備課長。
都市整備課長(松木浩一君) お答えいたします。
当該地の雨水排水の計画につきましては2系統ございます。工業団地西線のほうの東側のエリア、鉄塔の東側のエリアは工業団地西線にございます雨水管600ミリ、これに道路側溝を通じて接続させて、県でつくった奥田川防災調整池のほうに誘導します。奥田川を通して善川に流れると。もう一方の鉄塔の東側のエリアにつきましては、今お話ししている下にございます苗代沢ため池をかさ上げして善川に持っていくと。
ご質問のように、ここにつきましては宮城県河川課防災調整池、200年に一度の雨の確率でも対応できるというようなことで設計を組まなければなりません。事前協議は既に終えてございまして、今、測量等を含めて詳細設計をやっているということで、宮城県河川課との協議も許可もその中でとっていくと。事前協議は既に終わってございます。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 先日というか、ちょっと前にこの団地造成に係る地元説明会を開催したようでございますけれども、その際、地元からの要望というものが出たのか出ないのか。出たとすれば何か。一つや二つで結構ですから教えていただきます。
議長(萩原達雄君) 都市整備課長。
都市整備課長(松木浩一君) お答えいたします。
今月の12月2日にこの団地整備計画の説明会を平林会館和室で開催してございます。この説明会は、都市計画の地区計画の変更の手続を進めてございますけれども、その中の公聴会の一部の位置づけもしているものでございます。夜分にかかわらず十数名の方が説明を聞きに来ていただきました。
主なものでございますが、衡下地区からも二、三名来ていただきまして、先ほど質問ございましたように、雨のときの雨水洪水対策等々のご質問をいただいておりまして、今申し上げたような形で排水計画を立てているということでご説明をさせていただいております。あとは近隣のときわ台の方等々の出席もいただいておりまして、将来的な団地の防災というのか、保安というんですか、街灯とかそういったものも将来は必要になってくるんだよというようなアドバイスをいただいたような説明会となってございます。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 私の地元からも洪水の関係のお話を受けていたものですから、参加したという話を聞いたものですから、意見が出たとすれば結構だというふうに思います。
それでは、次の通告の案件について質問をいたします。
書類を一切出さないで口頭説明のみに終始した。それは何も資料を出さなければならないという決まり、規定はないと言い切りましたけれども、村長は事の重大さをどのように認識しておられますか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 先ほど申したとおり、それ以上のことは答弁を控えさせていただきたいと思います。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 答弁は控える。いろいろ考え方があるからしようがありませんけれども、私ども仲間の議員、書類何一つなく説明を受けたんですよ。その説明を受けても理解するには時間が必要ですし、結局それを理解するには会議録しかないんですよ、言った、言わないになるし、会議録に残っていますから。そうでしょう。公金ですよ。役場が予算・決算をつくるでも、1円たりとて合わなければ予算組めないでしょう。それが何百万という大金がこういうふうになったのに書類一切を出さない。私は村長が余りにも議会を軽視している、そう思う一人です。そうじゃありませんか。やはりきちんと、起きてしまったのは仕方ないから、今後こういう防止策なりそれで進めるから理解をしていただきたいというならわかるんですよ。私はそう思うんです。ですから、村長は余りにも甘く考えている。じゃ10万ならいいんですか。100万ならだめだとかそんなことないでしょう。1円たりとも公金は公金ですよ。それを書類一切出さないで、出さなければならないという規定はないと、そんなことは絶対おかしいですよ。そういう考えですから、ここまで来てしまったものだと私は思っています。
それから、5月28日の全員協議会で、26日に載った新聞の関係で説明を受けました。そして私も28日の全員協議会の会議録をずっと何回も読みました。しかし、97万何がしの説明を村長なり担当課長なり、当日そこの会議に入った課長たちはお話ししました。しかし、何ですか。5月9日に400万返されている、弁済されているという事実があったんじゃないですか。400万に一言も触れないで97万だけ説明する、それはどういうことだったんですか。悔しいですよ。残念ですよ。そんなことはあってはならないでしょう。なぜ400万をこれこれに弁済されましたと。村長はその400万、弁済されたとき決裁したんでしょう。どうですか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 告発されている身ですから、それ以上のことはお答えを控えさせていただきます。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 当然400万弁済されれば伝票つけて書類は整理していかなければならないんですから、村長は当然決裁するでしょう。それなのにその400万に一言も触れていない。我々同僚議員が新聞報道の400万という数字。それは金庫に入ったんですかと言えば、それは誤報だとまで言った。なぜ本当のことを言って。さっき私言ったでしょう。起きてしまったことはしようがないから、今後どうすれば防止策がなるのか、そういうふうに話を進めないとおかしいと思うんですよ。その400万を聞けば、今、検察庁に行っているからどうのこうのとありますから、決裁したのかしないか私は聞いているんです。わかるでしょう。なぜできないんですか。そのとき決裁したかしないかだけ聞いている。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 先ほど申し上げたとおりでございます。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 多分仲間の皆さんも、そういうのは非常に残念に思っているんですよ。書類何も見せられない。そして28日の説明会、そしていろいろ後から書類をとってみると、何だ5月9日に返されているんだやと。我々説明には、不審なデータがパソコンに残っているそう。それは400万とは別なものですか。どうでしょうか。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 先ほど申したとおりであります。
議長さん、この件については司法のほうにも行っているものですから、私あえて質問されても答えようがございませんので、お諮りをいただきたいと思います。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎議員、今、村長からそういうお話ですが、質問の角度を変えて。齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 前に質問したときに、まだ本還付をいただいていないと、書類関係。それで、この水道関係の事業を進めるに当たって、今職員の皆さん頑張っていただいているものだと思いますけれども、こんなに本還付を受けていないで今の仕事なり支障がないものか。それはどうなんでしょう。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 担当課長に答弁をさせます。
議長(萩原達雄君) 都市整備課長。
都市整備課長(松木浩一君) 現在の水道事業の業務については、支障は来してございません。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) じゃ台帳関係なんかもどういう形で把握というか管理というか、それはパソコンに残っているデータでのいろいろな仕事上進めていらっしゃるのか、そこだけお伺いします。
議長(萩原達雄君) 都市整備課長。
都市整備課長(松木浩一君) 一連の流れにつきましては、会計規定にのっとって業務を進めてございます。
多分お伺いしたい点につきましては、毎月の監査にその点詳しく給水申し込み状況等を例月の出納検査のほうに逐次報告している状況でございます。
議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。
4番(齋藤一郎君) 私も質問をやめますけれども、やはり職員も絶対ミスが起こらないとは限りませんけれども、傷口は浅いうちに早く手当てをして、私ども議会にもきちんと説明をして、なぜそれが起きてしまったか、その防止策なりを説明して議会にも、住民代表として出ている議員にもそのことを理解してもらう、そのような形でぜひこれから進めていただきたい。
それをお願いして質問を終わります。
議長(萩原達雄君) ここで休憩いたします。
再開は3時50分といたします。
午後3時38分休憩
午後3時50分再開
議長(萩原達雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続けます。
通告順7番、佐藤 貢君、登壇願います。
〔3番 佐藤 貢君 登壇〕
3番(佐藤 貢君) 通告7番、佐藤 貢です。2件通告しておりますので、一問一答で質問いたします。
1件目、自然・歴史・文化を生かしたまちづくりを進めてはと題し質問をいたします。
今、大衡村は自動車関連企業を中心に企業立地が増加しており、富県宮城の具現化に向け一歩一歩前進しております。また住宅構想についても、人口の増加、定住化促進に向け住宅団地開発計画が着実に進められており、第5次総合計画に基づいた大衡村の姿が大きく変貌を遂げたと確信しているところでございます。
観光面においても昭和万葉の森、万葉クリエートパーク、おおひら万葉パークゴルフ場など、大衡村の観光スポットとして多くの方々に親しまれていますが、さらに地域の観光資源を生かしたまちづくりを進めてはどうかと、その3点について質問をいたします。
1点目として、平成20年における村民の意識調査によると、大衡村の自慢は「緑豊かで自然が多い」が最も高く評価されています。昭和万葉の森を初め牛野ダム湖畔公園、春はお花見、夏はキャンプ、秋は芋煮会と、四季折々の楽しみがある人気スポットです。その近くには大衡村で一番高い山、達居森があり、標高約260メートルと、比較的気軽な登山コースとして村民にも愛され、特に中高年の方々には大変人気のあるスポットであります。また大衡中央公園、大衡城跡を初め桜の名所も数多くあり、このような自然豊かな観光名所をどう管理しているのか、また今後どのような維持管理を行っていくのか。
2点目として、村内には数多くの歴史的資源が残存しております。以前、大衡村には奥州街道や羽後街道が走っており、今もその面影が一部残っており、その跡地をたどって歩く人たちの姿が多く見受けられます。ほかにも縄文式文化遺跡、由緒ある神社・仏閣など、これらの歴史資源をどのように残していくのか。また、村の文化財に指定されている須岐神社、伝統芸能である大瓜神楽、さらには村の創作舞踊である万葉踊り、また新たな伝統文化の創作として取り組んでいる和太鼓、そして大衡村の食文化といった伝統文化を今後どのように後世に伝えていくのか。特に大瓜神楽においては後継者不足といった課題もあり、この現状をどう考えるのか、また村としてどう対応していくのか。
3点目として、大衡村の豊かな自然との触れ合い、地域の歴史、伝統文化を学び、次世代に伝えていくことが大事だと思いますが、郷土教育の一環として自然・歴史・伝統・文化といった大衡村の魅力、地域の魅力を学び体験していくことが必要だと思います。村の生涯学習事業計画にも取り入れて実践してみてはどうか。
以上、この3点について村長の見解をお伺いします。
次に2件目。タクシー利用券を高齢者世帯にも交付してはどうかと題し質問いたします。
今、少子高齢化が進み、高齢者人口がふえている中、大衡村においては高齢にもかかわらずみずから車を運転し、用足しをしたりスポーツを楽しむといったまだまだ元気なお年寄りもたくさんおりますが、その反面、通院を繰り返したり、歩くことが困難な年老いた夫婦、あるいはひとり暮らしの高齢者世帯が少なくないのも現状です。黒川郡内の病院に行くのも買い物に行くのも、今は大変便利な住民バスもありますが、それを利用しても約1日かかってしまう。交通手段としてタクシー券を一番必要とされるのは運転免許を持たない高齢者かもしれません。こういった高齢者世帯を対象としたタクシー利用料金の一部を助成してはどうか。村長の考えをお伺いします。
議長(萩原達雄君) 村長、答弁願います。
〔村長 跡部昌洋君 登壇〕
村長(跡部昌洋君) お答えをいたします。
1番目の自然・文化・歴史と題してのご質問でありますが、これは後から教育長が答弁をいたします。
まずもってタクシー利用券を高齢者世帯にも交付してはどうかというご質問でありますけれども、少子高齢化の時代がよくこのような言葉で言われておりまして、少子化と高齢化を比べると、子供たちが少ないから高齢化率がなおさら高くなってきているということも言えると思います。そういう中で、どこの自治体においても高齢人口がふえているというのが現状であります。
本村における65歳以上の高齢者は、ことし3月末現在で1,386人、全人口の24%、このうちひとり暮らしを含む高齢者のみの世帯、ひとり暮らしの世帯が222世帯で12%となっております。総人口に占める65歳以上の割合は35市町村の中で27番目ということでございますので、恐らく皆様方、えっこんなに大衡村の高齢化率低いのと、そう思われる方がほとんどだと思いますけれども、27番目に位置されておるということです。
ご質問の運転免許を持たない高齢者の方々にタクシー券の利用料金の一部の助成をしたらいいんでないかという話でありますけれども、交通手段を持たない方々の足を確保するために今までも万葉バスや代替バスの駒場線を運行しております。さらには、高速バスの運行や三本木線を大崎から大衡まで延伸してもらっております。万葉バスや駒場バスにつきましては、平成23年度から利用料金を200円から100円というふうに下げまして、利用者の利便性を図っているところでございます。
また、公的支援につきましても、要介護認定を受けている方につきましてはケアプランの中で、病院などへの通院をするための補助として障害者手帳をお持ちの方にはバスやタクシーの割引制度があると。私余りこれ知らなかったんです。あるようであります。ですから、免許を持たない高齢者の方々への交通手段としてどのような方法がよいのか、どのような制度を利用していったほうがよいのか、これから調査をしてまいりたいと思いますので、どうか一緒に佐藤議員も調査に入って、少しいい情報を伝えていただければありがたいなというふうに思っております。
あとは教育長から答弁いたします。
議長(萩原達雄君) 庄子教育長、答弁願います。
〔教育長 庄子明宏君 登壇〕
教育長(庄子明宏君) それでは、私のほうから自然・歴史・文化を生かしたまちづくりを進めてはということについてお答えしたいと思います。
これまでつくり上げられた諸先輩方の業績について、簡単に変更することはなかなか難しいなとまず考えております。しかしながら、ここまで来られた中をもう一度考えてみますと、1番目の万葉の森、達居山等の自然環境の保全、維持管理については次のように考えられます。大衡村は、豊かな自然環境に恵まれており、昭和万葉の森や達居森を初め万葉クリエートパークや牛野ダムキャンプ場、これらは仙台都市圏を見越したレクリエーションの拠点として位置づけられておると考えています。自然の景観を生かした憩いの場として親しまれていると考えております。最近では大型連休、土日、そして祝日などにおいては、仙台圏を超えた県内外からたくさんの家族連れが来てにぎわっている状況であります。
第5次総合計画や国土利用計画、また都市整備課のほうで作成しておりますマスタープランにより計画している中心市街地の西部・東部地域の森林や農地については、里山としての活用や景観資源としての活用を図るなど、自然環境の保全と調和した活用を行うこととしております。
なお、万葉の森につきましては、今後も県の指定管理者であります万葉まちづくりセンターの管理のもと、適切に森林等を含め施設の維持管理を徹底し、相乗効果を高めてまいりたいと考えております。
また、達居森につきましても昭和53年に遊歩道を整備し、平成13年に大規模な歩道の改修を行っております。引き続きこれらの施設の点検とあわせて森林の育成状況を把握し、保全のため必要であれば間伐や保育を行うことを今後検討してまいりたいと思います。
豊かな自然を生かしたレクリエーションの場である昭和万葉の森や達居森は、自然環境や良好な景観を保全、活用しながら広域的な観光地として利用促進を図っていきたいと考えております。
2つ目になりますけれども、本村指定の文化財は3件であります。無形文化財の大瓜神楽、有形文化財の須岐神社、史跡の大衡城址があります。さらに村内には86カ所の遺跡が点在し、県より文化財保護管理指導者対象の埋蔵文化財包蔵地に指定されています。村では毎年、管理指導対象の遺跡から5件を選定し、村文化財保護委員の立ち会いのもと現地確認調査を行い、その調査概要を県文化財保護課へ報告しております。
文化財は村の貴重な財産であり、その保存については次の世代に伝承・継承することが求められておりますので、今後さらにどのような対策が必要なのか、県文化財保護課などと相談しながら保存に努めてまいりたいと考えております。
また、大瓜神楽などの伝統文化については、できるだけ多くの方に保存の必要性を認識してもらうため、お祭りでの披露など触れる機会をふやし、継続的に取り組む必要があると考えております。
3つ目になりますが、生涯学習への取り組みといたしましては、今年度はレディーススクール及びメンズスクールにおいて村の文化財をめぐる学習の機会を設定し、実施しております。
これからも生涯学習事業において村の歴史を学ぶ機会を設け、子供から大人までの各種事業に取り組み、できるだけ多くの方に学ぶ機会を提供してまいりたいと思います。また、大衡城青少年交流館の民俗資料館の展示室や役場玄関ホールなどの展示スペースを有効に活用し、村の歴史資料や埋蔵文化財などの展示を行い、村民の皆様や来村者に幅広く文化財の情報を発信したいと考えております。
議長(萩原達雄君) 佐藤 貢君。
3番(佐藤 貢君) 件名1のほうから質問します。
今、教育長のほうから、大衡村にも遺跡・史跡・名所がたくさんあると、観光名所もいっぱいあるということを聞いたんですが、私もすばらしい大衡の財産でもあると思うんですが、割と県内を初め村内に住んでいる方にも余り、知っている人は知っている、知らない人は知らない、そういったイメージがあると思うんですよ。それで村のホームページでも、ある程度の資料はあるんですが、ただ、その場所がよくわからない。それで例えば大衡村に観光に来てそういう資料というかパンフレット、観光案内を求めようとしてもどこに行ってそれが手に入るのか、もらえるのか、それがよくわからないという方もいると思いますので、何といいますかね、そういったものを配置しておく施設等、例えばパークゴルフ場とかおおひら館にもあることはあるんですけれども、何か余り目立たない、隅のほうに置かれているというような印象も見受けられます。ですから、大衡村を散策あるいは史跡をめぐるにしても何かのマップといいますか地図といいますか、そういったものも必要ではないのかな。そういった資料を目につくところに置くのもいいのかなと思いますけれども、その点いかがでしょうか。
議長(萩原達雄君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) 最初に、今ご指摘ありました、質問ありました3点の課題について、共通してやらなければならないなと考えていることがあります。それは文化財の保護と文化財の学習はやっぱり連携した一つの取り組みとしてやっていかなければならないというふうに考えています。そのためにどうすればいいかということになりますけれども、4月にここに参りましてからやはり私も同じようなことを思うようなことがたくさんありまして、大衡村の資料を集めてはみたのですが、歴史資料と文化財資料と、それから工業団地周辺の資料、パークゴルフ場周辺の資料というのがみんなばらばらになっていて、なかなか扱いにくいなということがありました。
それから、生涯学習を通して小学校、中学校、そして大人まで使えるような資料でなければならないという点もあると思います。そういう意味で、先ほどマップというお話が出てきましたけれども、大き目のマップをつくりまして、まだ名前はつけておりません。一応今のところ大衡村何でもマップというか、そのような形で考えておりますけれども、つくりまして、ちょうど小学生も総合的な学習の中で、村を回って自分たちの村を勉強するという機会があります。それから中学校に行けば社会科のほうで、自分のまちの歴史を知るというふうな項目もあります。そんなようなこと。
それから、最も根本的なことだと思うんですけれども、先ほどもご指摘あったように、大衡村の人が大衡村を知らないんじゃないかというところが非常に大きな課題でもあるような気がしてなりません。そういう意味でもただの地図ではなくて、ここに行けばこのような史跡がある、このような店がある、このような活動ができるところがある、ここに来れば健康増進のために登れる山がある、そういった多角的に見たマップをつくることを考えて今いる段階です。できればそれを今度、役場のエントランスホールがリニューアルオープンということもありますので、電光掲示板だけで示されてもなかなか次に行く機会はないと思いますので、そこにそのような地図を置いて持っていっていただいて、よりよく活動してもらえるということが考えられると思います。それから、大衡村に研修に来る方々に対しても、そのマップ一つでおよそのことがわかるかなというふうな、ちょっと欲張ったものではありますけれども、今そんな形で学習と文化財の管理というのを一つに考えてやっていくことで佐藤議員さんがおっしゃった自然・歴史・文化を生かしたまちづくりを進める一環になるのではないかなというふうに考えて進めております。
議長(萩原達雄君) 佐藤 貢君。
3番(佐藤 貢君) 今、教育長の答弁で、庁舎の玄関ロビーにもそういう大きいマップをつけるということで、これは大変いいことではないかなというふうに思います。
それで、一番は例えば村内にいる方もちょっとわからない人もいるかもしれませんけれども、今、大衡村に県外から住みついている方も結構いるんですよね。そういった方が大衡村に来た以上は大衡村の名所とか歴史とかそういったものを知りたいというときに、何かちょっとまだPRが足りないというか、そういう学習する場も少ないかもしれませんけれども、そういったものを考慮してPRすること、周知していくことにもう少し努力されたほうがいいのではないかと思いますけれども、今後そういう周知活動みたいなことについてはどのように考えているかお聞きしたいと思います。
議長(萩原達雄君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) まず、小中学校につきましては先ほどお話ししたとおりでございます。先ほど考えられる大衡村の何でもマップというのを、観光だけではなく歴史の勉強にも使えるようにつくっていくと、そして授業の中で実際に展開していくということがまず一つだと思います。その次だと、それもやっぱり大衡村の住民の方々全員に、1戸に1枚ずつそれを渡して理解していただくということもまず一つだと思いますし、そしてまた、それをもとにツアーを組んで回るというのも考えられるかなというふうにも思います。今のところここまでしか考えておりませんけれども、さらに議員の皆さんのお知恵を拝借しながら検討してまいりたいなというふうに思っております。
議長(萩原達雄君) 佐藤 貢君。
3番(佐藤 貢君) それから、大衡村の伝統文化であります大瓜神楽、万葉踊り、あるいは今で言いますと和太鼓、そういったものを継続的に育成していくためにも、ある程度、村の行事、イベント、そういったものにも積極的に参加していただくことによって団体の存在意識、あるいは士気を高めることにもつながるんではないかと思いますけれども、その辺どのようなお考えなのかお伺いしたいと思います。
議長(萩原達雄君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) ご指摘のとおりだと思います。ただ、和太鼓は今上り調子なんですけれども、指導者がいなくなったときの継続というのは非常に難しいところがあるので、今大切なところは後継者をしっかりとつくらなければいけないと。これは和太鼓でも大瓜神楽でもそれから万葉踊りでも同じことが言えると思います。全く人材が、ちょうどその中堅たる人がなかなか見つからなくて保存が難しくなっているのが現状だと思います。
大瓜神楽につきましては、11月に大瓜神楽の会長さんとお話し合いをしまして、今後の大瓜神楽の運営等について相談をいたしました。結果的には大瓜神楽は大瓜上の方が管理をしているというか、保存会の中でやっているということなので、もう少し私たちに任せてもらえないだろうかというふうなお話をいただいてはおりますけれども、今後やはり後継者が少なくなった折には一緒に考えていかなければならないものかなというふうに考えております。
議長(萩原達雄君) 佐藤 貢君。
3番(佐藤 貢君) このように大衡村を幅広くPRして、大衡村の魅力を県内外に知ってもらうということがこれからの人口の確保あるいは定住化にも期待ができるのではないかというふうに思いますけれども、そういった考えを村長にお伺いしたいと思います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) タクシー料金については……あっ、それはさっき教育長が答弁したとおりです。
議長(萩原達雄君) もう一回。
3番(佐藤 貢君) 大衡村のそういうイメージを広くアピールすることによって、みんなに大衡村のよさを知ってもらうことによって人口の確保、増加するかどうかわかりませんけれども、知っていただくと。定住化にもつながるのではないかということで村長さんのお考えをお聞きしたいと思います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 教育長が答弁したとおりでございまして、それ以上のことはございません。
議長(萩原達雄君) 佐藤 貢君。
3番(佐藤 貢君) わかりました。じゃ次、タクシー券のほうに行きます。
村のほうで、そういう健康なお年寄りもいっぱいいると思いますけれども、例えば病気したり通院したり買い物、足がない、そういう人たちというのは、年齢が何歳じゃなくて、免許もなくて交通手段に不便さを感じている人たちというのは大体何割ぐらいいるか把握しているんであれば教えていただきたいと思います。
議長(萩原達雄君) 村長。
議長(萩原達雄君) 担当課長から。
議長(萩原達雄君) 担当課長、誰だ。保健福祉課長。
保健福祉課長(高嶋由美君) 今、障害者の計画の中で調査をしておりますが、それは障害者の中で調査しております。それからあと、介護保険の計画の中で今調査しておって集計中ではございますが、そのような確実な数というのは把握してございませんが、恐らくひとり暮らし、2人暮らし、あと3人暮らしのお年寄りのほかに、ご家族の中でも日中誰もいらっしゃらなくて、そして移動手段のない方というのもいらっしゃると思いますので、これから調査したいと思います。
議長(萩原達雄君) 佐藤 貢君。
3番(佐藤 貢君) 先ほど村長の答弁で、大衡村には住民バスもあるし高速バスも通っているし何でもありますよと。いいんですか、課長、こっち向いて。課長に向って言っていいんですか。それは当然大変便利よくていいんですけれども、ただ、それは時間が決まっているもので、例えば仙台のほうの病院に行っている方も若干はいると思うんです。そうした場合、吉岡の宮城交通まで行きたいんだけれども、その時間帯に合ったバスがなかった場合なんかはやはりタクシー券があれば行けるという人も多少はいると思うんです。
この間の新聞で、一応新聞記事持ってきたんですけれども、大崎市の三本木、あそこでタクシー会社と契約して巡回バスを始めたという新聞記事が載っていますけれども、村長、新聞記事を見ていますよね。河北新報に載っていたけれども、このようにタクシー車両を利用した住民バスじゃなくて、例えばこの記事によりますと「1時間に2台ずつ1日計9便が地域を守り、運転免許を持たない高齢者の交通手段として活躍しています」というように実際に実施されているんですけれども、大衡村でそれを必ずまねることはないと思うんですが、せっかくのタクシー券があるものですから、それをもう少し拡大解釈して、そういう困っている年寄りにも交付するという考えはないのかというのが私の今回の質問の一番言いたいところなんですけれども、その点をもう一回お伺いしたいと思います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 私初めて見ましたけれども、こういうのも一つの車両活用方法ということでここに載っておりますけれども、なるほどなと今見させていただきました。
いずれにしろ、高齢の方々が今免許を持たない、持たせられないんですよ、持たないというより持たされないんですよ。ですから、そこをじゃどうしようかということも一つの方法だと思いますし、どこまでその範囲を広めていったほうがいいのか。果たしてタクシー券がいいのか、ここに載っているように高齢者を主体にした巡回バスがいいのかということもいろいろな方法があると思いますので、ぜひこの新聞を見させてもらって、そしてまたまた調査をしながら検討していくのもよろしいんじゃないかなと。検討する価値もあるなと思っております。
議長(萩原達雄君) 佐藤 貢君。
3番(佐藤 貢君) 今後、期待していいような答弁がございましたので、よかったなと思いますけれども、これまでいろいろな高齢者に対しての支援等があると思いますけれども、その内容と今後どのような、こういったタクシー券に関係なく、今からどのような施策をしていくような計画を持っているのか、それを最後にお聞きしたいと思います。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 何、もう一回、もう一回。
3番(佐藤 貢君) 今まで高齢者に対してのそういった支援策と、あとこれからどういうのを高齢者に対してやっていく計画があるのか。計画があるんであれば教えていただきたいと思います。(「検討すっとや」の声あり)いや、検討じゃなくて実績。
議長(萩原達雄君) 村長。
村長(跡部昌洋君) 今、タクシーの券かと思って聞いていたら別な角度に行ったものですから、何ふうに答えたらいいのかなと思っておりましたけれども、これからの福祉関係の検討はまだしておりません。今までのやつを継続しながら、そして次に、今お話にあったタクシー券をどうするかという宿題をいただいておりますので、その宿題をどうしていくのかというのも来年度に向かった、あるいは再来年度に向かった、その次の年に向かったことも考えていかなくてはならないのかなというふうに思っております。
いずれにしろ、佐藤議員のお話も参考にしながら、そしてよりよい財源を見てやっていきたいというふうに思っております。
議長(萩原達雄君) 佐藤 貢議員の一般質問が終わりました。
ここでお諮りいたします。ここで本日の一般質問を終わりとし、引き続き明日も一般質問を続けることといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。よって、本日の日程はこれで全部終了いたしました。
本日はこれで散会といたします。
お疲れさまでした。
午後4時28分散会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
大衡村議会議長
署名議員
署名議員